認知症の方が施設に入居し夕方には、荷物をまとめ「家に帰りたい」と訴えています。
でもどう対応したらいいかわからず、とりあえずその場しのぎの対応をしている。
なんてことはありませんか?
実は、家のような環境づくりをすれば帰宅願望は減っていきます!
認知症の方は環境の変化に対応することが苦手で、結果として不安や混乱を招きやすいです。だからこそ、今までの生活に近づけることが重要なのです。
わたしは、有料老人ホーム等で10年以上働いています。数え切れないほど認知症の方を受け入れてきました。
その方の日々の生活が安定するには「居心地をつくること」が重要と考え、様々な取り組みを行いました。
この記事では、居心地をつくるために必要な「生活習慣」「個性的空間づくり」「人間関係」「三大介護」「役割づくり」の5つの取り組みを実例とともに紹介します。
この記事を読むと、認知症の方が入居した際に最初にやるべきことが見えてきます。また、既存の認知症の方にも効果が見込めます。
80代男性のケース紹介:認知症の帰宅願望に向き合う
80代・男性、要介護3の方です。入居直後から「帰してくれ」と夜間も歩き続ける日々が続きました。家族4人で暮らしていましたが、お子様は独立し、奥様は他界。認知機能の低下により一人暮らしが難しくなり施設へ入居されました。
なぜ自分が施設にいるのか理解できず、不安や混乱が行動に表れていました。ご本人のこれまでの人生やご自宅での生活リズム、人間関係、楽しみを丁寧に把握し、「今までの生活」を施設でも再現する支援から始めました。
家のような施設づくりに必要な5つの取り組み
1.生活習慣を変えない

ご自宅での生活リズムをできる限り継続する
認知症の方にとって、環境や時間の変化は大きな不安になります。
まずご家族に協力をお願いし、ご自宅での1日の流れ(起床・食事・入浴・就寝など)を丁寧に聞き取り、施設でも同様のスケジュールを組みます。※入浴は「夜に入っていた」場合でも大概の施設では日中帯だと思います。施設のルール上、どうしても対応できないときはあります。できる範囲で工夫をします。
自宅では「一人の時間によく音楽を聴いていた」とご家族より情報がありました。
そこで、好きな歌手のCDとCDデッキを居室に用意し、いつものように音楽に耳を傾けられる時間をつくりました。
帰宅願望があるときに居室にご案内し音楽を流すと、目をつぶり落ち着かれる事が何度もあります。
2.個性的な空間づくり
「自分の家」に近づける工夫を
施設入居時には、自宅で使用していた家具などをできるだけ持参してもらいました。なかでも、ソファーが一番お気に入りとのことで、必須で持ってきてもらうようにお願いしました。一人のときはソファーに座り、音楽を流して聞いていました。その他にも、昔表彰されたトロフィーも飾りました。物が増えて部屋が多少散らかっても問題ありません。その時のエピソードを話している間は、帰宅願望はありません。話し終わった後は、こわばっていた顔は笑顔になります。
見慣れた物、使い慣れた物に囲まれることで、「ここは私の場所」という感覚が少しずつ育まれていきます。
一人ひとりのお部屋がない施設もあります。その場合でも、寝床(ベッド等)は毎日変えることなく同じところにし、馴染みのある枕や目覚まし時計などを近くに置くようにしましょう。
3.人間関係を変えない

なじみのある人・関係性を新たな環境でも
施設に入ることで、家族や近所とのつながりが薄れるのは避けられません。
施設内で「なじみの関係」ができるまでは、ご家族にお願いをし2.3日に1回の面会をしました。友人の面会でも良いです。
施設での関係性:
・共感してくれる人(他の認知症の方など)
・規範となる人(見本になれる入居者)
・頼れる人(職員や看護スタッフ)
✅ 共感してくれる人=認知症の他入居者
認知症の方は、相手の話を遮ったり否定したりすることが少なく、自然と笑顔(愛想笑い)で対応される場面も多く見られます。これは、会話の内容が正確に理解できていないことが要因とも言われていますが、それでも「否定されない安心感」を与えてくれる存在です。
たとえ名前を覚えていなくても、食事を同じテーブルでとり続けることで「顔なじみ」として安心感が生まれ、落ち着きに繋がります。
✅ 規範となる人=面倒見の良い自立された利用者
新しい環境では「何をどうすればいいか分からない」ことが多いもの。そんな時、何をするのかを教えてくれる利用者がいると、認知症の方も安心して行動を真似することができます。
関係性が築かれることで、その方が“頼れる仲間”となり、集団生活への参加意欲も高まります。
✅ 困ったときに頼れる人=介護職員やスタッフ
介護職員との信頼関係も、日々のケア(入浴・排泄・食事など)を通じて少しずつ構築されていきます。認知症の方が不安そうにしている場面や困っている時には、すかさず声をかけ、手助けをすることが重要です。
小さな積み重ねが「ここにいれば安心」という信頼に変わり、認知症の方の生活の安定に繋がっていきます。
このような関係づくりを通じて、「ここでの生活も悪くない」と感じてもらえるような環境を整えましょう。
認知症の方といっても、症状は軽度から重度まであります。この方は、自分の意思を伝えたり相手の話を理解することはできますが、短期記憶がありません。できるだけ、同じ症状の方と一緒に食事をしてもらいました。挨拶程度で多くのことは話しませんでしたが、顔は覚えており廊下ですれ違うと挨拶するようになりました。「知っている人がいる。」安心感があったように感じます。
また、施設内で会うごとに「○○さん、おはようございます。」とスタッフが名前を呼ぶようにしました。「おー!」と勢いよく返ってくるようになりました。名前を呼ばれることで「自分の事を知ってくれている。」と感じてもらえた気がします。
4.三大介護を“今まで通り”行う

食事・排泄・入浴を「できることは自分で」
認知症の方にとって、「今までどおりの生活」を送ってもらう事が大切です。
食事・排泄・入浴という三大介護も、無理に特別対応するより、今まで通りの流れを重視しましょう。
トイレに行ける方をベッド上でおむつ交換や、個浴に入れる方を機械浴など。これは、今まで通りの生活とは言えません。
実際、「はっきりとADLがわかっていないからまずは機械浴で」と入居前に施設で話し合われていましたが、「はっきりしていないからこそ個浴でしょ。慣れない機械浴のほうが不安にさせるのでは。」と個浴に変更。結果として、入浴後毎回「いい湯だった。」と仰っています。帰宅願望がある方は、自分で荷造りをしたり歩き回ったりと、ADLが高い場合が多いです。尚更、できることは今まで通りやってもらいましょう。
5.一人ひとりの役割づくり

その方の強みに着目しよう
この方は、かつて「土いじり」が好きだったとご家族から伺いました。
今でもできるのか、意欲があるのか未知数でしたが、「とりあえずやってみよう!」と施設の屋上にある庭園に本人専用のスペースを設け、植物の世話を日課にしていただきました。
最初はスタッフの声かけが必要でしたが、やがて自発的に水やりや植物の成長の確認をされるように。
その姿は、まるで「我が家の庭仕事をする日常」そのものでした。
役割作りの着眼点
・かつてやってきたこと(趣味、仕事等)
・今の身体でできること
・周りから認められること
(「◯さん、手先が器用ですね。」その場合、野菜の皮むき等の役割を担ってもらう)
本人のできることを多く知っておくと、良い効果があります。
実際、帰宅願望がある方が「帰ります!」とスタッフに話しかけて来られた際、「家の鍵はありますか?」「家までのお金はお持ちですか?」と伺います。「ないです。」と仰った際、「こちらで準備しますので、お待ちいただいてもいいですか。」とその間、本人のできることをやってもらっていました。今回だと、居室で音楽を聞いてもらったり、水やりをやってもらったり。その期間、帰宅願望はなく目の前のことに集中されます。「もうやりました。帰ります。」と再度いらっしゃった場合でも、いくつかストックを持っておくと対応しやすいです。本人の強みにもアプローチできているので、一石二鳥です。
家のような施設づくりをした結果
最初は「自分の家ではない」と感じて、居室に戻らず施設内を徘徊していましたが、本人に合った居室環境と生活支援によって居心地が良くなり、徐々に「私の家(居室)に勝手に入ってこないでくれ」と自分の空間を大切にする気持ちの変化が見られました。
3日間で「扉を開けてください」と受付に来た回数は124回でしたが、生活環境を整えた後は61回にまで減りました。
本人にとっても良かったですし、スタッフは「認知症ケアが何か具体的にわかった。」と自信をつけていました。
もちろん人によって環境に馴染みやすい方とそうでない方がいます。すぐには、結果はでないと思ったほうがいいでしょう。今回は、入居されてから9か月かかりました。
ただ、生活習慣や人間関係を尊重し、三大介護の基本に立ち返りつつ、個性的な空間づくりや役割づくりを通じて、認知症の方の帰宅願望を和らげることはできます。声がけの方法も大切ですが、まずは「居心地をつくること」から初めてみましょう。
帰宅願望があった際にしてはいけないこと
1.帰りたい気持ちを頭ごなしに否定する
2.無理に行動を制限する、閉じ込める
3.その場しのぎや曖昧にごまかす
4.嘘をつく
帰りたい気持ちを頭ごなしに否定する
「帰れません。」「無理です。」と言うと、不安や混乱が高まり、より強い帰宅願望や暴言・不穏につながることがあります。
何度も訴えてくるとスタッフ側は「勘弁して。」と苛々が募り、つい言ってしまいそうになります。わたしは実際に、言ったことがあります。ただ、逆効果でした。より時間と労力を使うことになりました。
家のような施設づくりをすると、帰宅願望が減り、自分の気持ちの余裕や「帰りたい。」と仰った際は趣味に没頭してもらうなど対応方法がわかるようになります。
無理に行動を制限する、閉じ込める
施設内で外に出ようとする方を強制的に制止したり、施錠・隔離をなどの抑制行動はストレスや帰宅欲求を増加させるだけでなく、安全面でもリスクがあります。
その場しのぎや曖昧にごまかす
「あとで帰れます。」「家族に聞いておきます。」のような適当な対応や誤魔化しは、根本解決にはならず不信感や不安を強めてしまいます。
ただ、わかっていても忙しい現場ではどうしてもしてしまいます。だからこそ、「帰りたい。」と仰った際の対応方法を施設で決めておくと良いです。一人でいると帰宅願望が強くなる方がいます。その場合は、他の利用者と談笑できる環境をつくりましょう。そのためにも、3.人間関係を変えないで記載したなじみの関係を作るは大切なことです。
嘘をつく
明らかに事実と違うことを言い続けると、利用者本人の不安が強くなり、信頼関係の損失を招く場合があります。
わたしのバイブル!!「介護とは?」がわかる本!!認知症ケアの軸になりました!!▼
 『新しい介護 ―介護職の新しい教科書―』を読んで変わった考え方
『新しい介護 ―介護職の新しい教科書―』を読んで変わった考え方
まとめ

居心地をつくるために必要な「生活習慣」「個性的空間づくり」「人間関係」「三大介護」「役割づくり」の5つの取り組みを実例とともに紹介しました。
認知症ケアは、利用者一人ひとり正解が異なります。ただ、人間なので誰もが同じような感情をもっています。居場所が悪ければ認知症の方でもそうでない方でも、その場から離れようとします。
個別でのケアは必要ですが、どの利用者にも共通して役立つケアも必要です。認知症ケアが苦手な人でも環境作りはできます。
帰宅願望がある方に、明日からぜひ取り組んでみてください。
【実践シリーズ】お看取りの方が復活!施設を巻き込むために介護リーダーが取り組んだこととは?▼
介護リーダーの悩みはコレを読めば8割解決できる!?▼
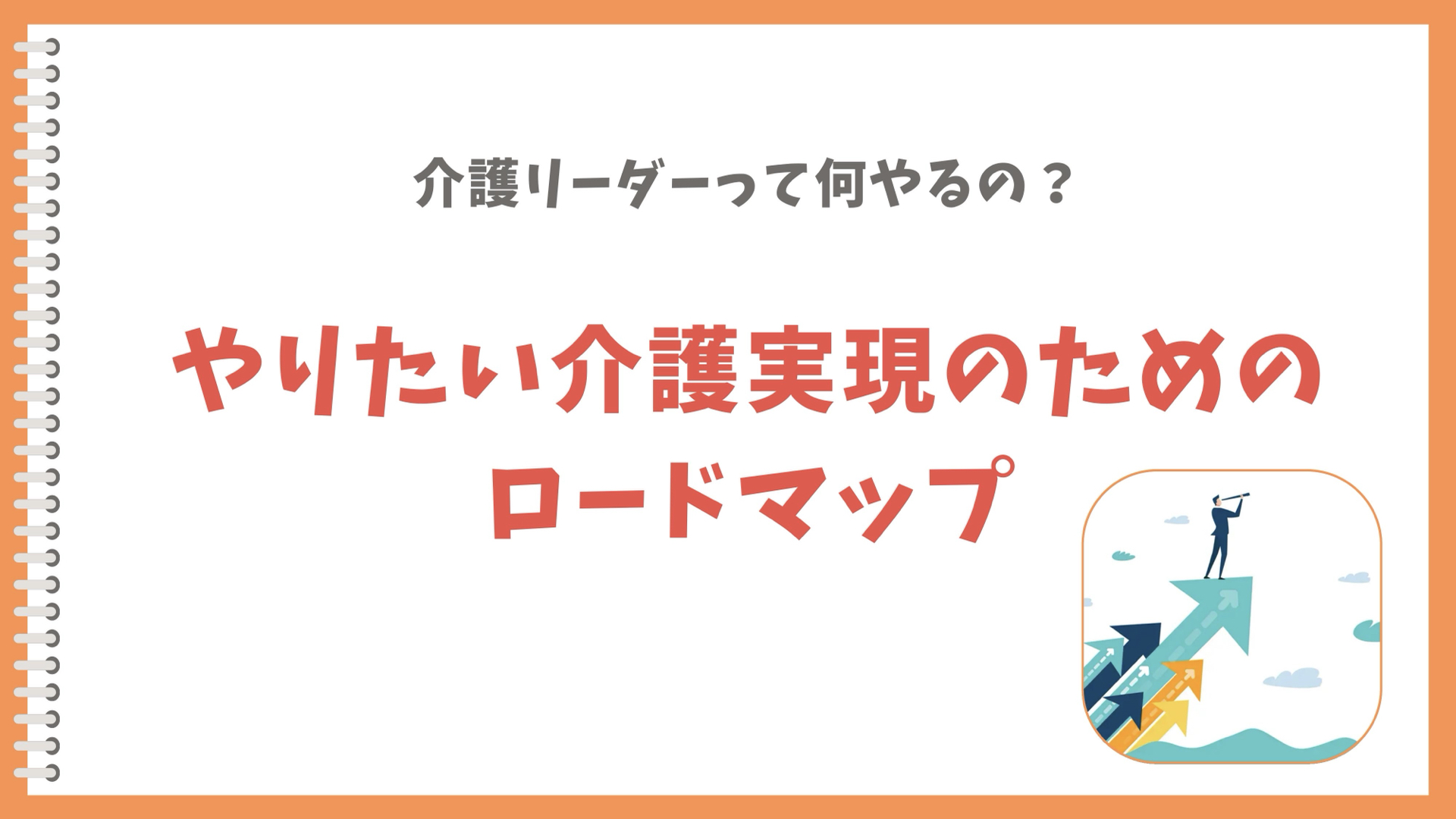 【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
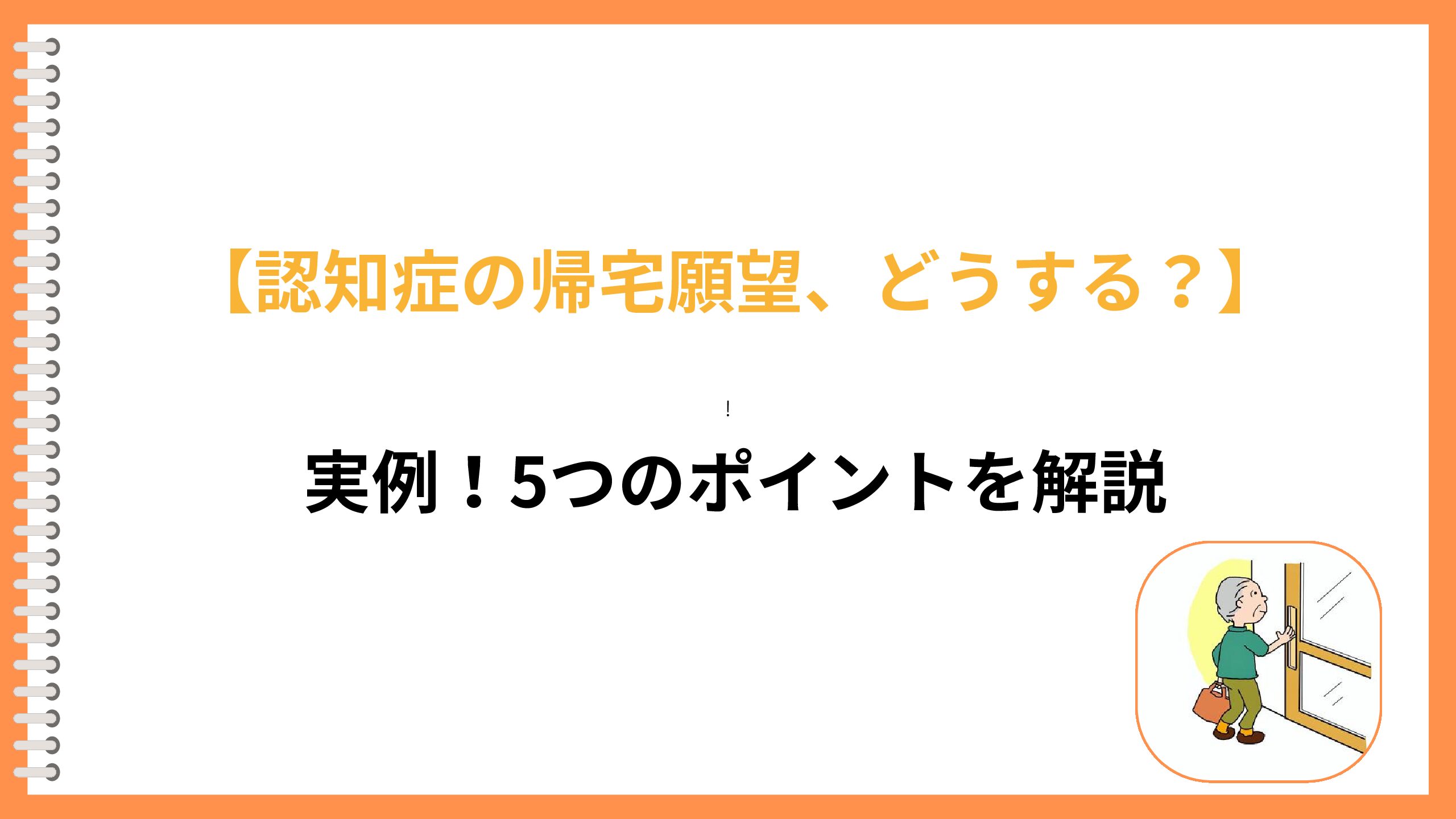
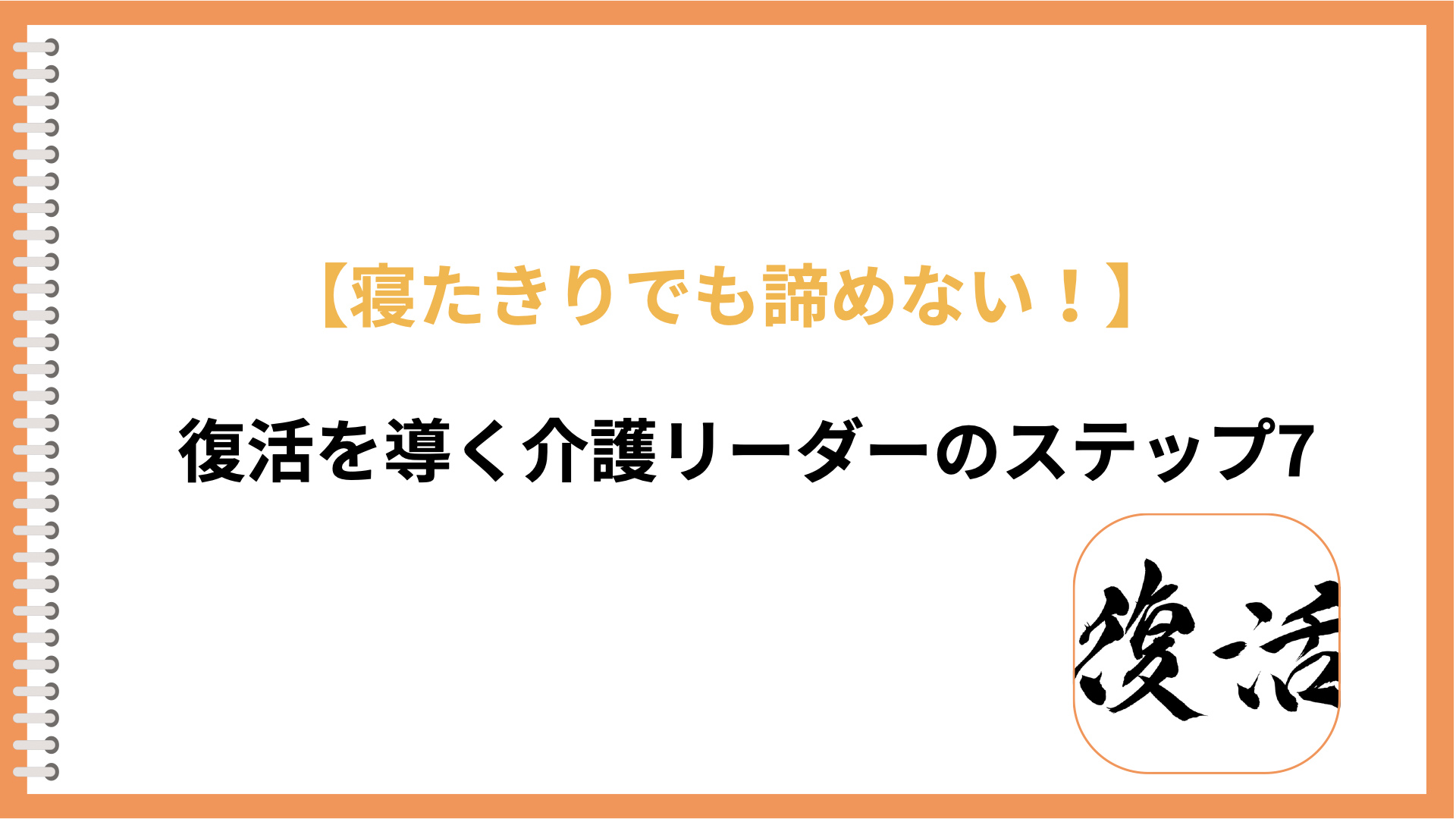

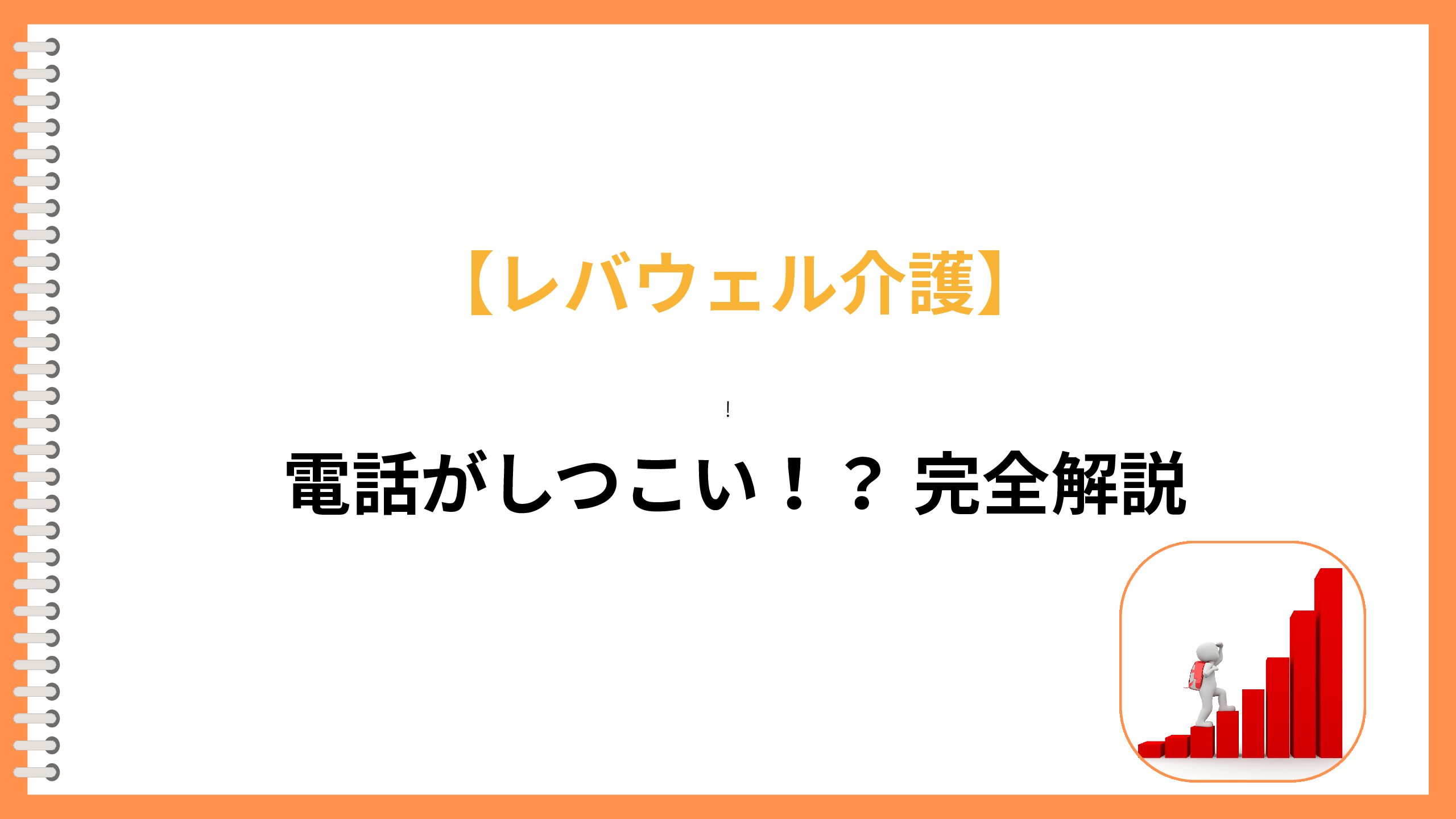
コメント