はじめに|「仕組みがないから理想の介護ができない」と悩んでいませんか?

「利用者のために介護しているはずなのに、最近は業務に追われるばかり……」
「スタッフの意識がバラバラで、理念がうまく伝わらない……」
こんな風に感じたことはありませんか?
現場でリーダーや管理者として働いていると、「やりたい介護」と「現実」とのギャップに悩むことが少なくありません。
その原因の一つが、「理念や価値観が仕組みとして整っていないこと」なのです。
本記事では、介護施設で“利用者主体のケア”を実現するための「老人ホームの仕組み作り方」について、私自身の実践経験をもとに5つの視点で解説します。
プロフィール|現場リーダー・管理者として“仕組みづくり”を実践してきた私の経験
介護歴と職歴
- 介護歴:10年
- 資格:介護福祉士
- 経歴:
・介護付き有料老人ホーム(6年/統括リーダー経験)
・住宅型有料老人ホーム(3年/サービス提供責任者兼マネジメント)
・現在:看護小規模多機能型施設の主任リーダー(2025年〜)
「やりたい介護」と「やりたくない介護」
- やりたい介護:
“ふつうの生活”に近づけ、なじみの関係を築くこと - やりたくない介護:
スタッフ主体で、効率だけを優先してしまうケア
現場とマネジメントの両方を経験して感じたのは、「どれだけ理念を語っても、仕組みがなければ現場は変わらない」という事実でした。
問題提起
私はこれまで10以上の介護施設を見てきましたが、どこでも同じような光景に直面しました。
本来、人生の最終章を穏やかに、主体的に生きてもらうはずの施設で、利用者がただ“受け身”になってしまっている──。
- 自分で食事ができるのに、介助を優先
- トイレに行けるのに、オムツ対応
- 機械浴で流れ作業的な入浴
- 「認知症だから」と自由を奪うケア
私は「このままでいいのか?」と自問し続け、やりたい介護・やりたくない介護を明確に言語化しました。
「意欲」を引き出す4つのケア
1. 生きがいのケア|やりたいことを叶える
例:長年の夢だった旅行にいく
夢や希望を持ち続けることは、年齢に関係なく人を元気にします。
2. 自立支援のケア|できることを自分で
例:受け身になる機械浴ではなく、自主的に動く個浴に入る
「できる力」を奪わないケアが、自信と尊厳を支えます。
3. かかわりのケア|役割を持つことの価値
例:整備士だった方がホームの車を洗車する
「誰かの役に立つ」ことで、自己肯定感が生まれます。
4. 社会参加のケア|地域とのつながりをつくる
例:近隣公園のごみ拾いなど、地域貢献活動
地域の一員としての役割が、「生きている実感」を支えます。
介護観を現場に浸透させるための老人ホームの仕組みの作り方【5選】
このようなケアを現場で実現するには、スタッフ全員が同じ介護観を共有する必要があります。
以下は、私が実践してきた「老人ホームの仕組みの作り方」の具体例です。
① 人間関係の構築|信頼ベースのチームづくり
ケアの質は「人間関係の質」に比例します。
まずは自分とスタッフが信頼できる関係を築くことが土台です。
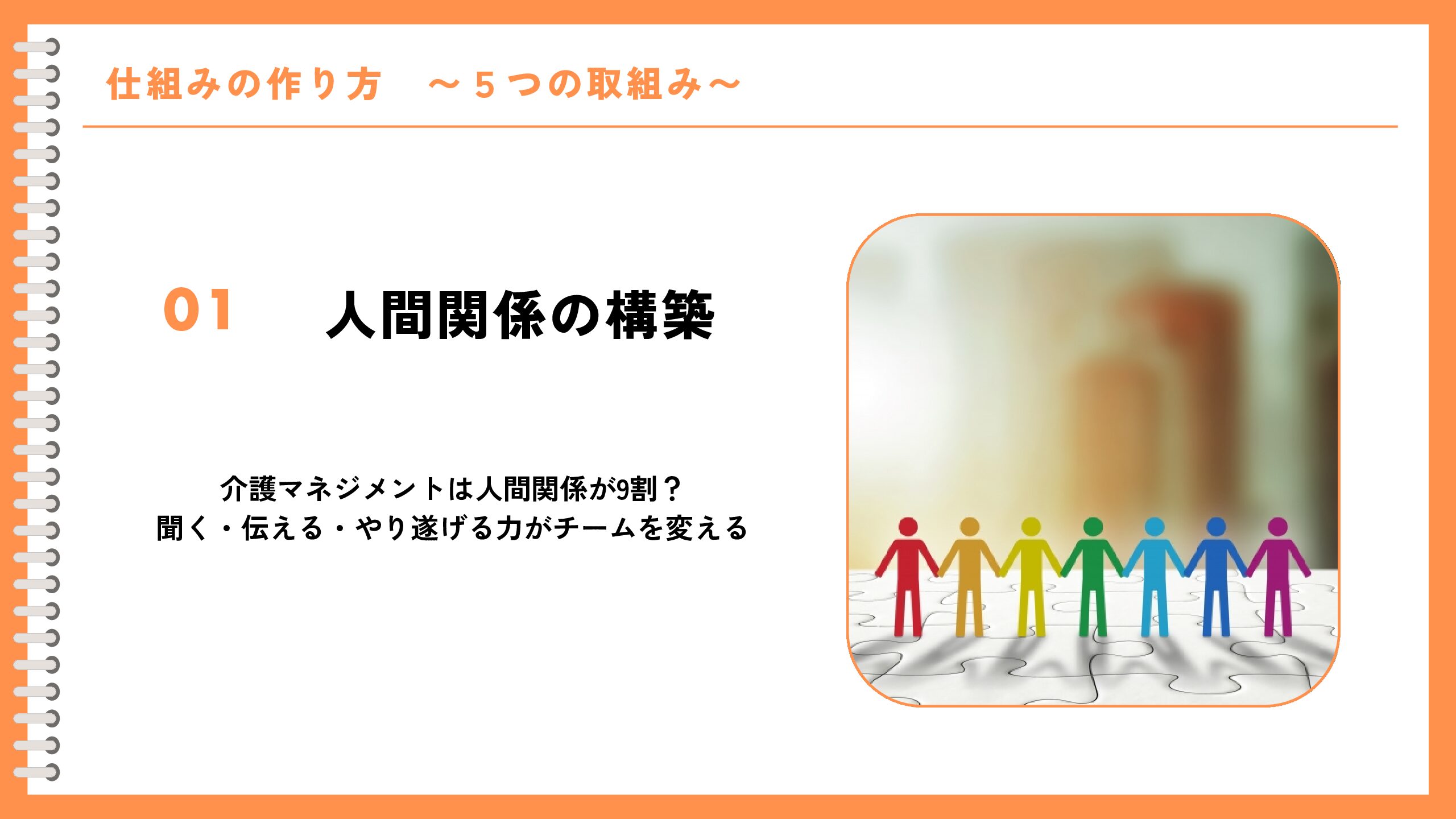 介護現場のチームを変えるコミュニケーション改善のヒント
介護現場のチームを変えるコミュニケーション改善のヒント
② 会話の場をつくる|価値観をすり合わせる対話の仕組み
忙しい中でも、定期的に「考えを話す」時間を設けます。
ミーティングやカンファレンスでは、「正解」ではなく「共有」を大切にします。
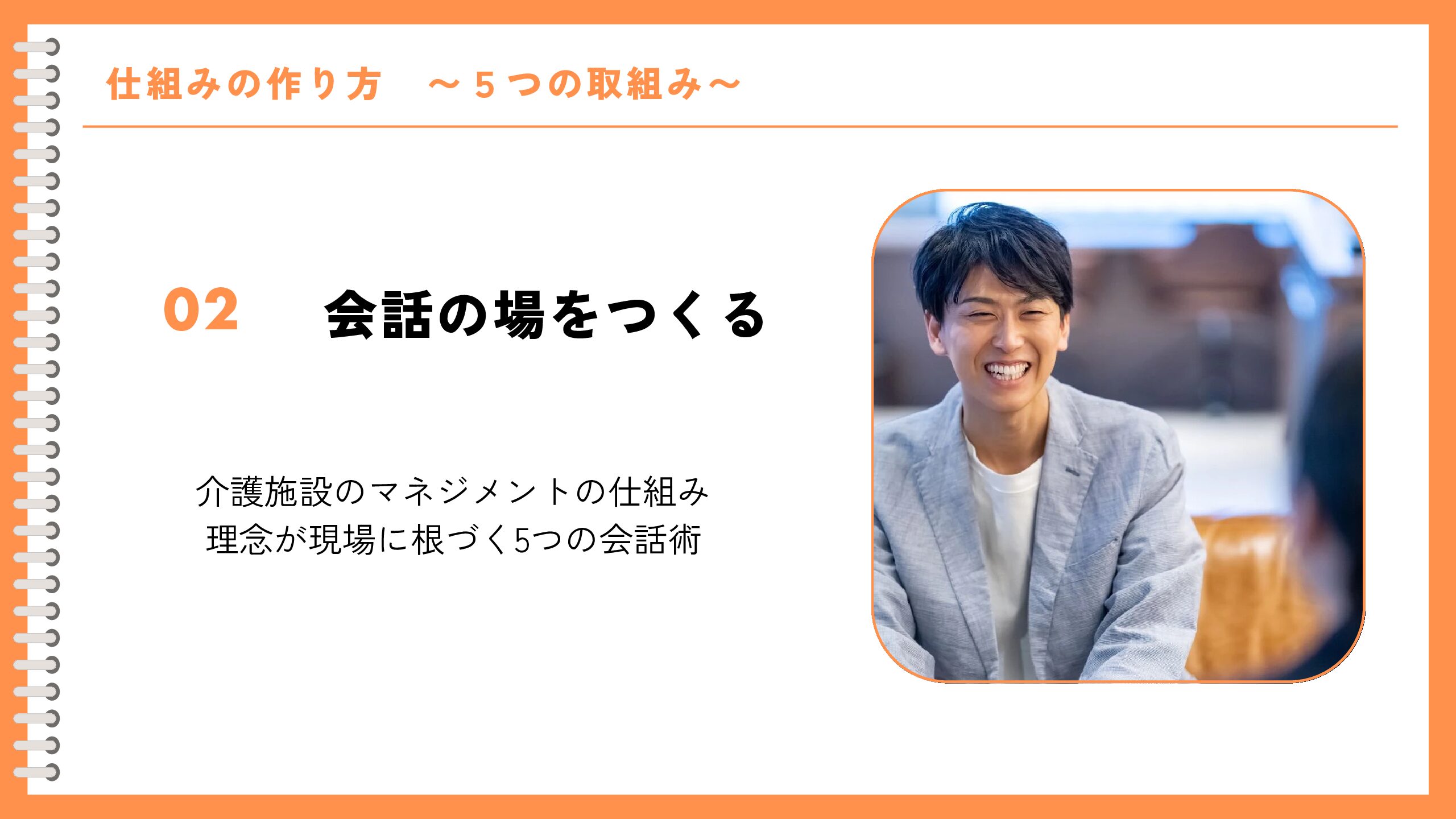 会話する場をつくる
会話する場をつくる
③ 人財の選定|理念に共感する人を採用する
技術よりも「どんな介護をしたいか」が合うかを重視。
必ず“介護観”を確認しています。
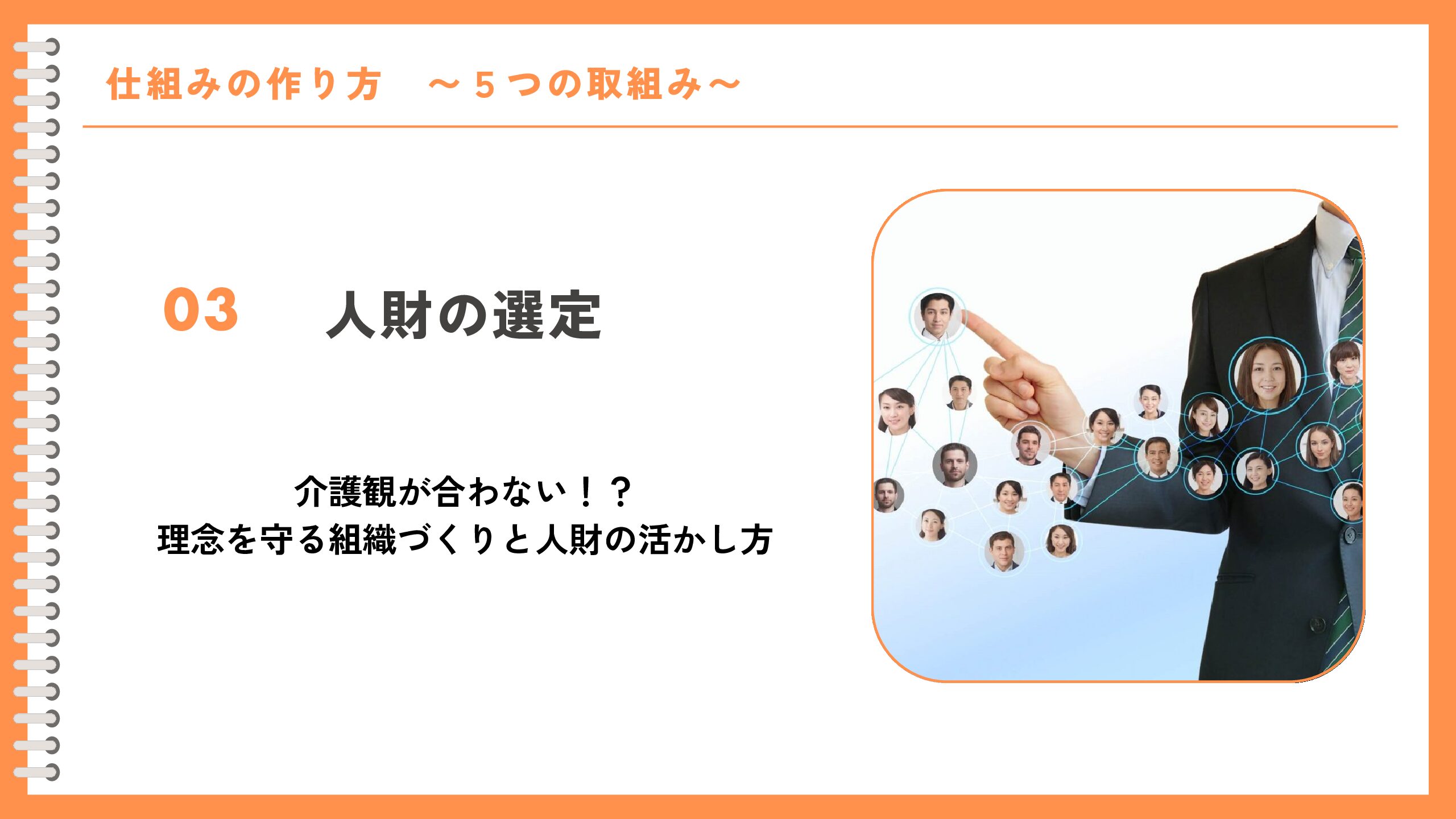 介護観が合わない。対処方法は?
介護観が合わない。対処方法は?
④ リーダーの配置|理念を言葉にし、現場に落とせる人財を
現場のキーパーソンには、介護観を発信し続けられるリーダーを配置。
“行動に移せる”人の存在が、スタッフの行動に大きな影響を与えます。
⑤ 委員会の活用|仕組み化によって理念を拡張する
介護観を体現する委員会(プロジェクト)を立ち上げ、全体に波及。
例:認知症委員会、介護技術委員会等
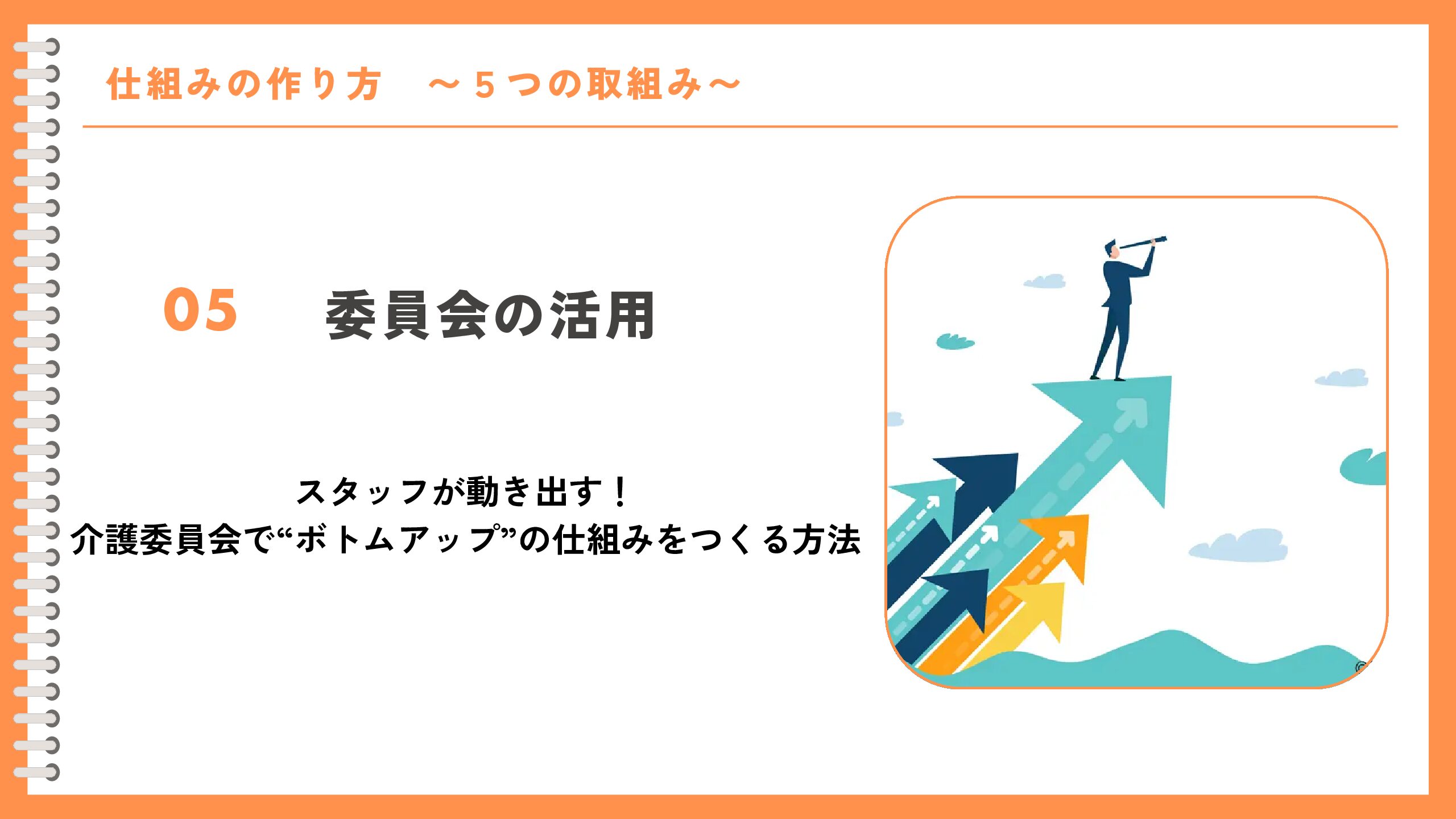 スタッフが動き出す!介護委員会で“ボトムアップ”の仕組みをつくる方法
スタッフが動き出す!介護委員会で“ボトムアップ”の仕組みをつくる方法
なぜこの仕組みが機能するのか?|施設の“空気”を変えるための具体的工夫
スタッフ間にある“価値観のズレ”を可視化・共有し、対話を重ねることで、チームの方向性が揃っていきます。
ここで重要なのは、「教育する」ではなく「共に育つ」視点──つまり“共育”です。
また、理念を押しつけるのではなく、スタッフ自身が「なぜそのケアが大事なのか」を腹落ちできるような仕掛けをつくることで、自律的な変化が生まれました。
こんな悩みを抱えていませんか?|「現職では仕組みづくりに挑戦できない」あなたへ
ここまで読んでいただいたあなたは、きっと“やりたい介護”をあきらめたくない方だと思います。
けれど、現場によっては──
- 上司に理念が通じず、変化が起こせない
- 年功序列でリーダーや管理職になれない
- 新しい取り組みに理解が得られない
そんな環境に悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
実際に私の周りでも、「本当はもっと利用者のために動きたい。でも、今の職場では限界がある」と、転職という選択をした人が少なくありません。
転職はキャリアアップのチャンス|「仕組みをつくる側」へステップアップ
もしあなたが、
- 「もっとマネジメントに関わりたい」
- 「理念を形にできる施設で働きたい」
- 「これまでの経験を活かして、仕組みから変えたい」
と考えているなら、転職で一歩踏み出すことが、理想の介護を実現する近道になるかもしれません。
しかも最近では、リーダー経験者や介護福祉士資格を持つ人材を求めている施設が多く、給与がアップするケースも増えています。
 レバウェル介護で年収20万円アップできた話
レバウェル介護で年収20万円アップできた話
まとめ|老人ホームの仕組みの作り方は、理想の介護を現実に変える第一歩
介護施設の現場を本当に変えたいなら、理念だけでは不十分。
それを支える“仕組み”があってはじめて、スタッフの行動は変わります。
今回ご紹介した「5つの仕組み」は、すぐに大きな成果が出るものではありません。
しかし、着実に積み重ねることで、利用者の表情、スタッフの声、チームの雰囲気が少しずつ変わっていくのを実感できるはずです。
「やりたい介護」をあきらめないあなたへ──
まずは、現場の“空気”をつくる仕組みから見直してみませんか?
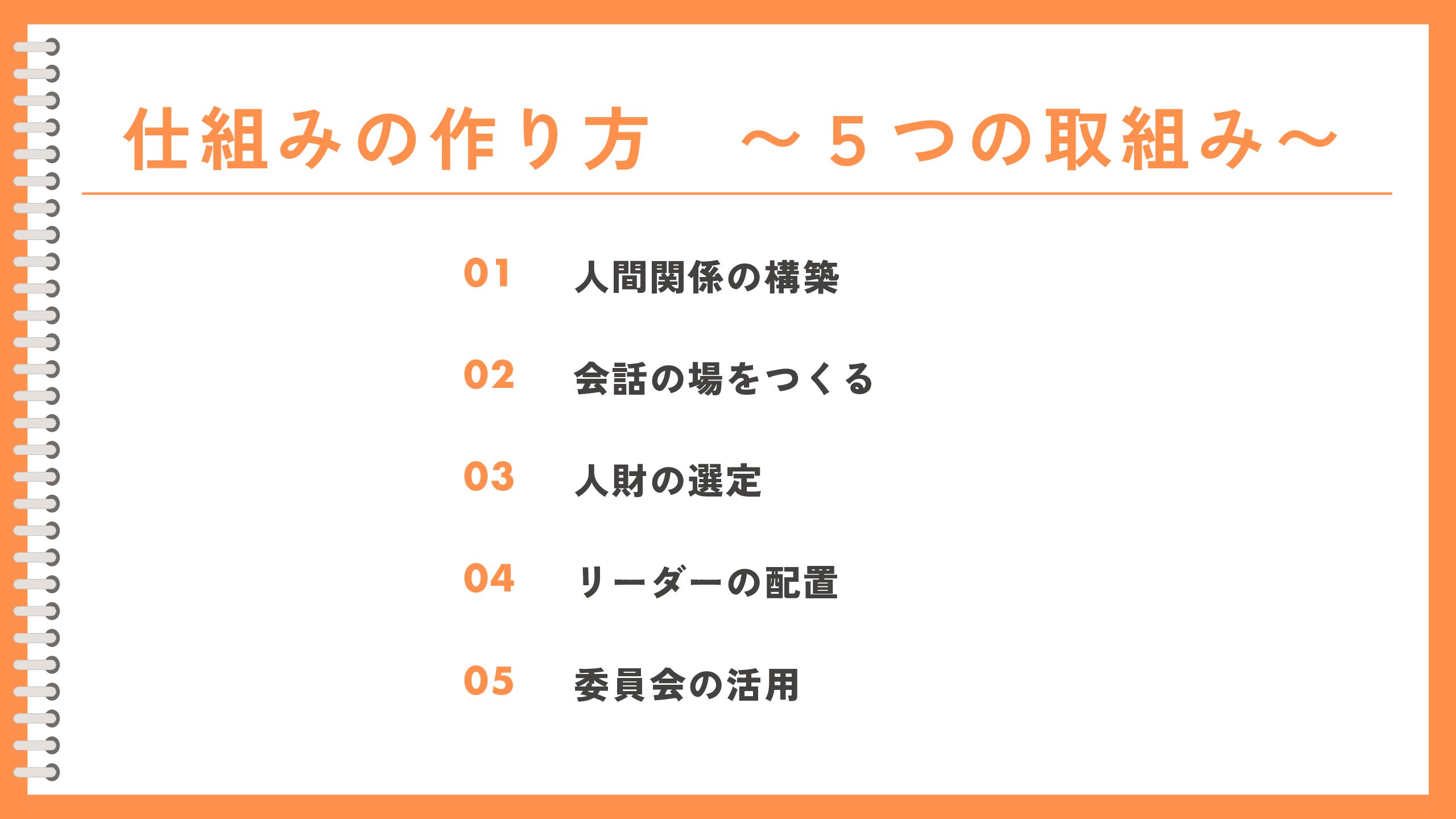
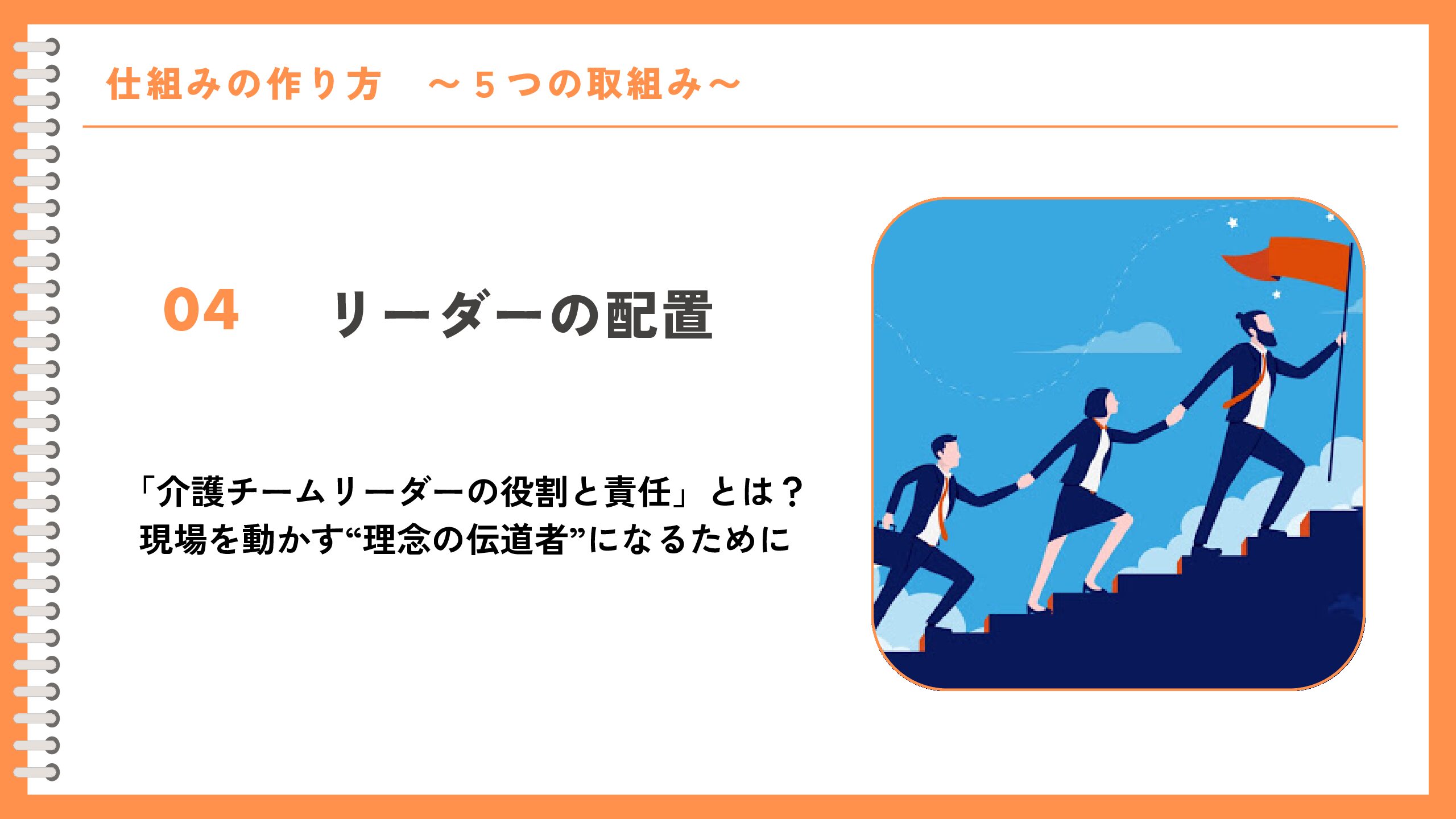
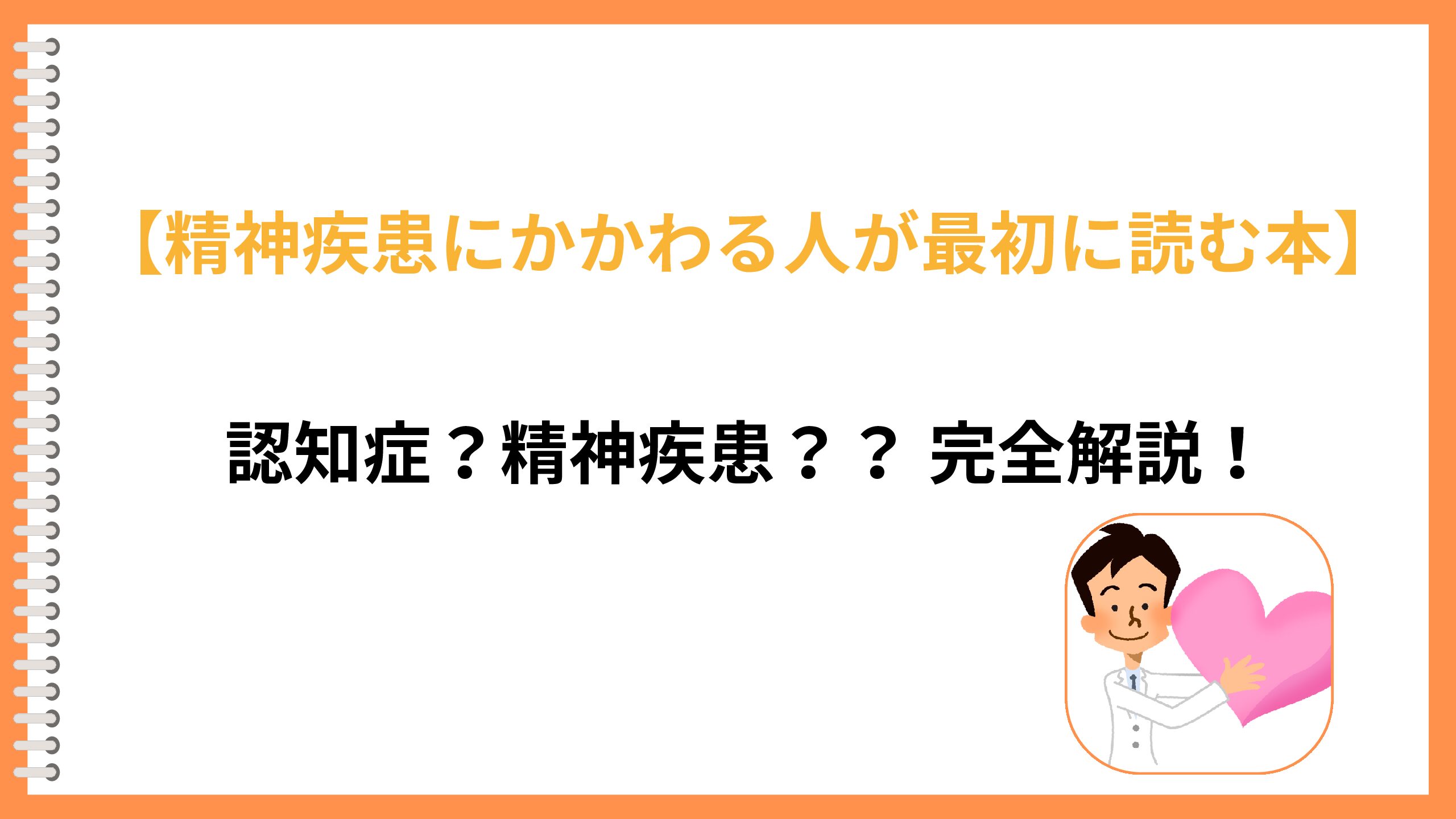
コメント