介護業界では、若くして介護リーダーになるケースが多々あります。
結果として、歳上の部下ができます。経験や知識が不足しているため、指示されることもあります。
「介護リーダーとして指導・指摘をしないといけないが、うまくできない。」
「言われたことしかできていない。」
なんてことに悩んでいませんか?
この問題は、ルールを作ることによって解決します!
なぜルールなのか?
介護施設のみならず、世の中ルールによって成り立っています。
たとえば、信号が赤になれば止まります。無視をすれば、処罰を受けます。
介護施設でも同じです。決まったルールを守れない場合、指摘を受けたり場合によっては就業規則によって処分が決まります。
ルールがない(または曖昧)状態で、指摘をしても「あなたが勝手に言っているだけでしょ。」で終わります。スタッフ間では「またなんか言ってるよ。まあ、言わせておけばいいか。」と相手にされません。しかし、ルールを作ったことにより、あなたの意見ではなく施設の取り決めに変わります。
わたしは、介護リーダーとして異動した際、社員12名中11名は歳上で「よそ者扱い」されました。提案など何も聞いてくれませんでした。
「だれがお前の言う事を聞くか!」という言わんばかりの言動をされてしまいました。
そこでわたしが行ったことは、自分のやりたい介護・やりたくない介護をスタッフ全員に伝え、共感するスタッフを仲間にし、理想の施設を実現するために必要なルールを一緒に作っていきました。
冒頭で、施設のルールを作れば歳上のスタッフにも指導・指摘ができると書きました。これは事実ですが、実際にはそのためにいくつかのステップを踏む必要があります。
この記事では、ルールがないことのデメリットとルールを作り定着するまでの流れについて説明します。
最後まで読んでいただけると、歳上の部下に対して臆することなく指摘できるようになります。また、その先で自分がやりたい介護の実現に近づけます。
ルールがないことによるデメリット

【1】ケアの質がバラつく
▶ 事例
・職員ごとにやり方が違う
→「Aさんはオムツをこう当てる」「Bさんは別の方法」など統一されず、利用者が混乱。
・食事介助の姿勢やペースも職員によって違い、誤嚥リスクが上がる。
・記録の書き方やタイミングが人によって違い、情報が抜ける。
▶ 結果
・ケアミス・インシデントが増える
・利用者・家族からの苦情につながる
【2】人間関係・チームワークの悪化
▶ 事例
・「誰のやり方が正しいの?」と現場が混乱
・先輩職員と新人の間で“ローカルルール”が衝突
・「あの人のやり方が間違ってる」と陰口・対立が起こる
▶ 結果
・チームがバラバラになり、情報共有が滞る
・指導がしづらくなる(ルールがないため注意の根拠がない)
【3】責任の所在が不明確になる
▶ 事例
・トラブルが起きたとき「誰の判断だったのか」が曖昧
・手順書がないため「言った・言わない」で揉める
・リーダーが責任を問われるリスクが増える
▶ 結果
・組織全体で「責任逃れ」の風潮が生まれる
・リーダーが精神的に疲弊する
【4】新人・中途職員が育たない
▶ 事例
・ルールが無いから教える内容が人によって違う
・「先輩によって言うことが違う」と新人が混乱
・中途入職者が馴染めず早期退職
▶ 結果
・教育コストが増大
・定着率の低下
【5】事故・クレームのリスク増大
▶ 事例
・医療行為に関わる判断(軟膏・服薬)で個人判断が入る
・事故後の対応ルールがないため、報告漏れ・隠蔽と見なされる
・家族対応が統一されず、「言うことが職員ごとに違う」と不信感を招く
まとめ:ルールがない施設で起こること
ケアの質が落ち、チームが乱れ、責任が曖昧になる。
結果として、「指導がしづらく、人が育たない」という悪循環が起こる。
ルール作りの流れ
STEP1 軸を決める
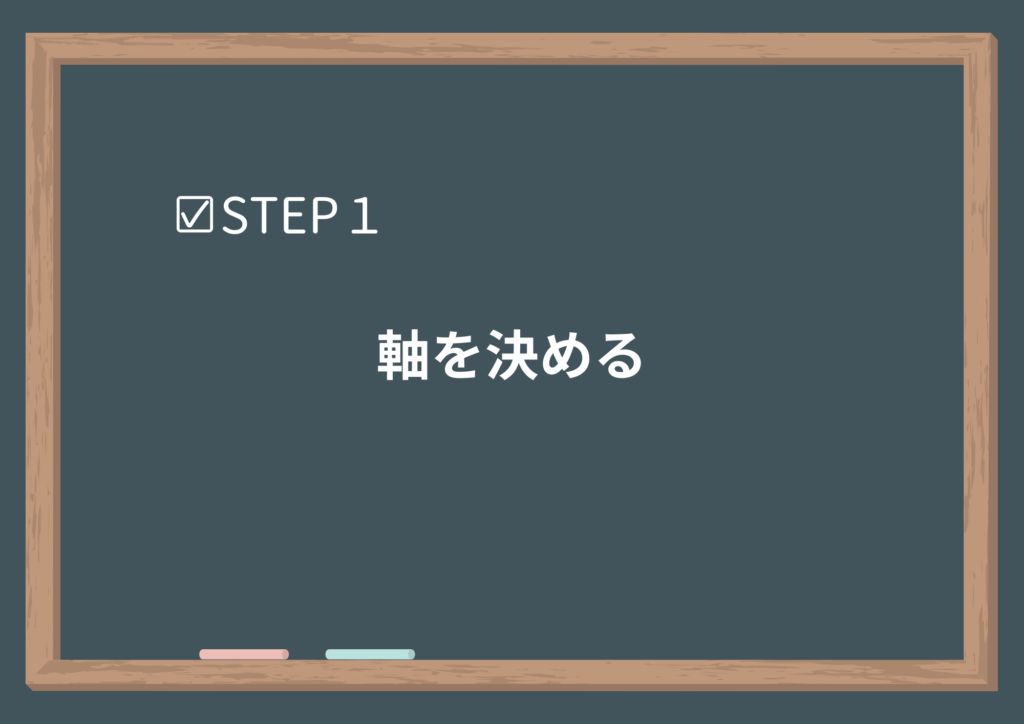
ルール作りの土台となる判断基準(軸)を最初に決めることで、スタッフの意見に左右されずに一貫した判断ができます。
ルールを作るとき大切なことは軸(判断基準)を決めることです。
「誰のためにルールを作るのか」
わたしは、利用者のためのルールを作ることを軸にしていました。
「このルールがうまくいった時、利用者に還元されるのか?」いつも自問自答しています。
なぜ軸が必要なのか?
事例をもとに説明します。
わたしの勤めていた施設での出来事です。
スタッフより「夕食の提供時間を19時までにしたい」と声が上がりました。理由は夜勤者の負荷を減らすためです。
食事提供時間は18時から20時までで利用者はいつ食事をしても良い。というルールでした。20時以降も召し上がっている利用者がいます。その方の食器を夜勤スタッフが手洗いする必要があるので手間が増えるという話でした。※20時前であれば厨房スタッフが行うことになっています。
わたしはその提案に「NO」と言いました。なぜなら利用者にとってマイナスになると考えたからです。生活リズムを大切にし遅めに夕食をとる方がいるのを知っていたからです。
ただこれだと、夜勤者の問題は解決しません。結果、20時以降の食器は手つかずで置いておき朝厨房スタッフが片付けてくれることになりました。利用者にとってマイナスになることなく夜勤者の負担も軽減することができました。もちろん厨房スタッフとも話し合って決めたことなので納得した形で受け入れてもらっています。
ここで、軸がなければ、スタッフの意見をそのままのみ「たしかにな。夜勤は忙しいから負荷を減らすために提供時間を変更するか。」と結論付けていたでしょう。
STEP2 仲間を作る
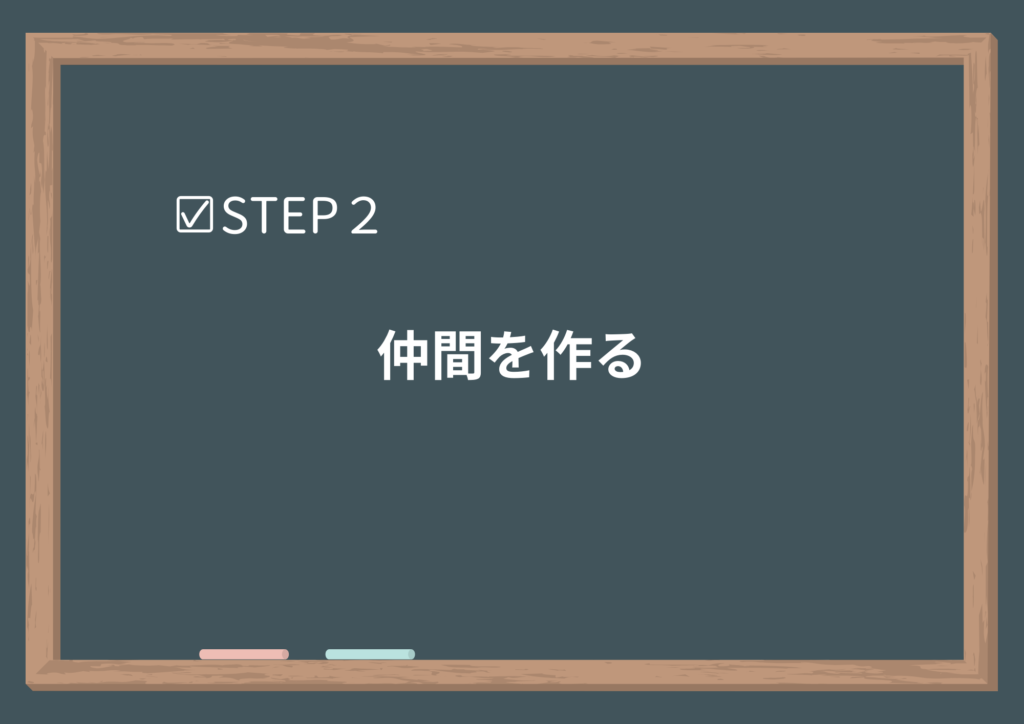
ルールを現場に定着させるには、同じ介護観を持つ仲間と協力することが不可欠です。
ルールを作るためには「仲間」が必要です。
一人でもルールを作ることはできます。ただ、施設で定着させなければ意味がありません。定着させるには指摘や指導をしないといけません。一人では時間と労力がとてもかかります。仲間がいれば、倍以上の時間短縮と半分の労力で済みます。ただ、仲間作りは時間がかかります。自分自身の目で「本当の仲間か」を判断する必要があるためです。
仲間とは自分と似た介護観を持っているスタッフです。
たとえば、わたしは「利用者がトイレの便座に座れるのであれば、トイレに連れて行く。一人で食事ができるのであればむやみに手伝うことはしないなど、当たり前(ふつう)の生活をしてもらう。そこを支えるのが介護」という考えを持っています。もちろん、麻痺の方に自分で食べろと言っているわけではありません。「当たり前(ふつう)の生活」に近づけるためにどのような介護をすればいいかを考えることが大切ということです。
ただ、これを説明すると「スタッフがいないのだからトイレで排泄ができてもベッド上でおむつ交換をします。」と言うスタッフがいます。
この時点で「自分と違う介護観を持っているのだな。」と判断します。別に悪いことではありません。介護に対する考えは人それぞれなので。
※わたしの場合、似た介護観を持っているスタッフは「人員不足でも、どうやったら実現するのか?」を考えています。その時点で、仲間認定です!笑
では、どうやってスタッフの介護観を確認していったのか?
結論、たくさん会話をしました!!
具体的に5つの場を活用しました。
1.現場(フロア)
2.申し送り
3.会議(ミーティング)
4.面談
5.研修
会話をする中で具体的に何をどう工夫したのか?
それ以前に自分の介護観がイマイチわかっていない。
両方を解決する記事▼
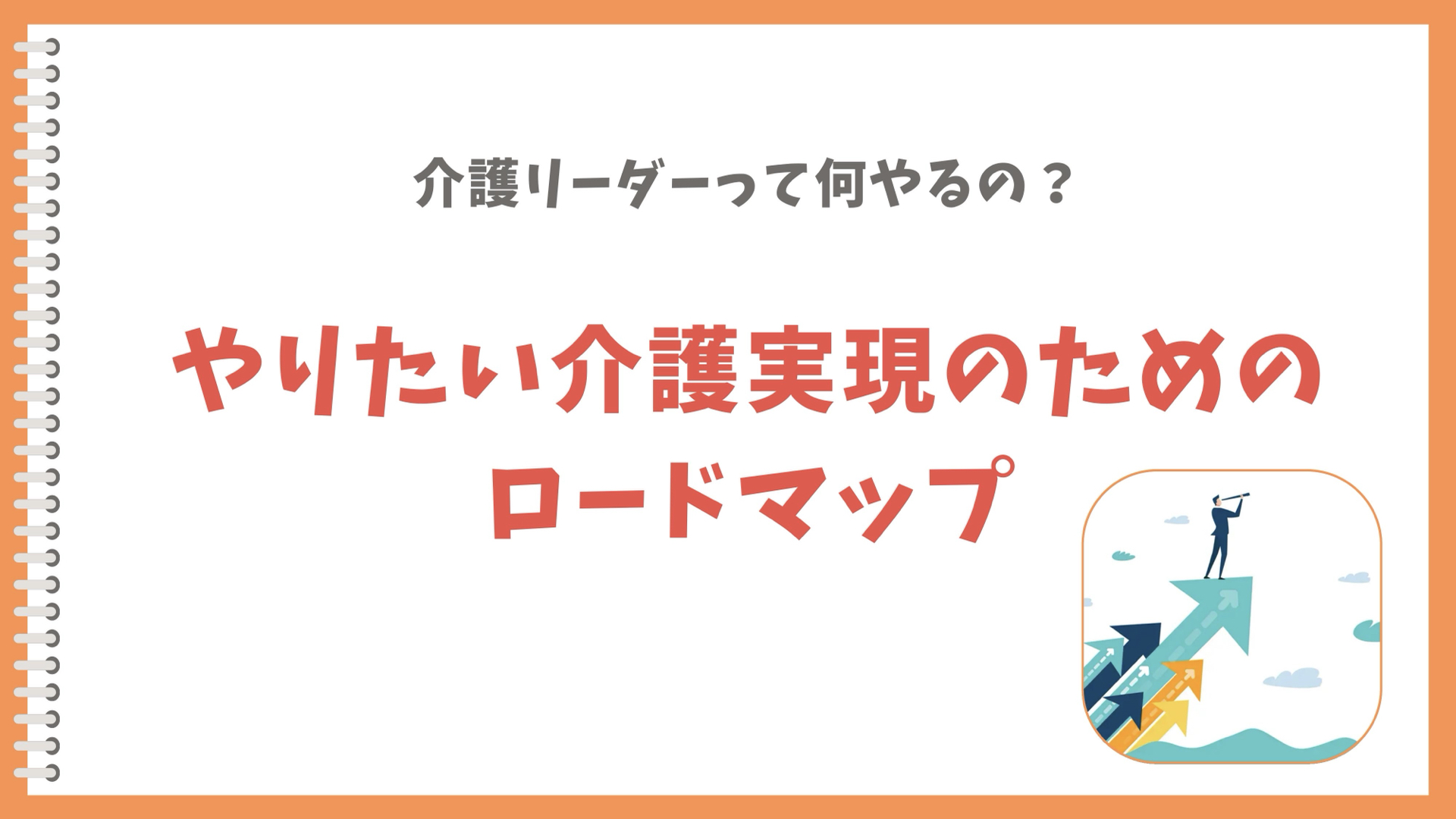 【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
仲間作り(人材の選定)は、結果1年かかりました。社員12名中、似た介護観をもったスタッフは3名でした。
この3名+わたしでルールを作っていきました。
STEP3 ルールを導入する
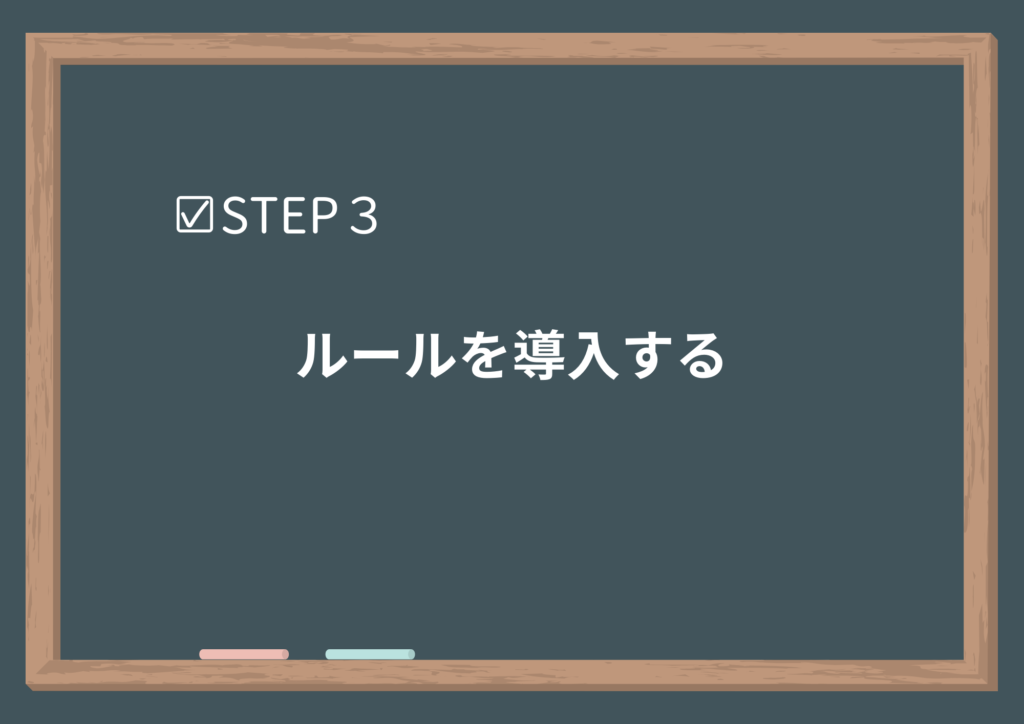
作ったルールを全員に周知し、問題・原因・対策の順で説明することで、理解と納得を得やすくなります。
ルールの原案を仲間と一緒に作ります。
ルールを作り終えると、まず周知・初回説明が必要になります。
「こんなルールが開始しますよー」ってやつです。
周知・初回説明をどのように行うのかはその施設によって変わってきます。
わたしの場合は、全体会議にて全スタッフにルールの説明をおこないました。参加できなかったスタッフには後日、直接口頭で説明します。
大切なことは、まず一度全員の耳に入れておくということです。「聞いてなかった。」「説明を受けていないからやらなくてもいい。」と思われないようにです。
説明方法は、
問題➜原因➜対策
の順で説明します。
例えば、
「人間違い誤薬が発生しました。利用者の命に関わります。再発防止が必須です。原因は、服薬担当者が〇〇様の薬と思い込んでいたことです。個人的な原因もありますが、施設に服薬手順マニュアルがなく独自のやり方を行っていたという意味で全体の問題でもあると考えています。対策は、マニュアルを作成し徹底することです。」とマニュアル中身を説明。
最後に参加の意見や質問を求めます。
良い意見が出た場合は、中身をブラッシュアップします。
ルールができたら目に付く場所に貼付しましょう。
ルールが開始されると最初は上手いこといきません。
内容を理解していないスタッフや忘れてしまうスタッフがいるためです。
ここでやることは、口頭での是正や指摘をする必要があります。仲間と一緒に行います。
『あーだ、こーだ』と言ってくるスタッフ言ってくるスタッフがいると思いますが、人間違い誤薬を起こさないためと説明しルールに従ってもらいます。
正直、ここが最も労力を要する部分です。さまざまな意見が出ますが、アドバイスであればよいのですが、やらない理由ばかり言うスタッフへの対応は大変です。ただ、全体の2割ぐらいかと思います。残りの8割はなんだかんだルールの必要性を理解し従ってくれます。
また、今後も施設に必要なルールを作っていくため従えない2割のスタッフは異動や退職願を出す傾向があります。
わたしはそれで良いと思っています。介護リーダーをやる以上、自分のやりたい介護ややりたくない介護を実現するには全スタッフの理解を得れないことは理解しておきましょう。
STEP4 ルールを浸透させる
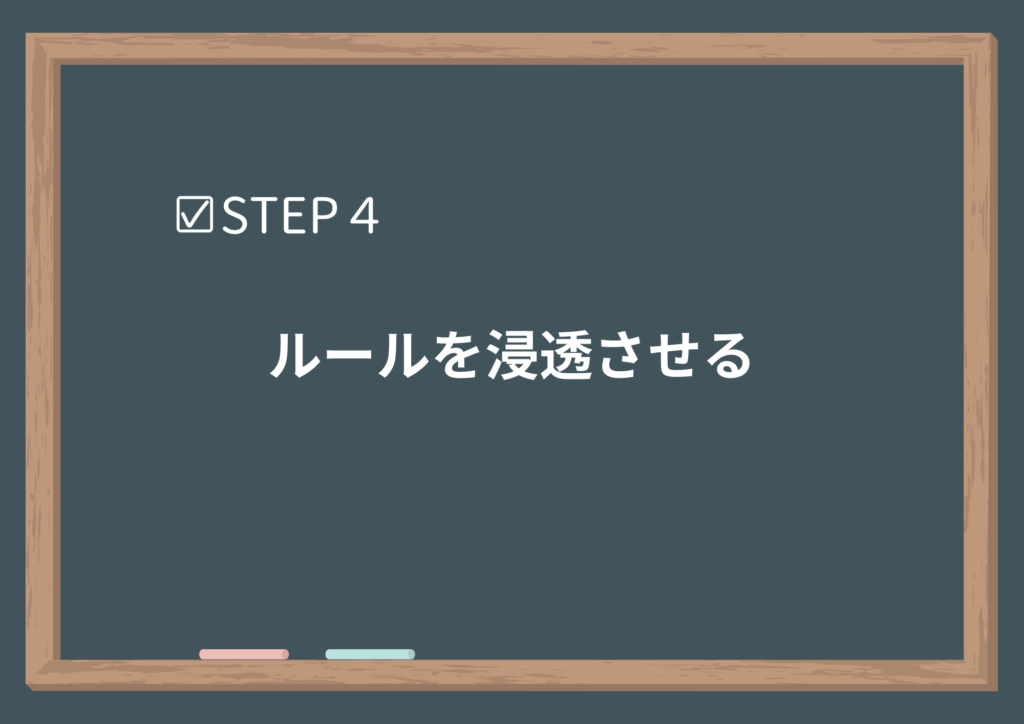
スタッフが現場で意識して行動に移す段階では、ブラッシュアップや口頭指導を繰り返し行い、ルールの理解を深めます。
導入が終わったら、浸透です。
浸透とは、スタッフが現場で意識し始め、行動に表れている状態のことです。
上記の例だと、全員ができているわけではないけど服薬手順マニュアル通りに動こうとしている段階です。
ミスも生まれる段階なので、発見したら是正をしましょう。
ここで大切なことは、ルール通りに行っていく中でイマイチうまくいっていない場合、ブラッシュアップをすることです。
「この手順不要だな」「もっと具体的にしたほうがいいな」などです。
できるだけ完璧に近い状態に持っていきます。
改善点が見つかれば、仲間と一緒に変更し、再度全スタッフに発信します。
その場合も、「聞いてなかった。」「説明を受けていないからやらなくてもいい。」と思われないように共有しましょう。
STEP5 ルールを定着させる
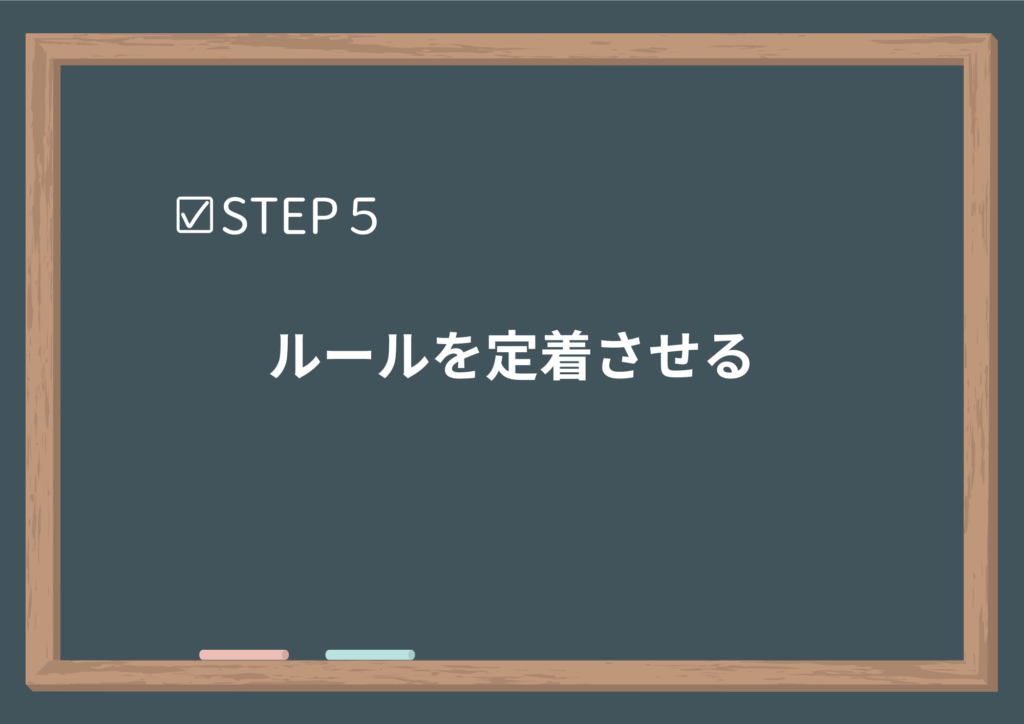
日常業務で自然に守られる状態を目指すことで、ケアの質向上やチームワーク改善、リーダーへの信頼が積み上がります。
最後に定着です。
定着とは、日常業務で自然に守られている、違反が少ない状態です。
ここまでくれば、ルールは施設に定着したと考えて良いでしょう。
逆にここまでしなければいけません。
ルールが定着すれば、上記で書いたデメリットと反対のことが起きます!
ケアの質が向上したり、人間関係が良好になったりします。
まとめ:ルール作りがあなたを強いリーダーにする
歳上スタッフに注意しづらい。この悩みの原因は、あなたの性格や経験ではありません。
現場に“指導の拠り所になるルール”がないこと。ただそれだけです。
ルールが整えば、指摘は無理せず自然にできるようになります。
ルールが現場で当たり前になると、
・指導しやすくなる
・スタッフが迷わなくなる
・利用者へのケアが安定する
・リーダーとしての信頼が積み重なる
といった、毎日の仕事が少しずつ軽くなる変化が起きてきます。
そして気づけば、あなたの“やりたい介護”へ向かう流れができています。
お局に悩まされている介護リーダーへ!その問題解決できるかも!?▼
介護リーダーの悩みはコレを読めば8割解決できる!?▼
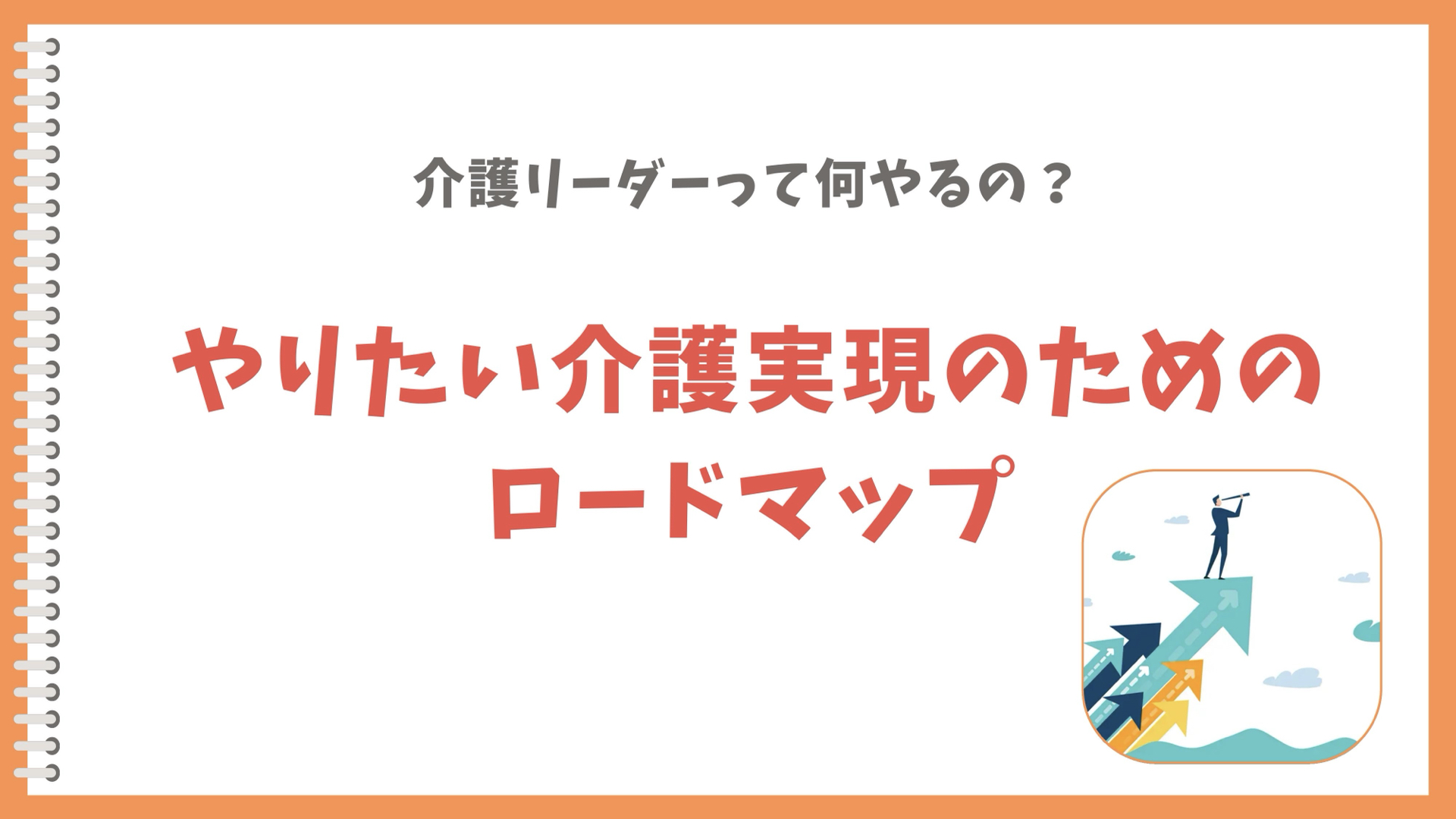 【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
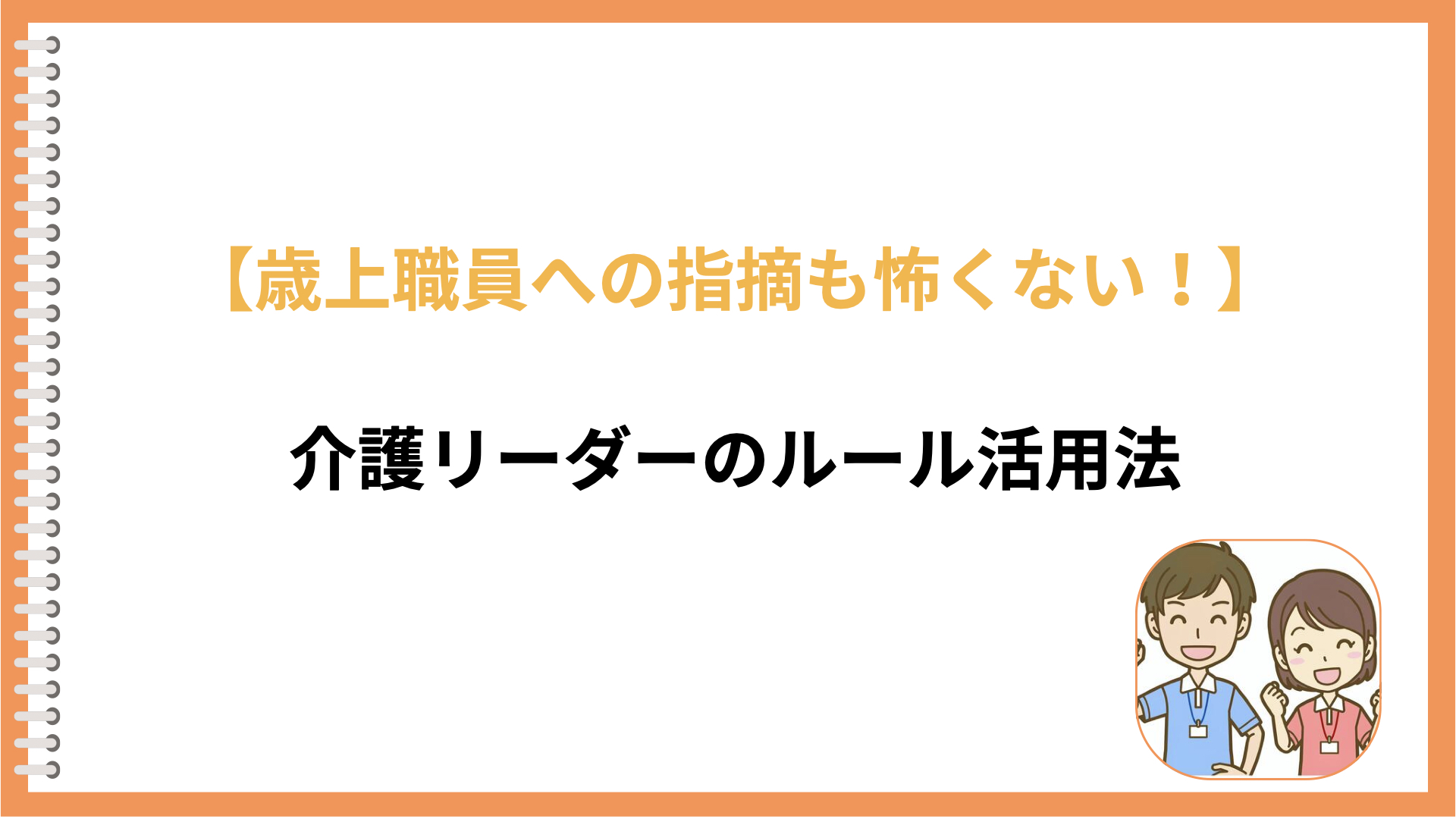
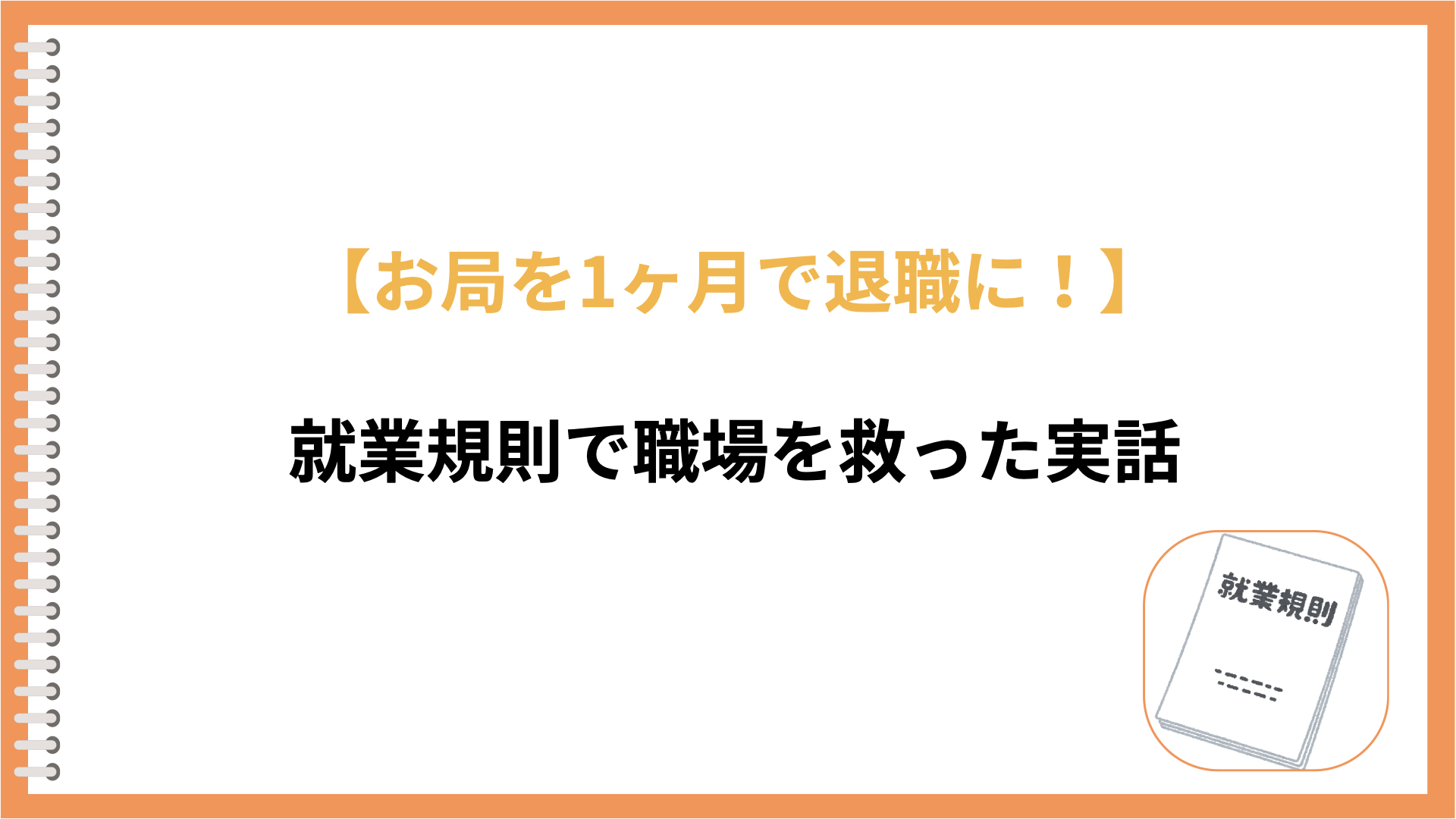


コメント