「お局の影響によって退職者が止まらない」「辞めてもらいたいのにできない」とお局問題に悩んでいませんか?
実は、“就業規則”を使えば解決できる可能性があります。
なぜなら、就業規則は労働基準法に基づいて制定される、会社と従業員双方が守るべき公式な労働ルールだからです。違反をすると罰則があります。お局の言動はそこに触れる可能性が高いのです。
わたしは介護リーダーをしている時、お局に悩まされました。お局に好かれないスタッフは辞めていく。介護が好きなスタッフも辞めてしまいました。2年間様々な手を打ちましたがうまくいかず。人事権がなかったので尚更時間がかかりました。ただ会社の就業規則を利用すると1ヶ月で退職が決まりました。それぐらい威力のあるものです。
この記事では、就業規則を活用しお局に退職してもらうまでの流れを実例でご説明します。
実践すると、悩まされてきたお局とおさらばできる可能性が高くなります。
STEP1 お局の特徴を知る
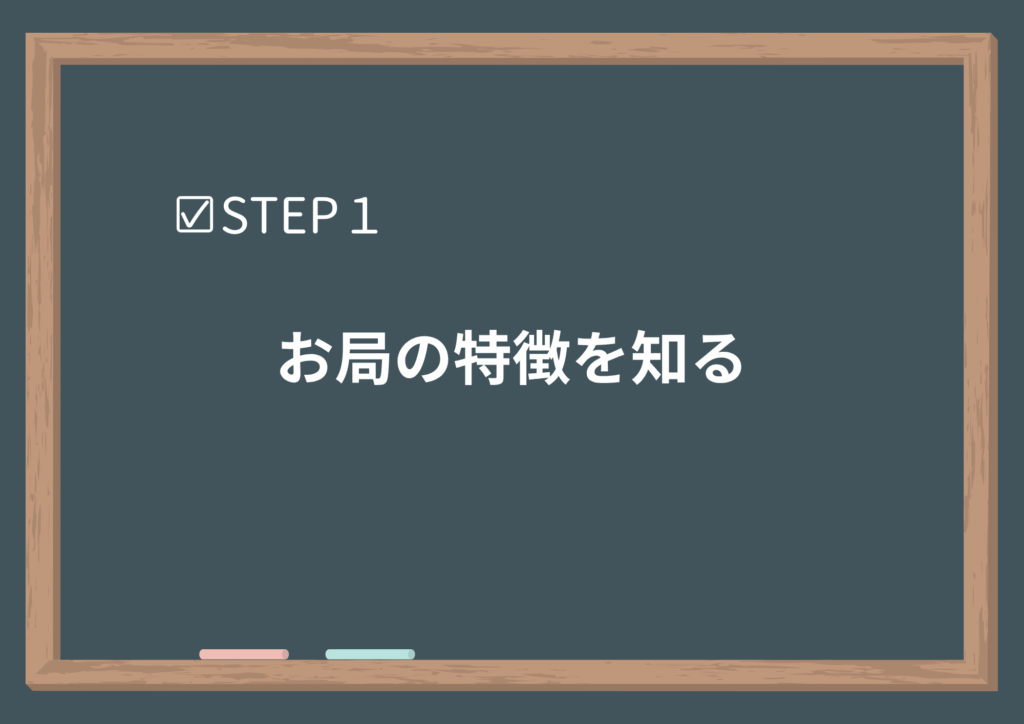
お局は施設長や介護リーダーなど施設内で影響力のある人物には本性を見せません。表の顔を見せ、いい人を振る舞います。なぜか??
① 自己保身(立場を守るため)
お局にとって「上の立場の人」は、自分の評価や立場を左右する存在です
もし悪い印象を与えれば、自分の影響力や居場所が脅かされる可能性があります。
だからこそ「いい人」「頼れるベテラン」を演じ、権力者に好印象を与えて自分を守ろうとします。
→ 「自分が不利にならないように」計算して行動している、という心理です。
② 二面性を使ってコントロールするため
お局は「相手によって態度を変える」ことで、周囲をコントロールしようとする傾向があります。
上には媚び、下には強く出ることで、上下関係の中で自分が優位に立てる構造を作るのです。
→ 「上には従うフリをして、下を支配する」という構図を作りやすくなります。
③ 承認欲求と支配欲のバランス
お局は「認められたい」という承認欲求が強いタイプが多いです。
施設長など“権威のある人”から褒められることで、自分の存在価値を確認します。
一方で、同僚や後輩など“安全な相手”にはそのストレスをぶつけやすくなります。
→ 「上からは褒められたい、下からは恐れられたい」という心理的バランスを保っている。
④ 長年の“処世術”が身についている
長く職場にいるうちに、「誰の前でどんな態度を取れば自分が得するか」を無意識に学んでいます。
結果的に、施設長など“影響力のある人”の前では自然と猫をかぶるようになります。
→ 「生き残るための技術」として二面性が定着しているのです。
⑤ 本性を見せるリスクを理解している
お局は経験豊富なので、自分の言動がどんな影響を及ぼすかをよく分かっています。
だからこそ、施設長の前で本音を出すような“危険な真似”はしません。
→ 「ここでボロを出したら不利になる」と計算できる冷静さを持っている。
STEP2 就業規則を確認する
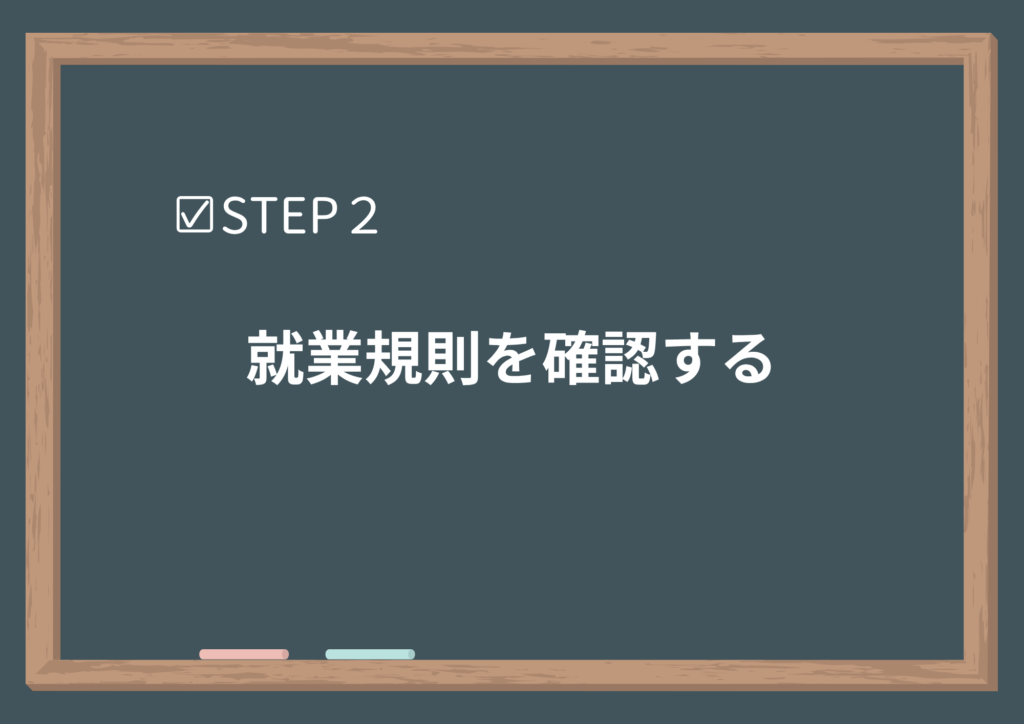
会社の就業規則の「懲戒(ちょうかい)」の項目を確認しましょう。
懲戒には「どんな行為が処分対象になるのか」「どんな処分が下されるのか」が明記されています。
つまり、お局の行動が“規則違反”に当たるかどうかの判断基準になる部分です。
懲戒の種類(一般的な例)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| けん責 | 口頭・書面での注意。記録が残る。 |
| 減給 | 給与を一部カット(法律上の上限あり)。 |
| 出勤停止 | 数日〜1週間の出勤停止。 |
| 降格 | 役職や職務を引き下げる。 |
| 懲戒解雇 | 最も重い処分。即時退職扱い。 |
パワハラ・暴言・利用者虐待などは、懲戒解雇の対象になることもあります。
懲戒項目でチェックすべき代表例
❶ 職場秩序を乱す行為
「他の職員に不快感を与え、職場の秩序・風紀を乱す行為をしたとき」
➜ 無視・陰口・威圧・仲間外れなどが該当する場合があります。
❷ パワーハラスメント等のハラスメント行為
「職員に対して暴力、威嚇、侮辱、誹謗中傷等のハラスメント行為を行ったとき」
➜ 明確に「パワハラ」「モラハラ」と書かれている施設も多いです。
この条項があると、人間関係の圧力行為も処分対象になります。
❸ 利用者に対する不適切対応
「利用者に対して暴言、威圧、虐待等の行為を行ったとき」
➜ 利用者への“強い圧”や“冷たい態度”も、この項目に該当する可能性があります。
❹上司・施設長の指示命令に従わない
「正当な理由なく上司の命令に従わないとき」
➜「施設長やリーダーの指示を無視して、自分のやり方を押し通す」お局も、この規定で注意・指導対象になります。
STEP3 情報を集める
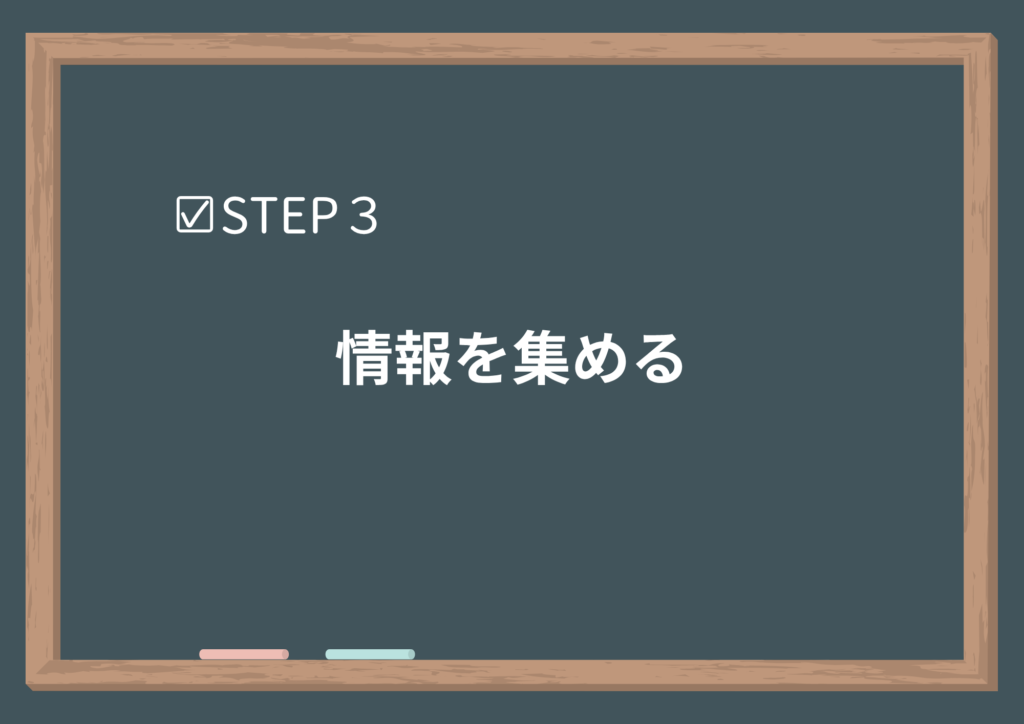
次に情報を集めていきます。
何の情報か?
懲戒に該当する言動です。
具体例:
利用者に対して「強い圧」をかけている具体例
①言葉で威圧するタイプ
・「またこぼしたの?何回言ったら分かるの!」
・「ちゃんとしないとご飯あげられないよ」
・「他の人はできてるのにねぇ」
特徴:表面上は“しっかりした職員”に見えるが、実際は利用者を“しつける”ように扱う。
影響:利用者が萎縮し、介助を拒否する・笑顔が減る・夜間に不安が強まるなどの心理的変化が起こる。
②態度で支配するタイプ
・食事介助の際に、わざと無言・無表情で行う。
・排泄介助中にため息や舌打ちをする。
・要求を聞き流したり、呼ばれても無視する。
特徴:「何も言っていないのに怖い」と周囲が感じるタイプ。
影響:利用者は「嫌われたくない」と気を使い、必要な訴えを我慢するようになる。
③ “かわいがり”の名を借りた支配
・「この人は私が担当だから口出さないで」
・「○○さんは私の言うことしか聞かないの」
特徴:一見、愛着のように見えるが、実際は他職員を排除し、自分の影響下に置く行為。
影響:利用者が特定の職員に依存し、ケアが偏る・他職員との関係が悪化する。
スタッフに対する「パワハラ」の具体例
① 公の場での叱責・否定
・申し送りやカンファ中に「そんなのも知らないの?」「あなたのやり方おかしい」
・利用者や家族の前で注意して恥をかかせる。
特徴:他人の前で優位に立ち、自分の“正しさ”を誇示する。
影響:若手や新人が発言できなくなり、報告・相談が減少。
② 無視・孤立化
・挨拶を返さない、話しかけても目を合わせない。
・申し送りで特定職員だけ話題から外す。
特徴:表立った暴言ではなく、じわじわ効く心理的圧力。
影響:職員が孤立し、退職やメンタル不調につながる。
③ 陰口・噂の拡散
・「○○さん、最近サボってるらしいよ」
・「あの人、利用者に嫌われてるんだって」
特徴:裏で人間関係を操作し、味方を増やして支配を強める。
影響:チーム内に不信感が広がり、連携が崩れる。
④ 業務の押し付け・過小評価
・「あなたはまだ新人だから、この仕事は無理でしょ」
・「私がやった方が早いからいいわ」→ 結果的に成長の機会を奪う。
・逆に「あなたしかできない」と、他人の分まで仕事を任せる。
特徴:上下関係を巧みに利用して支配する。
影響:ストレスと疲労が蓄積し、職員が燃え尽きやすい。
誰に聞き取りを行う?
対象者はスタッフです。
利用者からでも良いですが、認知症など覚えていない方を対象にしていることがあるので事実確認が難しいです。
スタッフから聞き取りを行う際、パワハラをされていても基本的には教えてくれないと思っておいたほうがいいです。
なぜなら、情報を流したことをお局にバレると仕打ちがくると考えているからです。
実際にわたしの施設であったことです。
若い女性スタッフが「〇〇スタッフ(お局)は高圧的な態度をとってスタッフや利用者をビビらせている」と施設長に伝え、お局と面談になりました。
お局は事実を認めず、「情報を流したスタッフは誰か」と犯人探しを始めました。
そこから、スタッフは誰も何も言えなくなりました。
聞き取りの方法
紙を使います。やり取りの痕跡が残りにくく、第三者に見られにくい方法だからです
面談など呼び出して聞き取りをする方法がありますが、お局やその仲間が嗅ぎつけ「何を話していたのか?」と探ります。
また施設長が行うとより目立ってしまいます。
なので、ここは介護リーダーの出番です。
現場で、お局が強くあたっているスタッフを見つけます。または、介護リーダーに「〇〇スタッフ無視されています」などスタッフからこそっと教えてもらった情報からターゲットを絞ります。
紙に書く内容ですが、わたしの場合『〇〇スタッフ(お局)からパワハラを受けましたか?事実を教えて下さい。〇〇スタッフ(お局)に直接話しをしているところをみられてしまうと、何か勘ぐられてしまう恐れがあります。あなたを守るために紙にしました。やりとりがみられにくいためです。できるだけ具体的に教えて下さい。「いつ・どこで・だれが・何をされたかのか」を紙に書いて教えてください。』と記載した紙を渡しました。大切なことは「あなたの味方です。あなたを守ります。」の意思表示をすることです。
情報を集約する
できるだけ多くの情報を集めます。信憑性が高くなるからです。
わたしは、スタッフ5名、計20件の懲戒に該当する情報を集めました。
抽象的な被害内容ではなく、「いつ・どこで・だれが・何をされたかのか」まで具体的にします。
まとめ方は自由です。Wordや手書きなど。注意事項として、自分だけしか見れない場所に保管しましょう。
例えば、全スタッフが見れるパソコンの共有フォルダや机の引き出しなども危ないです。フォルダや机にしても鍵をかけましょう。その鍵の保管場所も徹底して管理しましょう。
STEP4 施設長に報告する
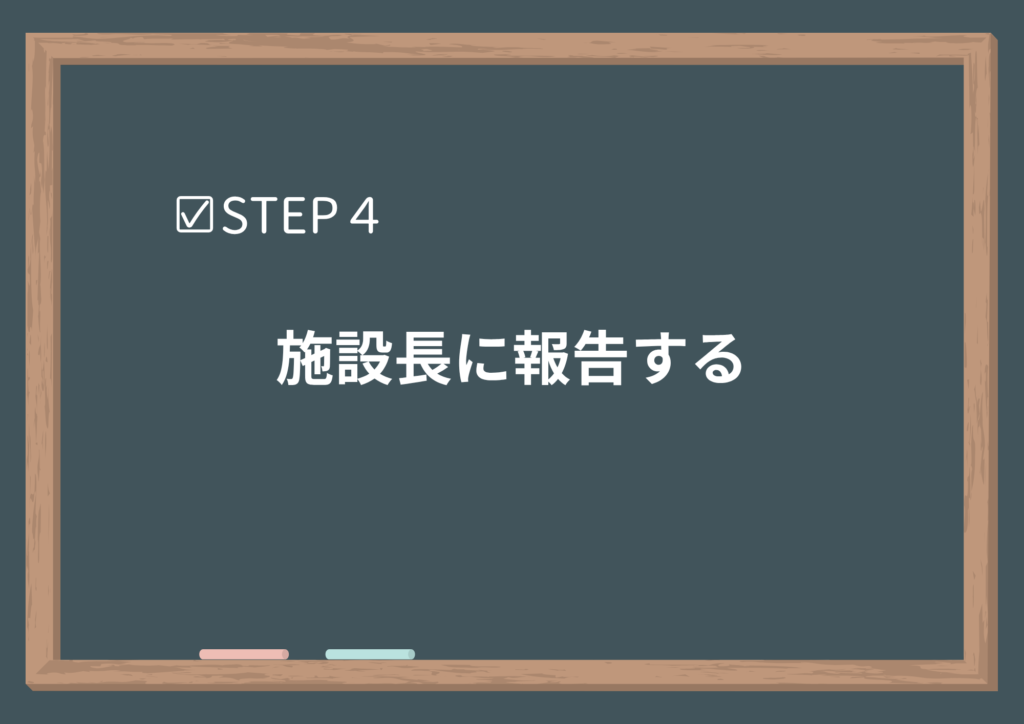
情報が集まったら施設長へ報告です。
まず伝えることは「情報をくれたスタッフをなんとしても守る」ことを共通認識してもらうことです。
お局から仕打ちが来るかもしれない覚悟で情報を提供してくれています。施設長は直接被害者とやりとりをしていないので温度差があります。だからこそ、最初に伝えるのです。
残念ながら、人事権のない介護リーダーだとやれることはここまでです。
内容が内容だと、施設長の上司である部長や本部長が出てきてお局との事実確認の面談が組まれます。
施設長や部長に任せれば、うまくやってくれる、頼れる人であればいいでしょう。
ただ、頼れない場合もあります。また施設長が味方とは限らない場合もあります。
その場合は、上長に相談せず本社に報告しましょう。
就業規則または職員ハンドブックに「相談・通報窓口」や「ハラスメント相談窓口」が明記されています。
そこに記載の部署名や連絡先が、正式な本社への報告窓口のことが多いです。
わたしはこの方法を取りました。上長からすれば「なぜ自分に相談がなかったのか」と信頼関係が揺らぐ可能性があります。しかし、わたしは上長との関係よりもスタッフや利用者を守ることを優先していたため、ためらいはありませんでした。
結果として、社長にまで話が行き部長が施設に駆けつけお局と面談を行い事実を認めたので退職となりました。
まとめ:就業規則は「最強の味方」になる
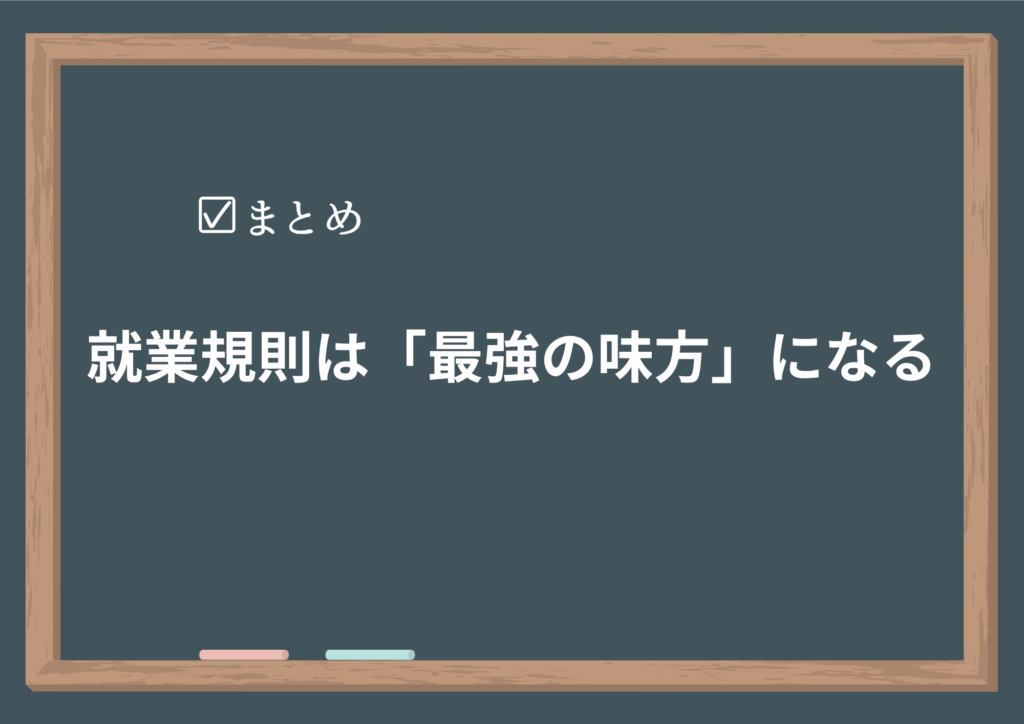
お局問題は、どんな職場にも起こりうる深刻な課題です。
人間関係のもつれとして片づけてしまうと、いつまでも状況は変わりません。
しかし、
「就業規則」という“会社の正式ルール”を使えば、状況を動かすことができます
なぜなら、就業規則は感情ではなく「事実とルール」で判断できる唯一の武器だからです。
お局の行動が懲戒項目に該当すれば、会社としても無視できなくなります。
つまり、“個人の戦い”ではなく、“会社全体の問題”にできるのです。
わたし自身、就業規則を使うまでは「何をしても変わらない」と諦めかけていました。
でも、ルールを味方につけた瞬間、1ヶ月でお局が退職する結果になりました。
あなたの職場でもきっと変えられます。
孤独に戦う必要はありません。
就業規則という“会社の盾”を使えば、お局問題は解決に向かいます。
【介護リーダー必見】「リーダーの役割がわからない」「言われたことしかできていない」と悩んでいるリーダー向けです▼
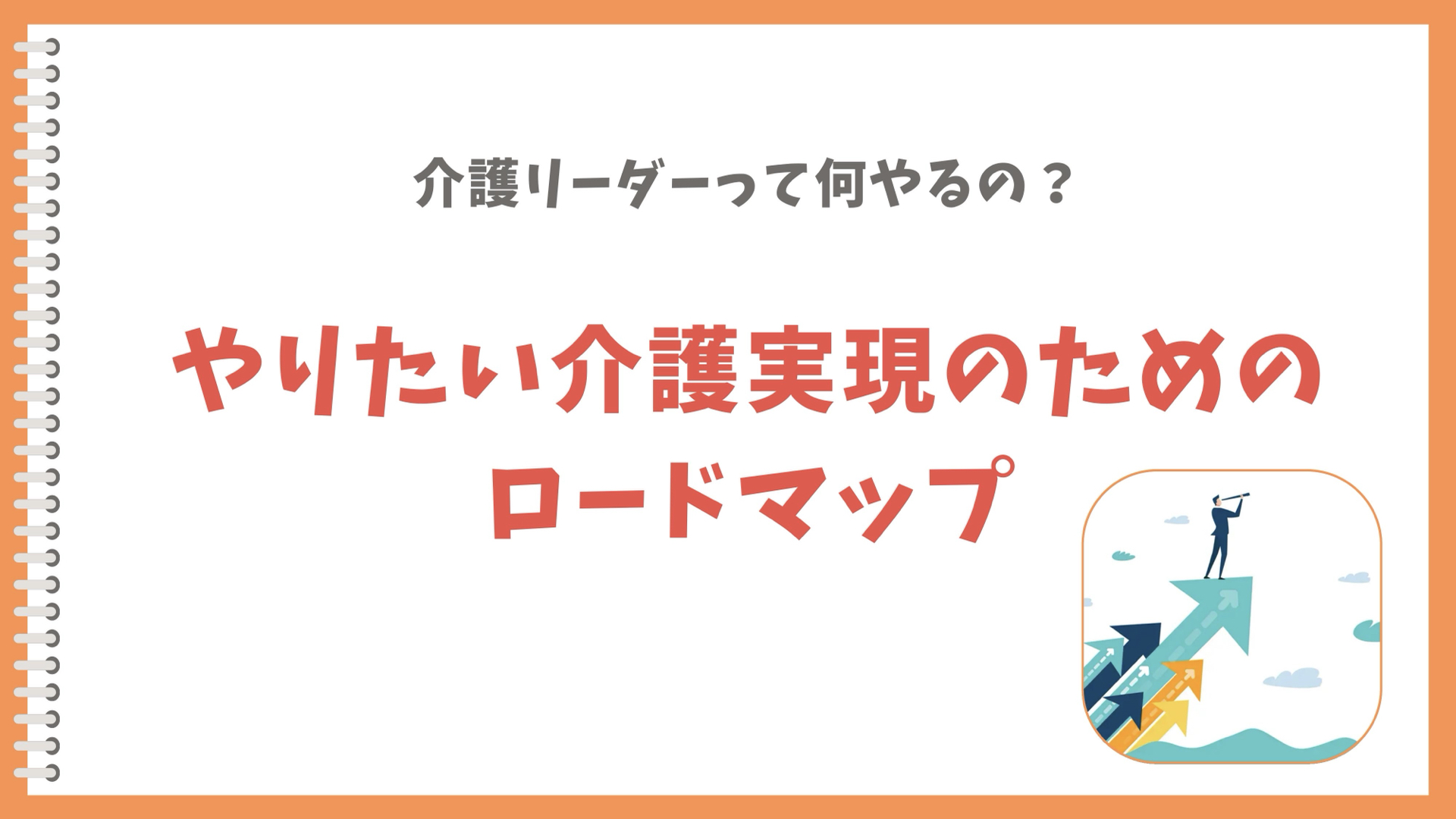 【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
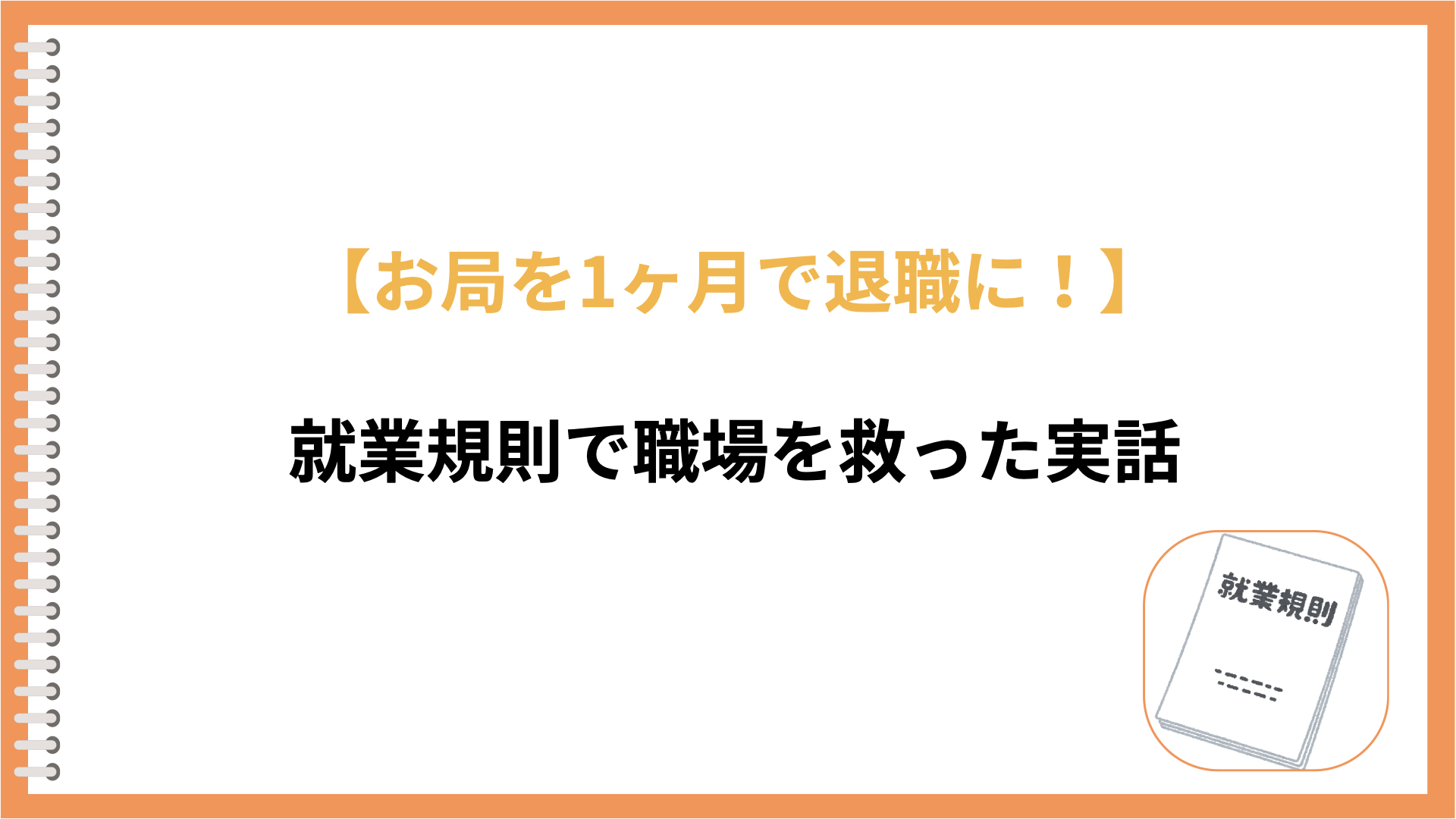
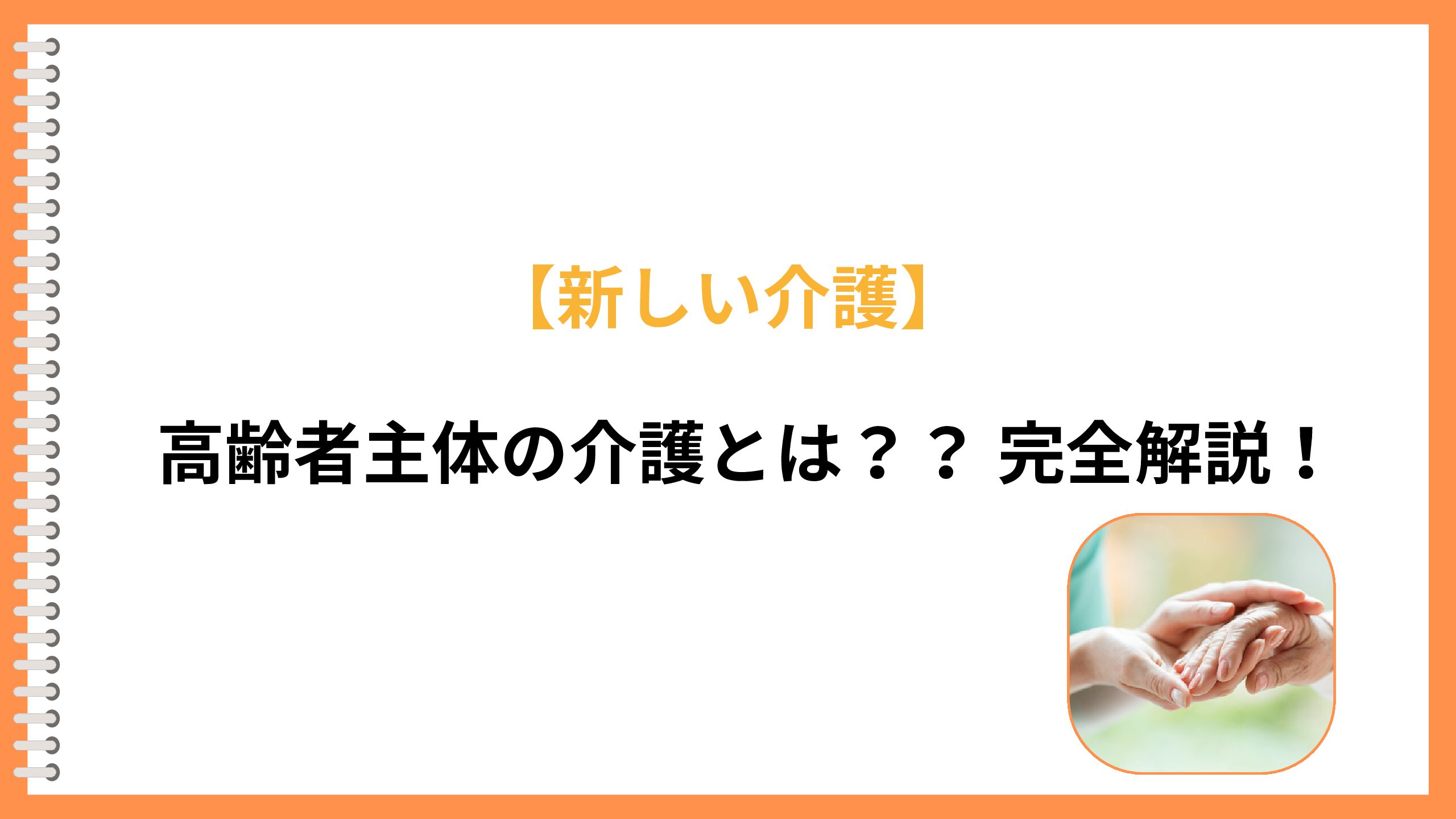

コメント