事故が起こるたびに「再発防止をしなければ」と思っても、毎日が忙しく、業務をこなすだけで精一杯。
結果、何も策を打てず同じ事故が何度も繰り返してしまう。「今のままじゃ、どうしようもできない。」と諦めていませんか?
実は、スタッフに事故の原因分析・対策・振り返り方法を教えることができれば、ある程度は解決できます。
そのためには、事故再発防止研修の内容に拘っていく必要があります。
事故が起きた際、根本的な原因まで分析して対策を立てている施設は少ないです。
例えば、転倒事故に対して「見守りを強化する」といった対応で終わってしまう場合です。なぜ転んだのか?を考えられていません。結果、的を得ない対策となり事故が再発します。
事故再発防止研修では、原因の分析に一番力を入れます。この力が身につけば、7割ほど再発防止できたと言っても過言ではありません。
わたしは、年間110件の事故が起きている施設でリーダーとして働いていました。事故再発防止研修をすることによって、52件にまで減らすことができた実績があります。
この記事では、事故再発防止研修でおこなう3つの取り組みを順にお伝えします。
研修を通じてスタッフに事故再発防止の意識が根付いた時、利用者のQOL(生活の質)の維持・向上や自分自身の負担の軽減を感じることができるでしょう!
事故再発防止研修の目的・内容・流れ

目的
まず、目的から考えていきましょう。
そもそもなぜ、事故を防止する必要があるのでしょうか?
わたしは、
利用者のQOL(生活の質)の維持・向上の為
と考えています。
転倒して骨折し寝たきりになってしまうなど身体的・精神的なダメージを防ぐことが重要です。
この目的を共通認識とし、研修を行います!
内容
研修参加者には、
1.原因の分析
2.対策の立案
3.振り返り
の3つを順に考えてもらいます。
流れ
- 研修担当者を2名決める。
1名は進行役、1名はホワイトボード記入者。最低でも2名必要です。 - 取り上げる事故を決める。
実際に起こった過去の事故を取り上げます。再発防止がなかなか進んでいない事故がいいでしょう。 - 研修場所を決める。
事故がおこった現場をおすすめします。実際の現場で行うことによって、今まで見えてこなかった原因が見えることがあります。場所が確保できない場合は、会議室などで行いましょう。 - 研修当日
1️⃣進行役とホワイトボード記入者は、事故があった現場を発見時と同じような環境にします。
例:入口の電気が消えており、椅子が倒れている、など。
2️⃣進行役は参加者に研修の目的と内容を説明。その後、STEP1〜3を行っていきます。
【STEP1】事故の「原因を深掘り」する
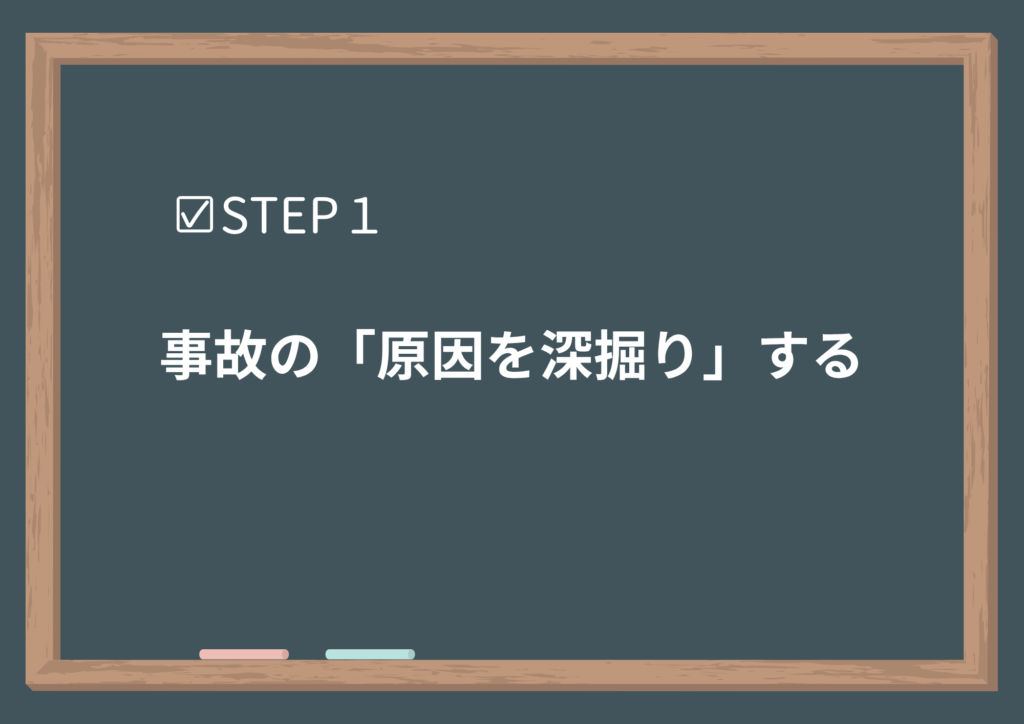
参加者に「○月○日○○様の居室で起きた転倒事故です。そのときの環境を再現しています。では、原因の分析を行ってください!」
と言っても何をすべきか参加者はわかりません。
まずは、進行役が以下の説明をしましょう。
⏬️⏬️⏬️⏬️⏬️⏬️⏬️⏬️⏬️⏬️⏬️⏬️⏬️⏬️⏬️⏬️
同じ事故が起きる理由=原因分析が甘いから
「また同じ利用者が転んだ」「対策をしたはずなのに…」というとき、根本的原因にたどり着けていない可能性があります。
事故原因は3つの視点から分析する
- スタッフ視点
- 本人視点
- 環境視点
原因を分析するには、現場検証することが効果的です。現場にしかわからない事実があるからです。現場に行かず「あーだよね」「こーだよね」と議論することは推測で話しているだけです。根本的原因からは遠ざかっていくでしょう。
原因は「直接的」と「根本的」に分ける
| 原因の種類 | 説明 |
|---|---|
| 直接的原因 | 表面的に見える具体的な要因(例:目を離した) |
| 根本的原因 | 背景にある構造的な要因(例:配置の問題・人手不足) |
【具体例】
食堂にて独歩禁止の認知症の方が、スタッフが目を逸らした瞬間に転倒していた。
スタッフ視点:(直接)目を逸らしてしまった (根本)他利用者に呼ばれた
本人視点:(直接)一人で歩いてしまった (根本)認知症がある
環境視点:
(直接)転倒された方の食席がスタッフから遠く見えにくい場所にある
(根本)一人では立ち上がらないだろうと思い込みどこでもいいと考えていた
原因の深掘りには、「なぜ?」を5回繰り返す(5WHY分析)の手法が有効です。
根本的原因か判断する方法は、
逆にしても自然に説明できるかどうかで判断します。
根本的要因を探す際は「なぜ?」を唱えていきますが、反対から「だから、〜だ」で無理なく遡る事ができれば逆の因果関係が成り立つことになります。
例えば、
「目を逸らしてしまった。」→なぜ?→「他利用者に呼ばれた。」
「他利用者に呼ばれた。」→だから→「目を逸らしてしまった。」
直接的原因が解決しても現状の回復にしかならず、問題が再発する可能性が高いです。よって、再発防止には根本的要因に対策を打つ必要があります。
⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️
参加者に原因分析の重要性や考え方を理解してもらいます。
そのあと、スタッフ・本人・環境の視点から回答を出してもらいます。
ホワイトボード記入者は、参加者の回答一つひとつ記載していきます。
この時、進行役はスタッフの回答に「なぜ?」と聞き返してみましょう。根本的原因がわかるまで考えてもらいます。
【STEP2】具体的な対策を立てる
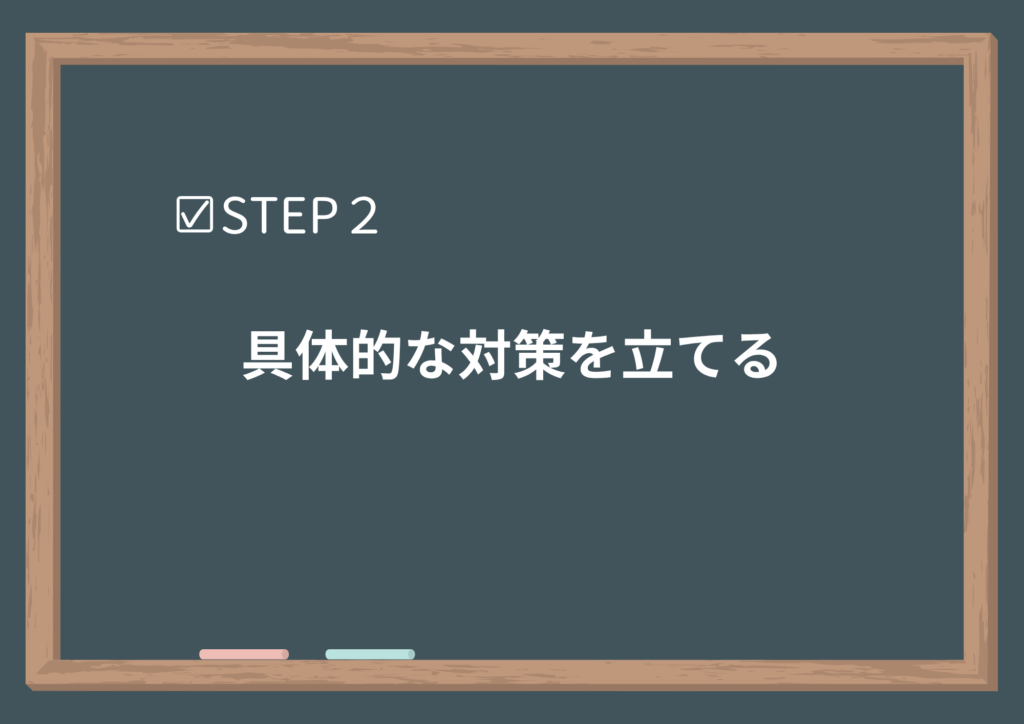
根本的原因がわかったら次は対策を立てます。
対策を立てる際は、「誰が、いつ、どこで、何を、どのように」まで具体化することがポイントです。
でなければ、誰が何をどうやって実行するのかわからず対策をあげて終わりになってしまいます。
【例】転倒事故の対策
- スタッフの対策
→ 食堂に2名スタッフが配置出来るように、本日フロア責任者が業務プログラムを作り直す - 本人の対策
→立ち上がった理由を3日間本人に確認し、記録する。最終日にフロア責任者が分析し対策を打つ - 環境の対策
→ 死角になる席がないようにレイアウトを食堂担当スタッフが本日変更する
→ 1ヶ月かけて全スタッフに危険予知訓練(KYT)を行う。担当者:研修スタッフ
立てた対策は、日々徹底して行い、毎日記録に残しましょう。振り返りの際、見返す為です。
【例】記録の書き方
○月○日 記入者:〇〇スタッフ
・スタッフの対策
→業務プログラム作成済み。常にスタッフ2名配置できている。そのため緊急の対応も可能
・本人の対策
→本人立ち上がったため理由をきく。「トイレに行きたい」とのこと。
・環境の対策
→レイアウトを変更する。今のところ視覚なく全体を見渡せる。
→危険予知訓練、○○スタッフと○○スタッフが実施済み
▷ 危険予知訓練(KYT)とは?
利用者のADL(日常生活動作)から事故リスクを予測し、対応策を事前に考える訓練。未然防止の意識を高めるのに効果的です。
【STEP3】振り返りと再評価を習慣化する
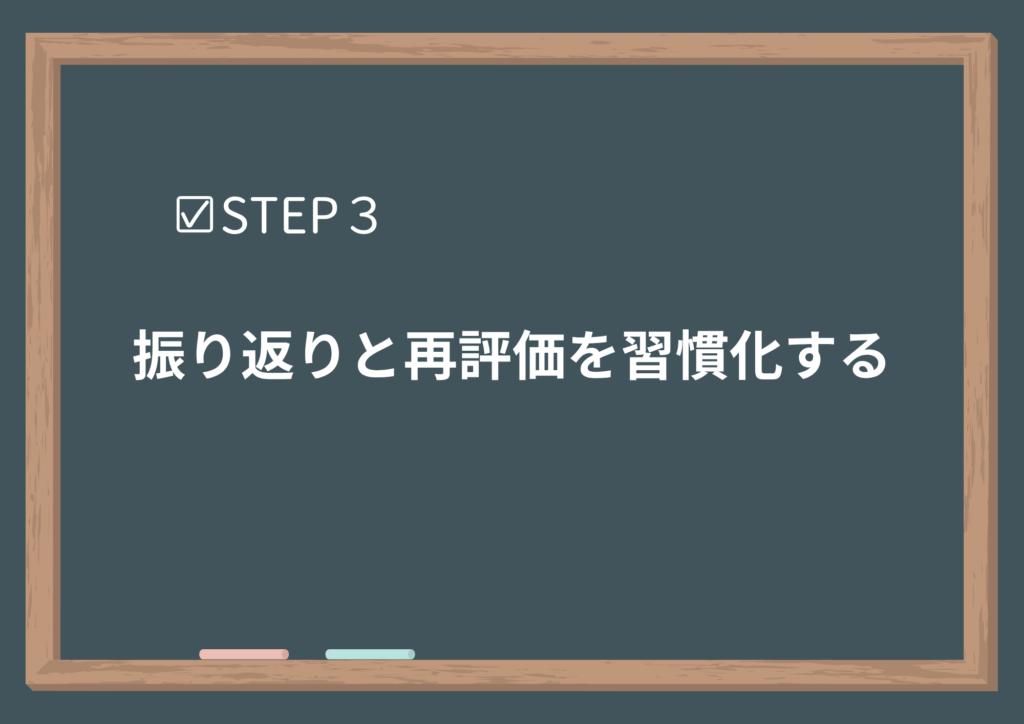
原因分析から対策まで参加者に考えてもらうところで研修は終了です。
ただ、事故を再発させないためには振り返りも必要です。
「対策を立てて終わり。」ではありません。
対策を立てたら「実行→記録→振り返り」の順で行います。
振り返りの習慣化
振り返りは事故発生から1週間後に行います。
朝の申し送りの後などに「事故カンファレンス(10分間)」を設けましょう。日常業務に組み込むことで、継続しやすくなります。
同じ利用者の同じ事故が起きていなければ、再発防止ができたということです。
再発した場合は、原因の再分析を行います。そして新たに対策を立て実行していきます。
原因の分析が誤っていない場合(根本的原因が正しい場合)は、対策の見直しをしましょう。
対策が実行できていないケースはよくみかけます。「対策は合っていたのに、実際にできていなかった」となれば評価ができません。そうならないように、実行した記録を毎日残していきましょう。
事故を減らす「仕組みづくり」がカギ
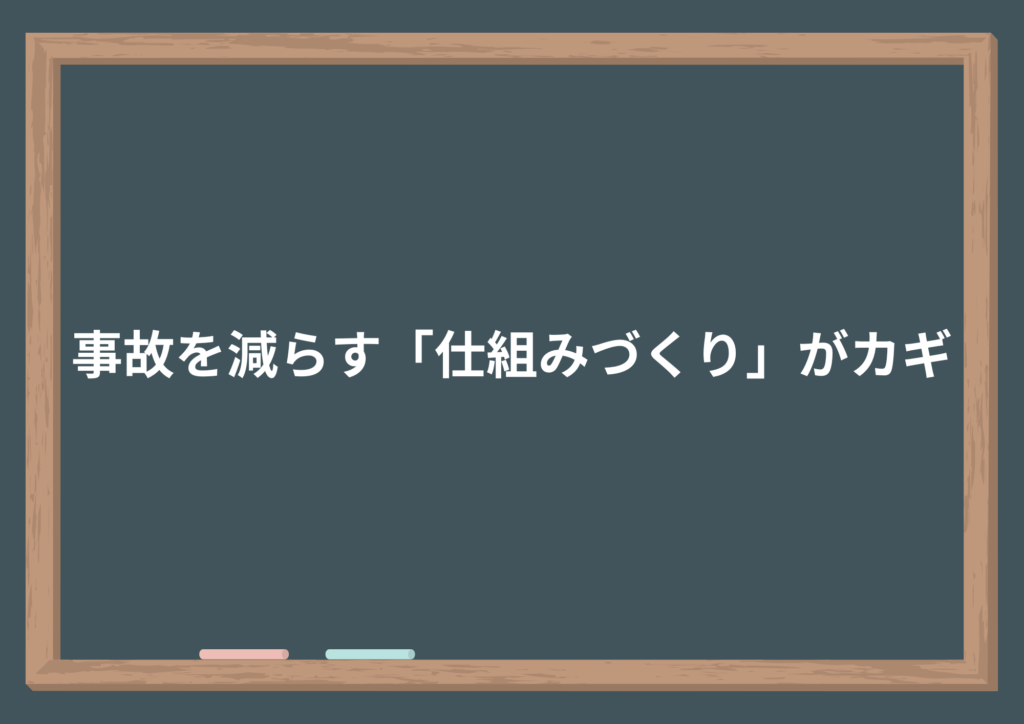
3つのステップは、スタッフの意識を揃え、理想のケアを「再現できる形」にしていくヒントになるでしょう。
3ステップは一時的な対応ではなく、仕組みとして定着させることが重要です。
▷ 実践例
- STEP1:現場検証を事故発生時に必ず行う(原因の分析)
- STEP2:その場で対策を話し合う(対策を決める)
- STEP3:記録ノートやSNSで実施状況を記録し、一週間後に振り返る(振り返りをする)
「対策して終わり」ではなく、「動いて、見直して、改善する」サイクルを回していきましょう。
事故対応におけるチームワークの具体的メリット
チームワークを強化することで、以下のメリットがあります。
- 事故リスクの早期発見と迅速な対応
- スタッフ間の情報共有がスムーズになりミスが減る
- 家族対応においても一貫した説明が可能になる
- スタッフの心理的負担が軽減され、チーム全体の雰囲気も良くなります。
まとめ:事故再発防止は「仕組み」と「意識づくり」がすべて
事故再発防止は、原因を深く掘り下げ、対策を具体化し、振り返りを習慣化することで成果が出ます。
一度の研修で完璧を目指す必要はありません。大切なのは、「分析 → 対策 → 振り返り」のサイクルを止めないことです。
現場では忙しさに追われ、「また同じことが起きた…」と感じる瞬間があると思います。
でも、同じ事故を繰り返さない仕組みを少しずつ積み上げることで、確実に現場は変わります。
事故を“責任”ではなく“成長のきっかけ”と捉え、施設全体で学び合える文化をつくる。
それが、利用者のQOL(生活の質)を守る最も確かな方法です。
そして何より、スタッフ一人ひとりが「事故を減らしたい」という気持ちを持ち続けること。
その意識こそが、再発防止の最大の力になります。
書籍紹介
介護現場でも使える問題解決に役立つ本です。
是非、参考にしてください。
【介護リーダー必見】「リーダーの役割がわからない」「言われたことしかできていない」と悩んでいるリーダー向けです▼
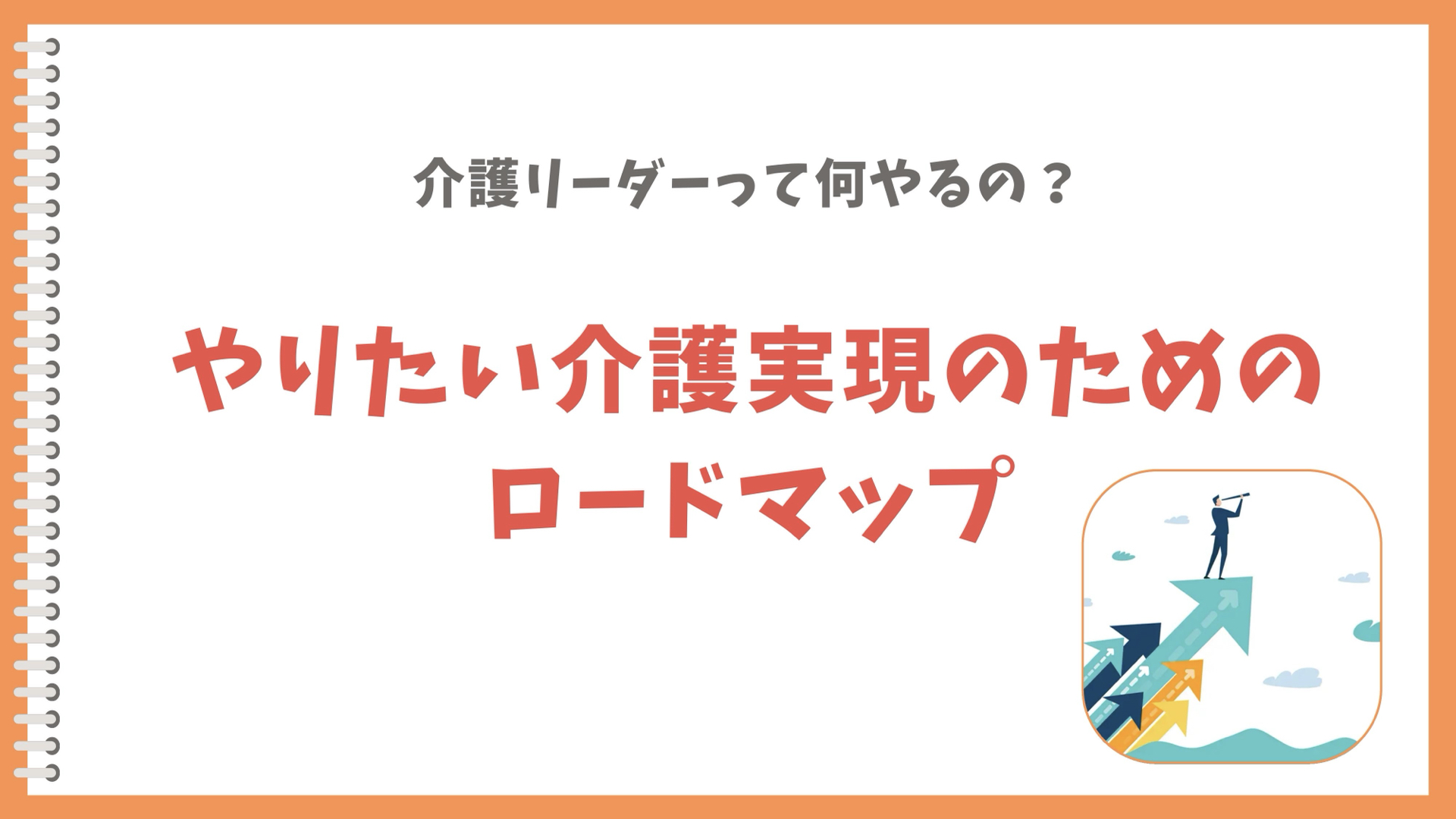 【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
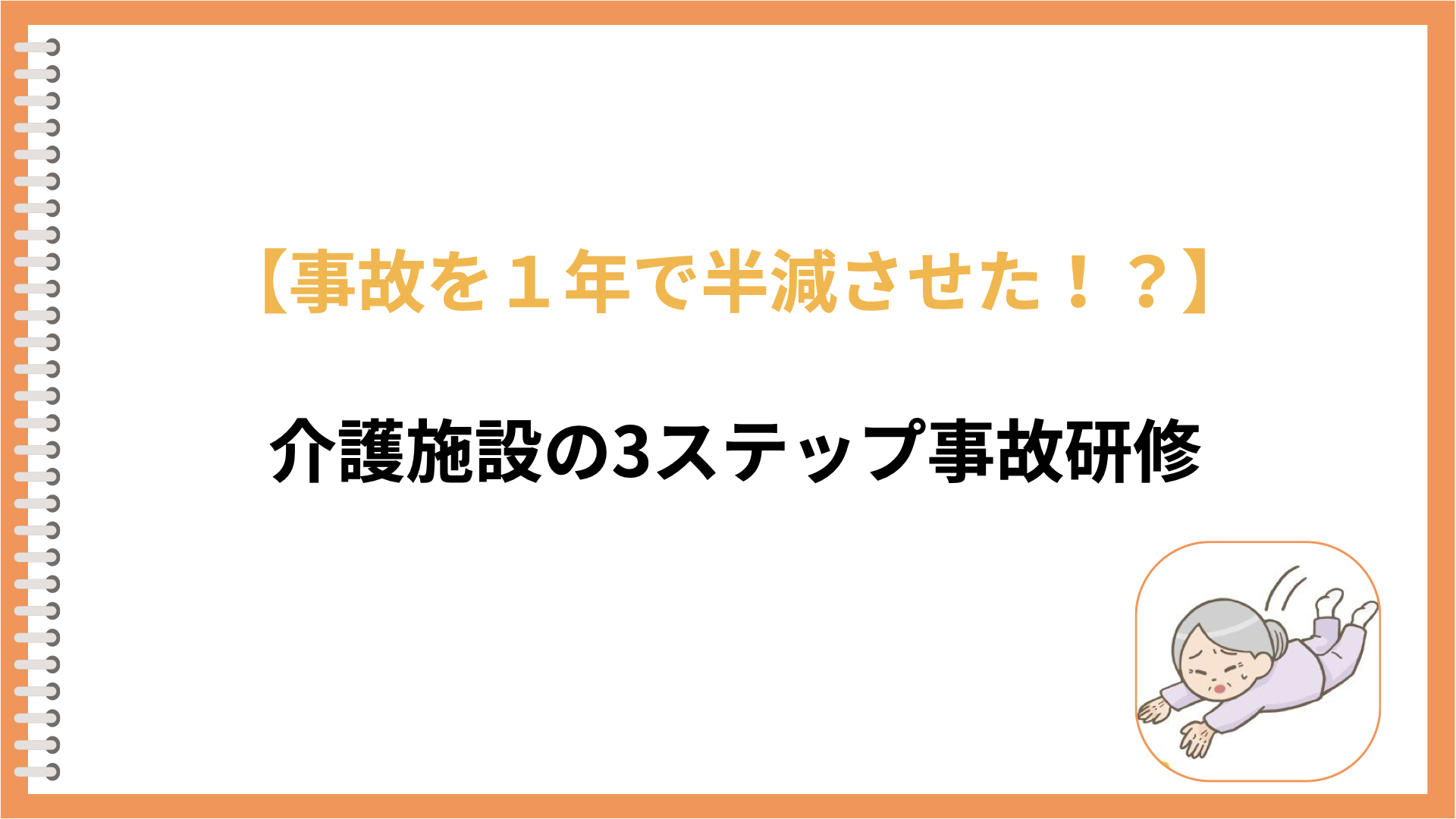
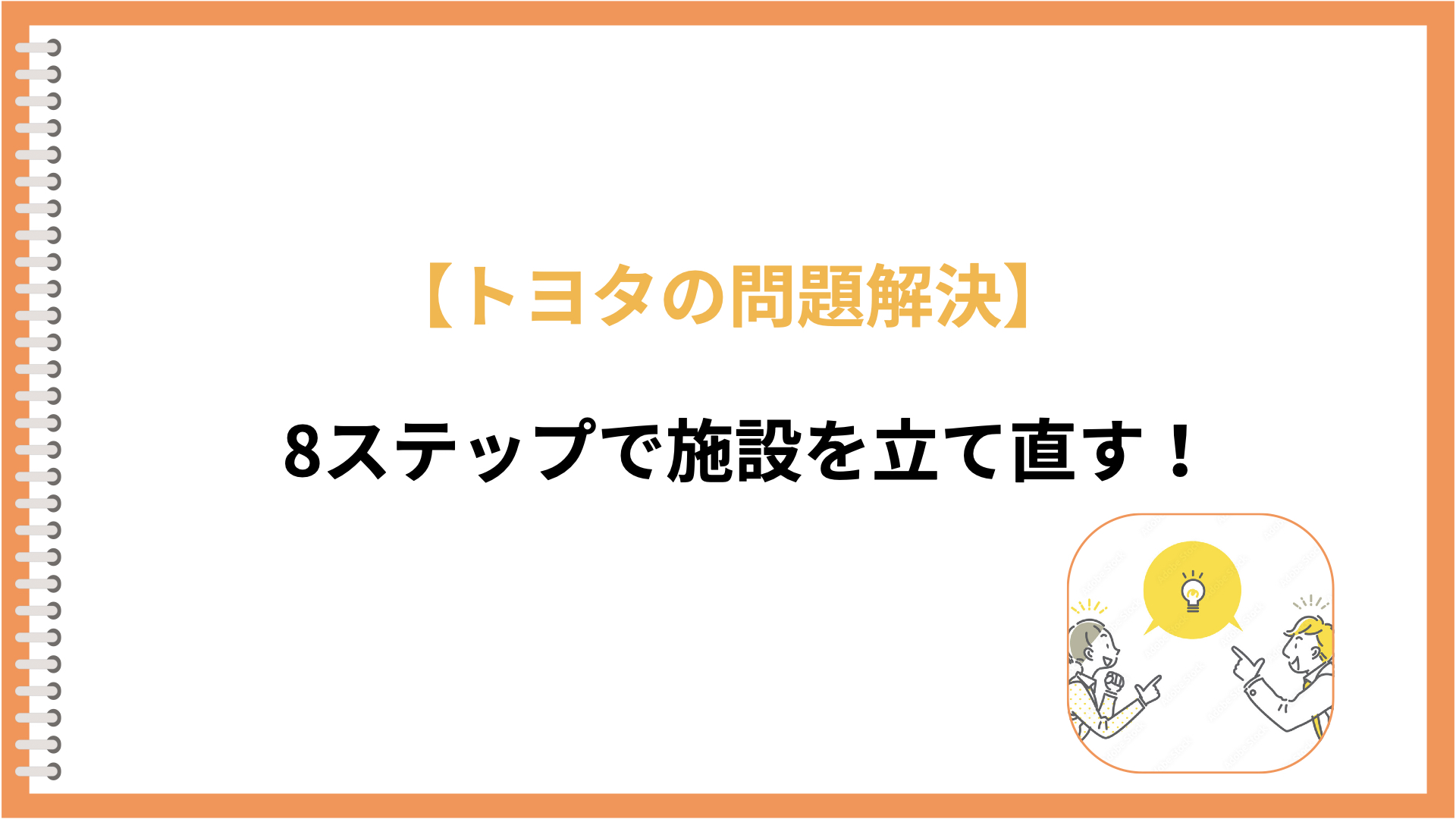

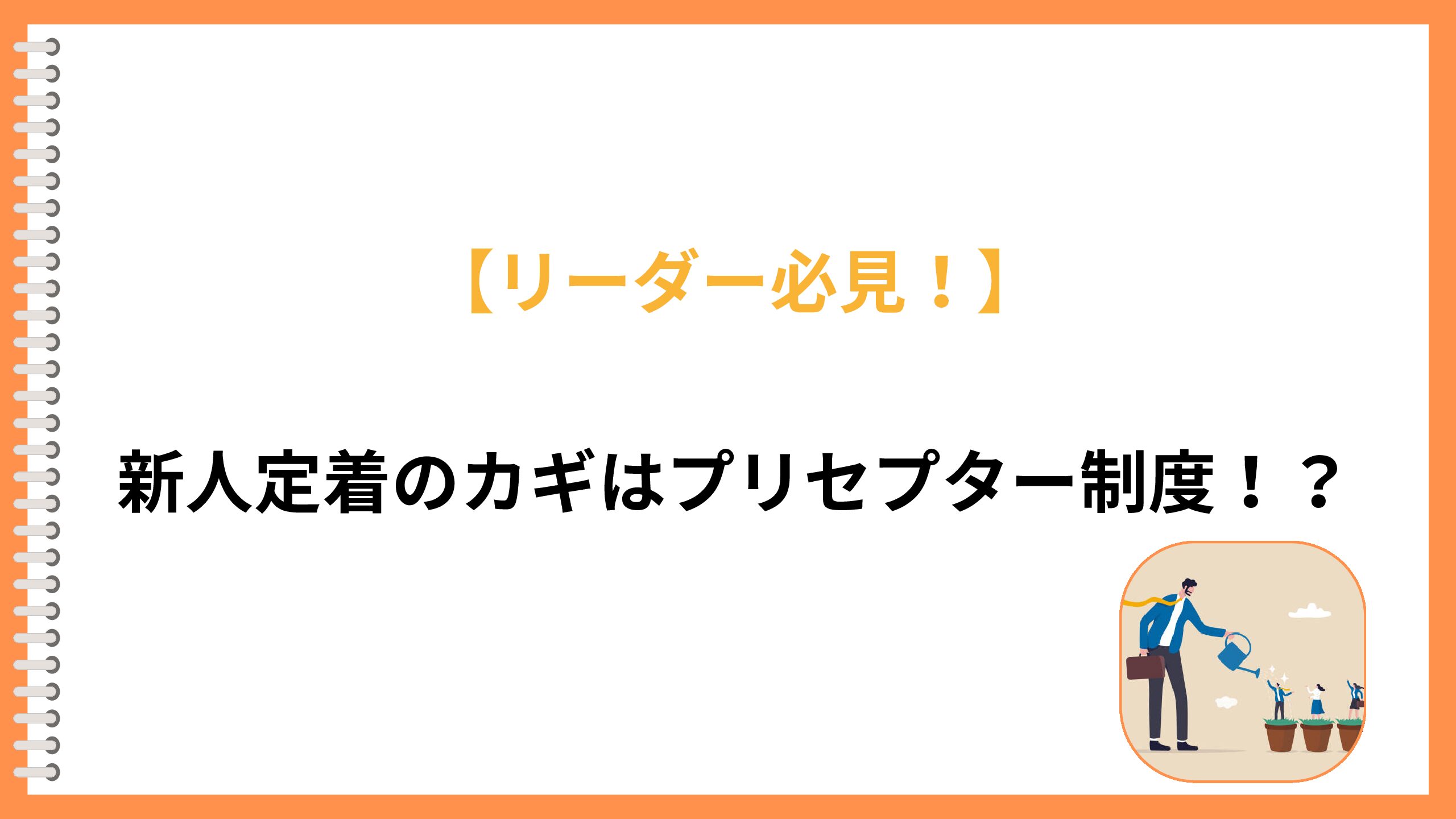
コメント