ベテランも新人も“なんとなく”業務をこなしているだけで、根拠に基づいたケアができていない。
リーダーとして現場を見ていても、「どうすれば専門性を育てられるのか」と悩むことはありませんか?
その答えの一つが、“専門に特化したチーム”をつくることです。
なぜなら専門チームが“知識と実践の中心”となり、現場全体に専門性を波及させる役割を担うからです。
介護の現場では、誰もが同じように業務をこなしているように見えても、実際には「判断の根拠」や「ケアの目的」が共有されていないことが多くあります。
専門に特化したチームをつくることで、特定の分野(例:認知症ケア、介護技術ケアなど)に対する知識と技術を高め、標準化された実践を施設に広げることができます。
つまり、専門チームは「現場のリーダー役」として、“なんとなくの介護”を“根拠ある介護”に変える起点になるのです。
わたしは、介護リーダーという立場で、「教えても定着しない」「考える介護が根づかない」という壁にぶつかりました。 しかし、専門チームを立ち上げてからは、スタッフが自ら判断し行動する機会が増え、ケアの質が安定しました。
この記事では、専門チームの立ち上げから、施設全体に専門性を広げるマネジメント方法までを解説します。
この記事を読むと、スタッフの主体性を引き出す仕組みや現場を自走させる方法がわかります。
STEP1 専門チーム立ちあげる&解体する
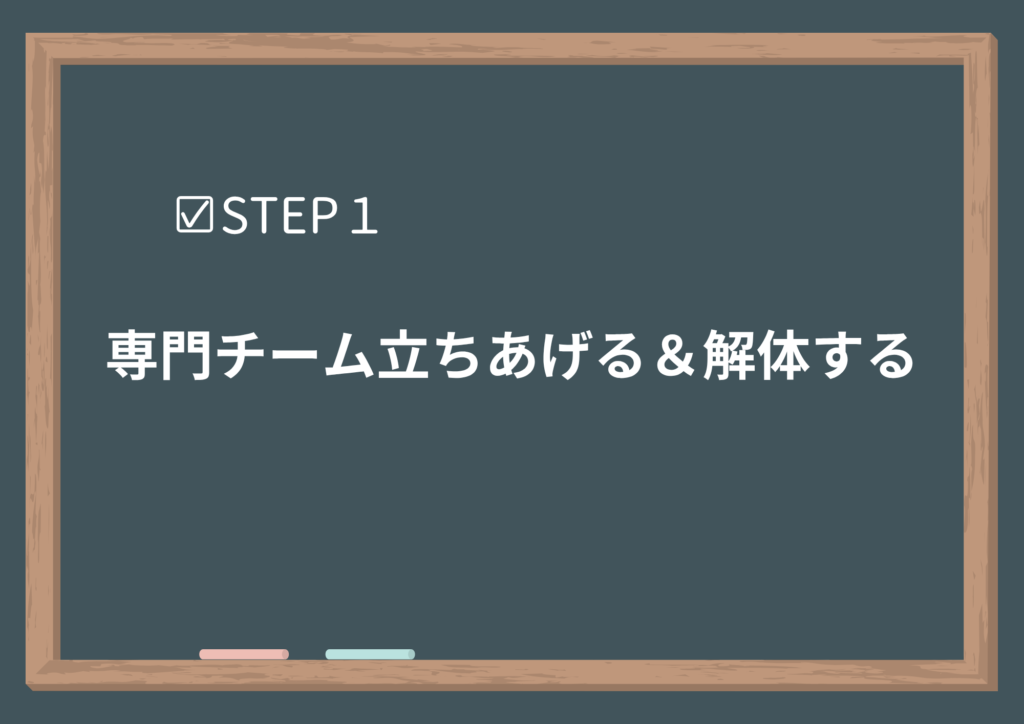
施設の課題を把握し、どの専門チームを立ち上げるか考えます。
やみくもに専門チームをつくることは避けるべきです。
介護技術のレベルアップであれば介護技術チーム(※プロジェクトや委員会という呼び方もします)
事故が多発している場合は事故再発防止チームなどです。
わたしの場合
介護技術のレベルが新卒、中途採用スタッフによって大きく違っていた⇒介護技術チーム
認知症ケアとは何をすべきなのかわからないスタッフが多数いた⇒認知症チーム
繰り返し転倒事故を起こす利用者が複数名おり再発防止ができていなかった⇒事故再発防止チーム
配属されたスタッフの退職率が高い⇒人材育成チーム
例外:
利用者のニーズ(ADLの課題ややりたいことなど)を把握しているスタッフが少ない⇒居室担当制にする
次に、必要のない既存のチームを解体します。
解体するべきか3つの判断基準
① 存在意義があいまいになっている
「毎年なんとなくやっている」「報告のためにやっている」状態。
👉 チェックポイント:
- チームの“存在意義”を説明できるメンバーが何人いるか?
- 目的が理念・施設方針とズレていないか?
② 成果が「現場で見える形」で出ていない
メンバーのモチベーションも低下している。
👉 チェックポイント:
- 過去半年〜1年で、現場に変化(事故減少・ケア改善・学びの共有など)はあったか?
③ 施設の現状と課題に合っていない
上手くいっていない施設の現状に対しチームをつくり解決します。すでに解決している場合、チームの必要性はありません。
👉 チェックポイント:
- そのチームの存在意義は果たせましたか?
一つでも当てはまれば解体しましょう。
STEP2 チームの存在意義と年間目標を決める
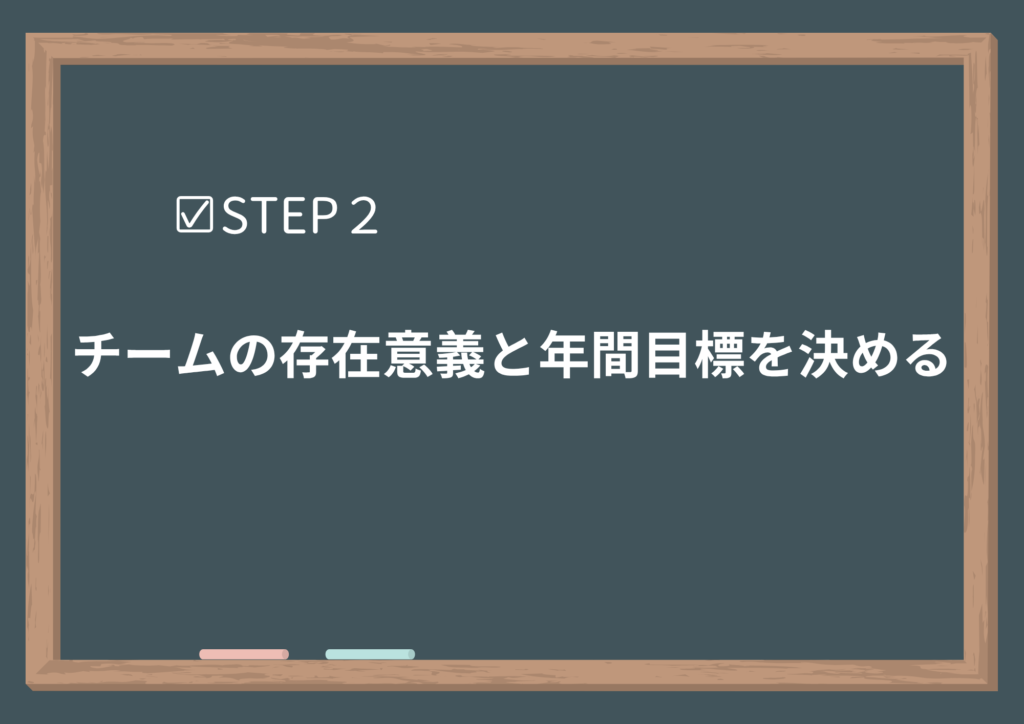
存在意義と年間目標は、最終的にはチーム結成後にメンバーが話し合って決めますが、事前に介護リーダーも考えておきます。なぜなら、すべて任せてしまうと施設が目指している方向と違う方向に進むかもしれないからです。
わたしの場合
施設の目指す方向:介護現場を“ふつうの生活”に近づけ、なじみの関係を築く
介護技術チーム
存在意義: 利用者の残存能力を活かし、“できる喜び”と自立した生活を支える
年間目標:
①月2名を対象に、ADLに合ったケア方法を検討し全スタッフに共有する
②3ヶ月に1回、介護技術に関する勉強会(研修)を開催する
認知症チーム
存在意義:認知症の方が安心して穏やかに生活できる環境を整える
年間目標:
①BPSD(行動・心理症状)の軽減を図る
② 安心・安定した生活環境を整える
事故再発防止チーム
存在意義:事故を未然に防ぎ、再発を防止することで利用者の生活の質(QOL)を守る
年間目標:
①前年度より事故件数を削減する(3STEPの定着)
②危険予知力を高めるため、KYT(危険予知トレーニング)を2ヶ月に1回実施する
事故が何度も起こる。これ以上、繰り返さない方法は?▼
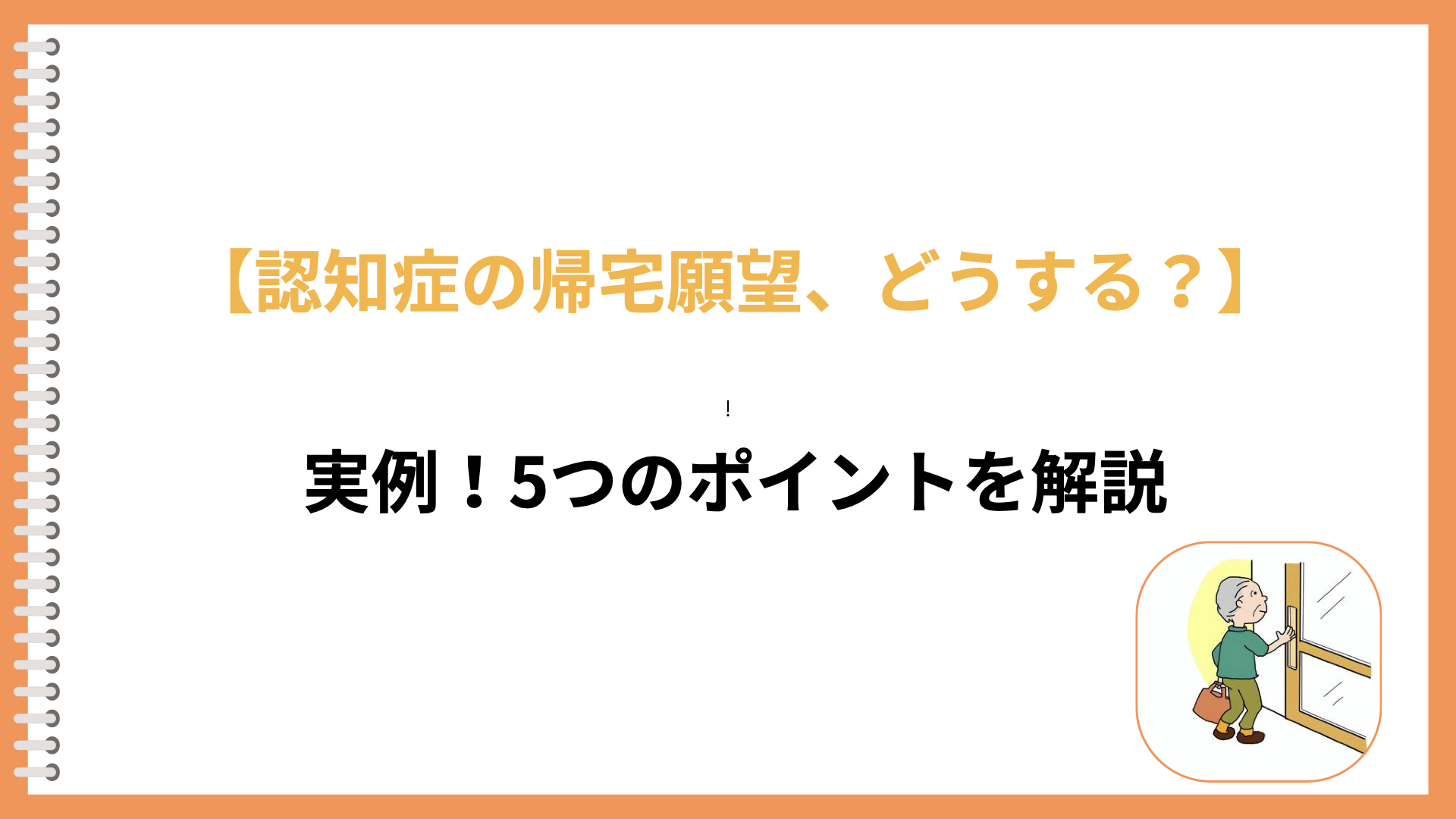 【事故を1年で半減させた!?】介護施設の3ステップ研修で再発防止を実現
【事故を1年で半減させた!?】介護施設の3ステップ研修で再発防止を実現
人材育成チーム
存在意義:施設の理念や思いを叶えるためのピースになるように育成をする
年間目標:
●通常業務
①全シフトで独り立ちできる職員を育てる
(独り立ち:一人で業務を遂行でき、介護技術を安定して発揮できる状態)
●利用者との関わり
① 三大介護(食事・入浴・排泄)・認知症ケア・終末期ケアにおいて、利用者主体の支援を実践できる
② 担当利用者の“思い”を1つ、具体的な形にする
残ってほしかったスタッフが辞めていく。施設全体で人材育成に力を入れていくには?▼
例外:
居室担当
存在意義:利用者の「自分らしく暮らす」をサポートする
年間目標:
① 三大介護(食事・入浴・排泄)を実践する
② 三大介護以外の支援(認知症ケア・終末期ケアなど)を実践する
③ 利用者一人ひとりのニーズに応える
大事にしたこと‼️
存在意義がスタッフ主体になっていないか?
利用者を主体としてものになっているか。主語は利用者か。
ここを間違えると、スタッフのための施設になります。
例:
介護技術チーム
存在意義: できるだけ迅速かつ安全におむつ交換を行うようにする
年間目標:
3ヶ月に1回、介護技術研修を実施する
スタッフが行動の目的を理解せず、『ただ早く交換する』ことだけを追いかけると、本来のケアの意味を見失ってしまいます。これだとスタッフ主体の考え方です。
例として、大腿骨骨折をしている利用者への対応を考えると、スタッフは体位変換のたびに痛みが出ることを踏まえ、できるだけ迅速かつ安全におむつ交換を行う。これが利用者主体です。
STEP3 施設長に専門チームをつくる&解体することを伝える
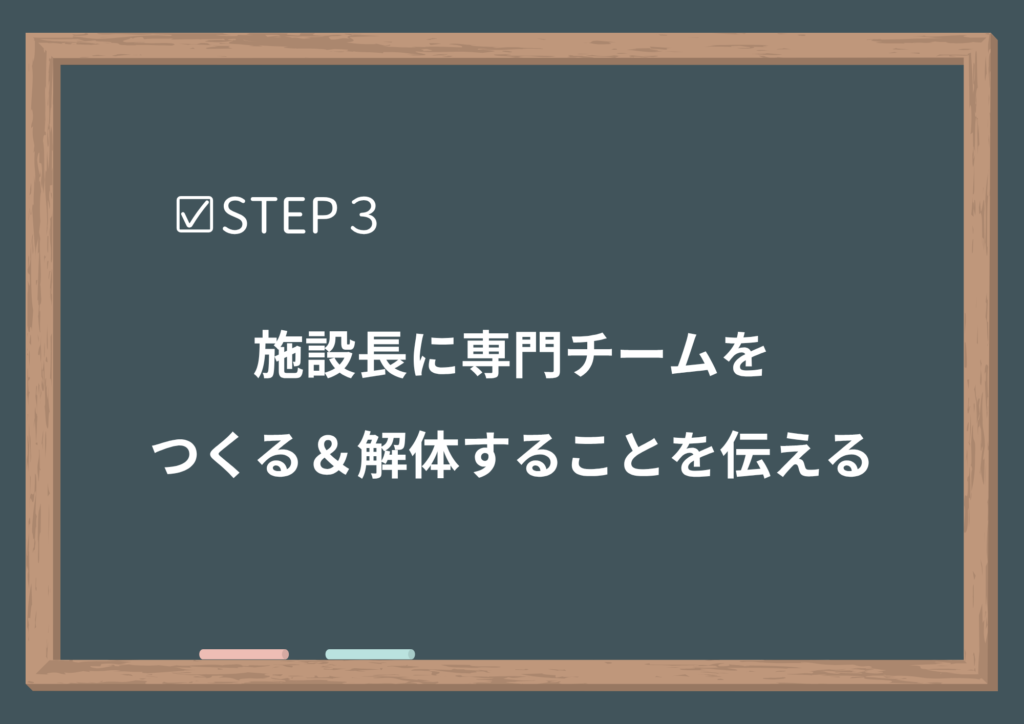
施設の課題を解決するために専門チームをつくる&解体することを施設長に口頭で伝えます。
新たにつくる予定の専門チームそれぞれどのような存在意義を持っているのか。を説明します。
そして、今後の動きも一緒に伝えます。(STEP4以降です)
また、解体するチームの理由も伝えます。
施設長の意見をしっかり聞きましょう。「人材育成チームはつくる必要がないので」と否定的なことを言われるかもしれません。その場合は受け入れましょう。「何としても必要だ」と思う場合は熱意を伝え、「確かに」と納得できる場合は諦めましょう。施設長が最終判断者です。うまくいかなかった際は、施設長の責任になります。相手の立場を理解することも大切です。
ここで了承を得ることができれば、STEP4へ行きましょう。
STEP4 スタッフに選んでもらう
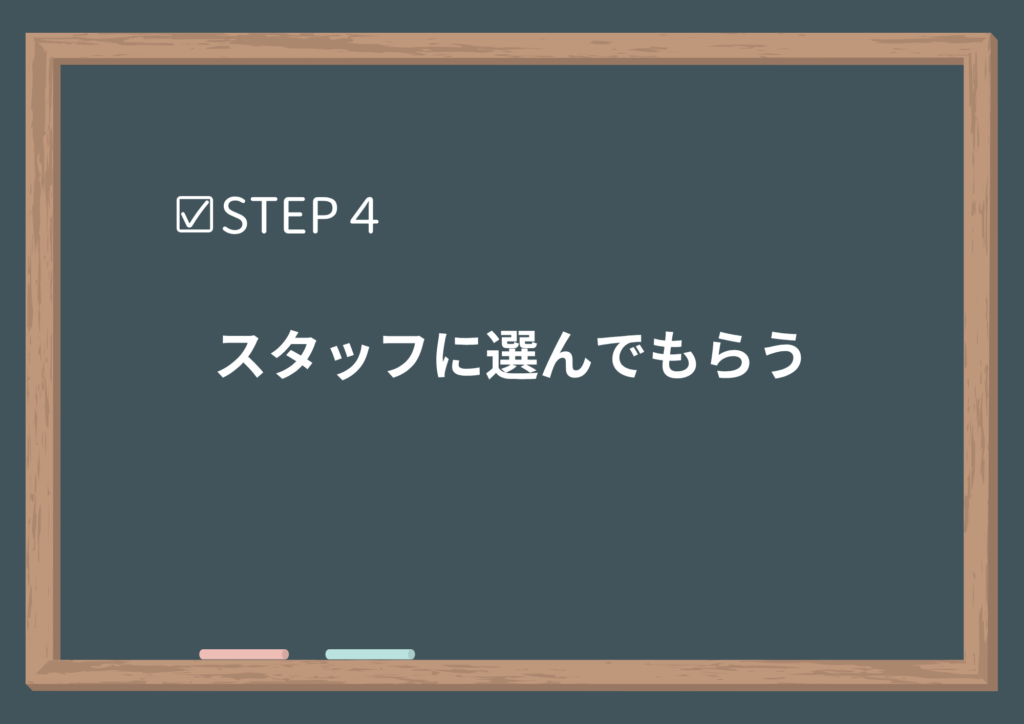
施設全体に専門チームを公表し、スタッフを集めます。
メンバーはこちらで全て決めるより、自ら選ぶことで、主体性が育ちます。
「どんな活動をするのですか?」と質問されることもあります。その場合は、「活動内容は自分たちで決めていく」と伝えましょう。※流石に認知症チームが介護技術をすることはなしです。(笑)
結果次第で「このメンバーで大丈夫かな?」と感じてしまうこともあるでしょう。でもそれでいいのです。仲良し小好しが集まった場合でも、最終的には成果をあげてくれればいいのですから。
入りたいチームがない、悩んでいるスタッフに関しては、介護リーダーがそのスタッフの“強み”を見つけて助言します。
「認知症の〇〇様の対応が上手だから認知症ケアが向いていると思いますよ」など。
事前に定員を決めておきましょう。施設のスタッフ数によって定員は変わってきます。目安として、1チーム3名ほどがいいでしょう。多すぎるとミーティング時に集まりにくいです。また、全員役割を持つことが大切なので多すぎると何もしないスタッフが出てきてしまいます。
定員オーバーした場合は、皆が納得する形で決めましょう。わたしは、あみだくじを行いました。(笑)
STEP5 専門チームでの活動
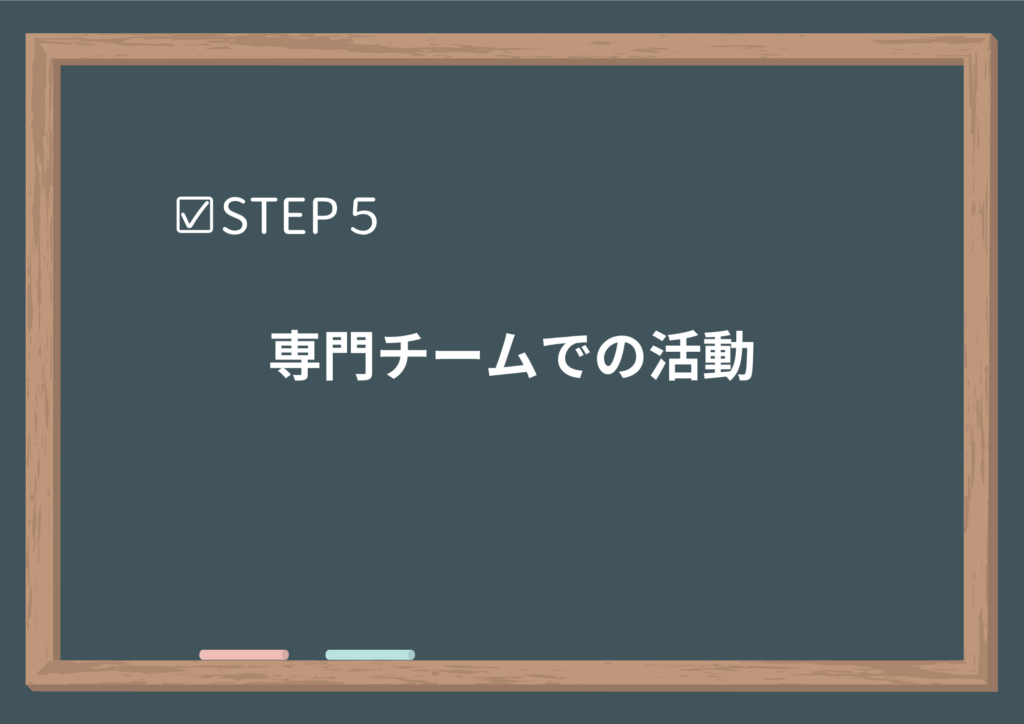
①チームリーダーを決める
チームメンバーで話し合い、リーダーを決めてもらいます。
ここでも口出しはしません。しっかり話し合って決めてもらいます。
② チームの「存在意義」をメンバーで考える
「なぜこのチームが必要なのか?」をメンバーに問い、自分たちで答えをだしてもらいます。
※あらかじめ、すべての専門チームの存在意義を明確にしているのでここで大きく方向性がずれないか注意しましょう。
③ 年間目標をメンバーで設定する
存在意義を明確にしたら、年間の具体的目標を自分たちで決めます。
※あらかじめ決めているものと違った目標になるかもしれません。ただし、最終的にチームの存在意義に合っていれば問題ありません。
④ 具体策を出して、行動にうつす
年間目標達成の為の具体的な取り組みを考えます。
いつまでに何をしていくかです。
具体的に決めましょう。
例:
介護技術チームの場合
年間目標:
①月2名を対象に、ADLに合ったケア方法を検討し全スタッフに共有する
⇒1ヶ月に一回、1週目に介護技術ミーティングを開催する。
ミーティングにて、介助方法が難しい利用者2名を決め介助方法を統一する。1ヶ月掛けて全スタッフへ周知する。
周知方法は、写真付きの介助方法をパワーポイントにまとめ利用者の居室に置く。実際にやってみてうまく出来ないスタッフは、一緒にケアに入り教える。
②3ヶ月に1回、介護技術に関する勉強会(研修)を開催する
⇒①を進める中で、ケア方法が一番難しかった介助方法の研修をおこなう。対象者は全スタッフ。時間が30分。
そもそもメンバーが介護技術について学ぶ場がない場合は、YouTubeや介護技術を教えているブログを活用するように伝えましょう。ここも、メンバー自分たちで勉強してもらいます。
介護リーダーは、各専門チームの存在意義が達成できそうか見ておく必要があります。自分がどこかのチームに所属していた場合でも、月1回チームリーダーに成果を聞くなどし他チームの動向は追っておきましょう。
STEP6 成果を振り返る
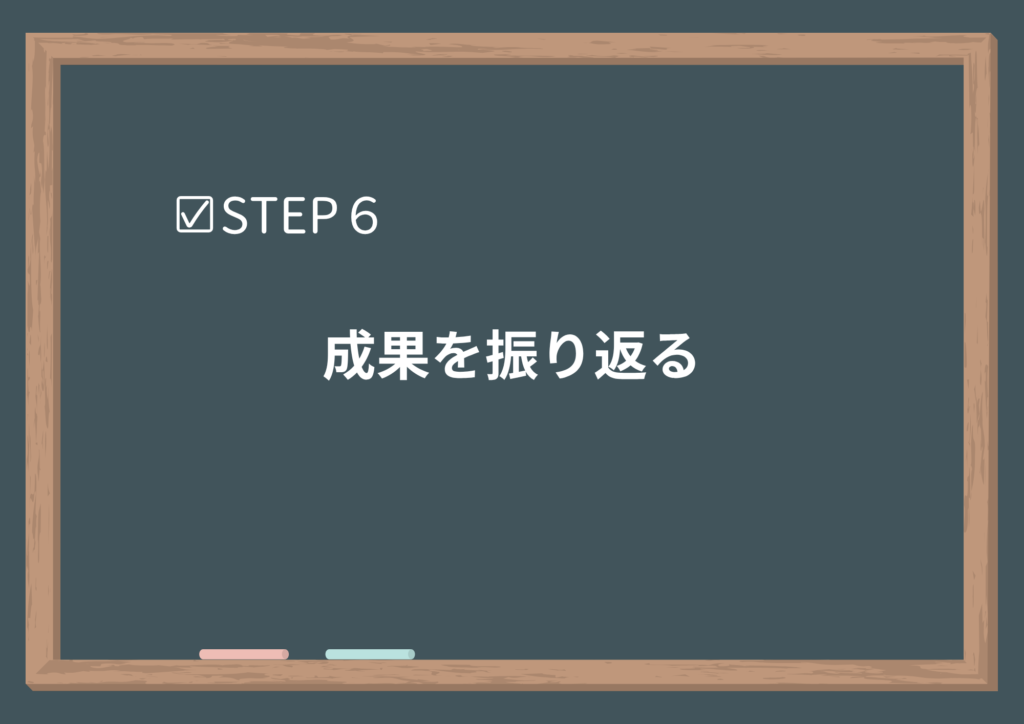
最後に、各専門チームが存在意義に合った成果を出せたか話し合いをします。
達成したチーム、そうでもないチームに分かれるでしょう。
ただ、一年で施設全体に専門性が浸透することはありません。これを来年、再来年と続けていくことが大切です。
わたしは3年続けました。1年目につくった土台をもとに2年目にブラッシュアップさせ3年目によりブラッシュアップしていきました。
まとめ
いかがでしたか?
これが、スタッフが自ら判断し行動しながら、現場全体に専門性を波及させる方法です。
専門チームづくりの本質は、「現場の課題を解決するために目的を決め達成すること」です。
チームを立ち上げ、解体し、成果を振り返る。
この一連のプロセスを通して、スタッフ一人ひとりが「自分たちの行動が施設を変えていく」実感を持てるようになります。
それこそが、“なんとなくの介護”から“根拠ある介護”へと変わる第一歩です。
【介護リーダー必見】「リーダーの役割がわからない」「言われたことしかできていない」と悩んでいるリーダー向けです▼
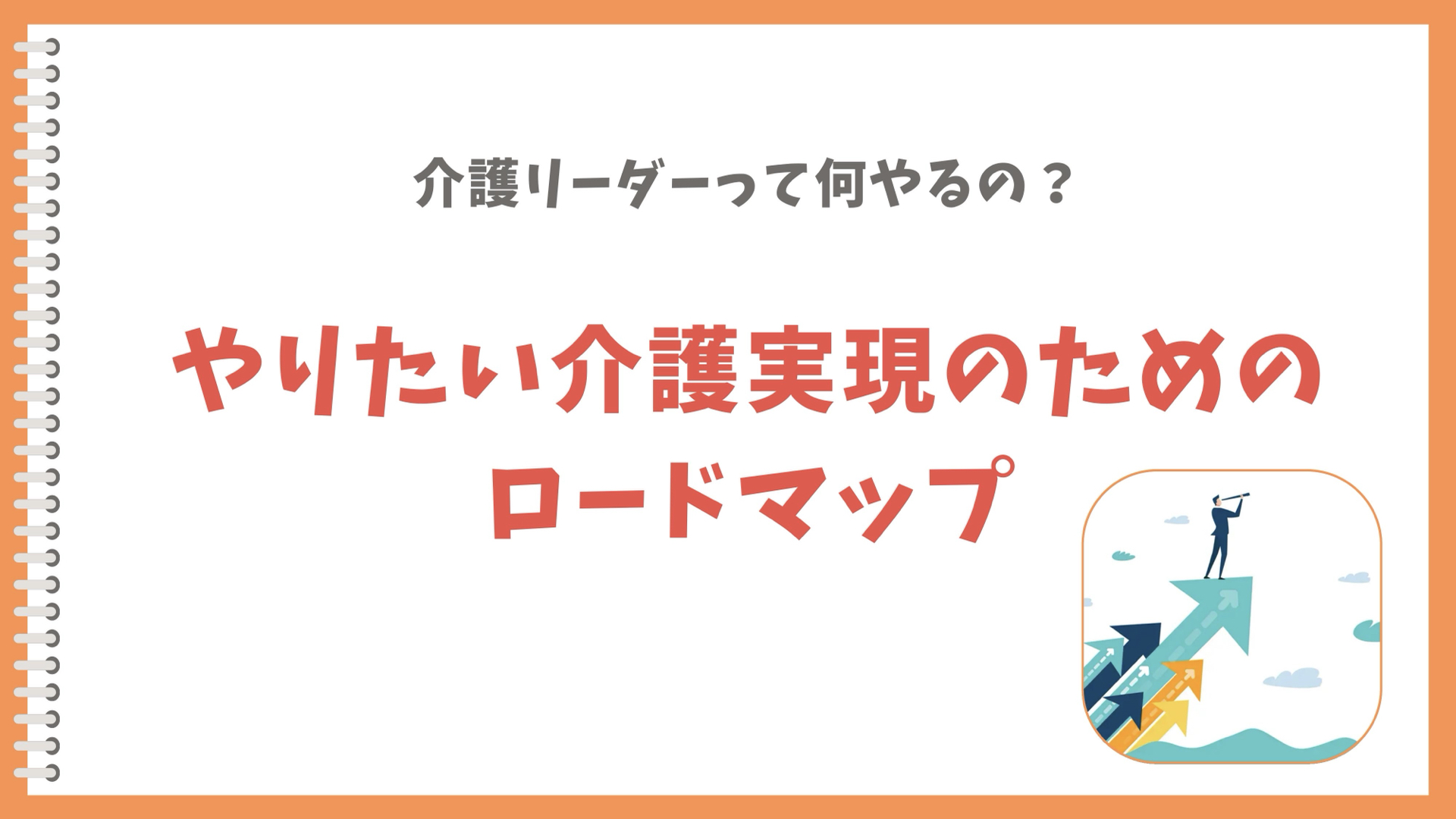 【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
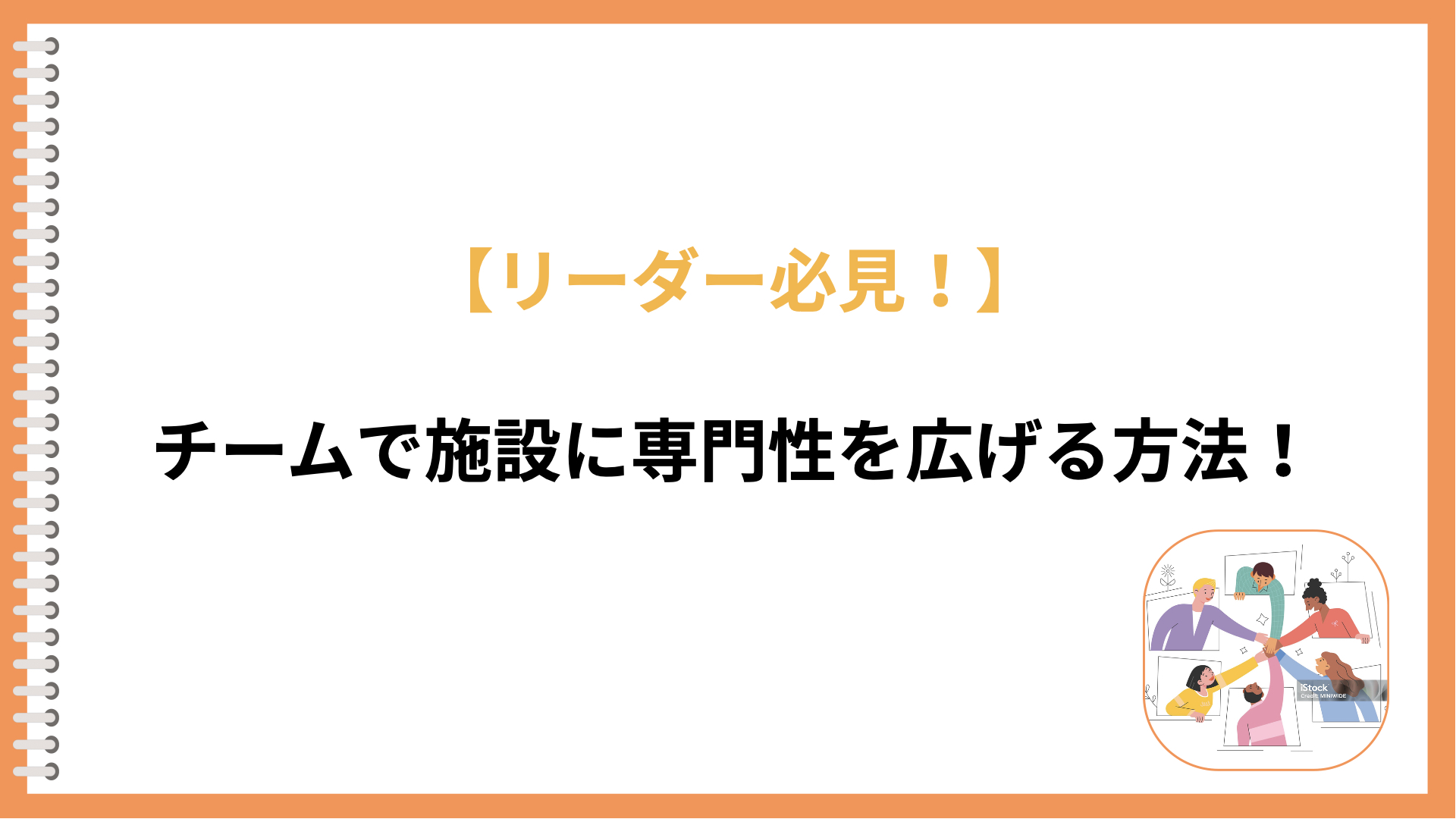
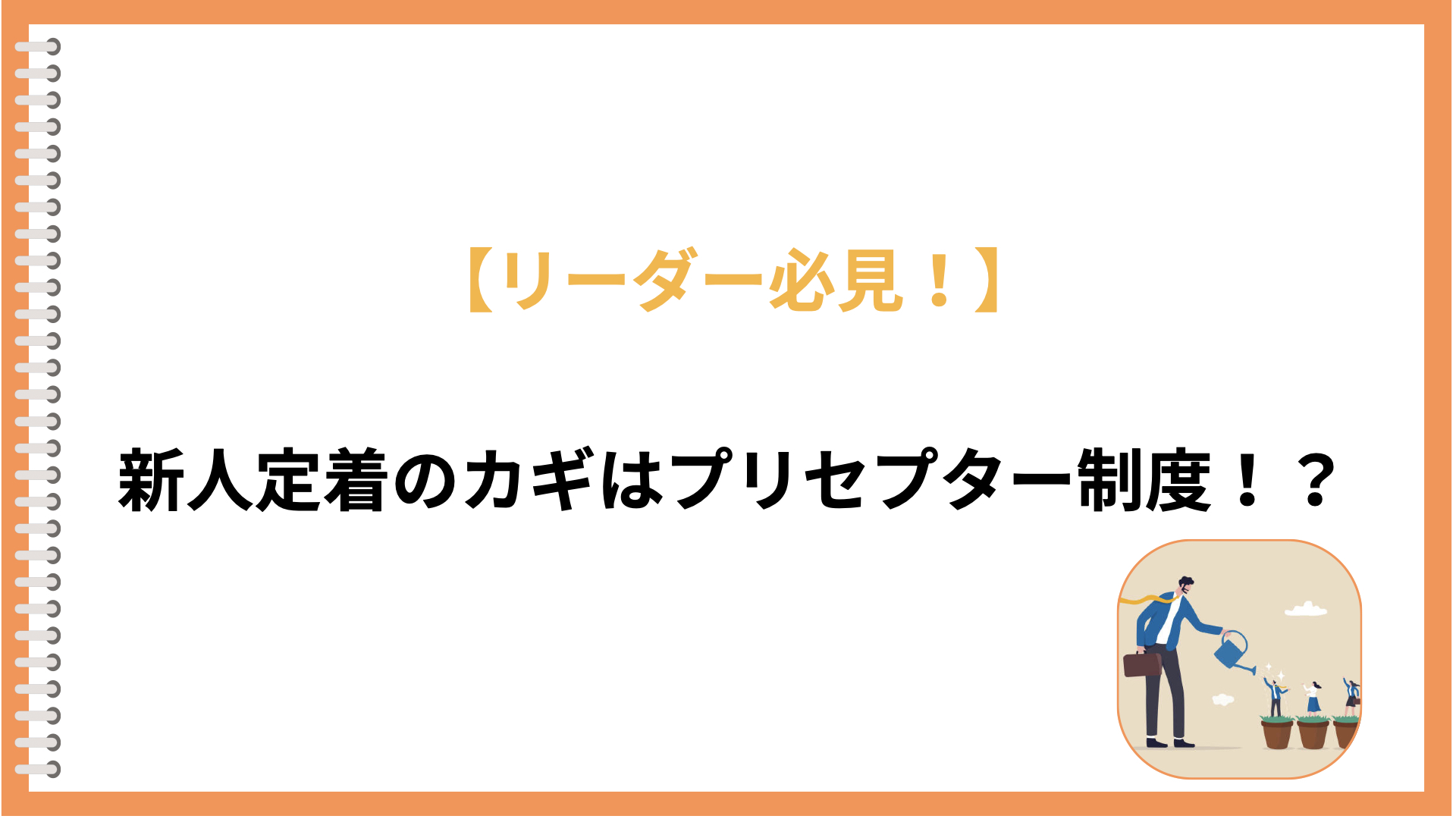


コメント