「〇〇さんはもう寝たきりだから」「歩くのは無理ですよ」
そんな言葉が、いつの間にか現場の“共通認識”になっていませんか。
実は、寝たきりの方でも「今までの生活」が実現できれば復活する可能性があります。
※「今までの生活」とは??
排泄はトイレ・入浴は個浴・食事は自分で食べる生活のこと。
トイレで排泄できる方が時間短縮のためベッド上でおむつ交換させられたり、一人で食事できる方が食事介助させる生活はNG。
何十年も当たり前に行ってきた生活を取り戻すことができれば人は元気になり意欲が出ていきます。
例えば、トイレの便座に座るからこそ重力が働き、お通じが出る。そのことによってお腹が減って食事が進む。エネルギーが蓄えられ、元気になる。元気になると、「○○がしたい」と前向きな発言が増えます。
わたしは老衰のため、看取り期に入ったと判断された100歳の女性を1年で「食事全介助から自分で食事をとり、ベッド上でのおむつ交換からトイレにいく」レベルまでADLを回復させた経験があります。
この記事では、「寝たきりから復活した高齢者のケアプロセス」と「介護リーダーとしてどう関わったのか」をご説明します。
この記事の内容を実践することによって、「一度寝たきりになったら、状態は回復しない」ではなく「まだやれることがある」と考えを改めることができます。また、成功体験が職員の意識を変え、施設の方向性が変わっていくことを実感できます。
寝たきり状態からの「復活」を本気で目指すということ

「食事や水分量がこのまま減り続ければ、老衰で亡くなるかもしれません」
そんな言葉とともに退院された100歳の女性。痛みと絶望に包まれたその姿に、施設全体が「そんなに長くないか。」という雰囲気でした。
ただ、わたしだけ「まだ生きられるかもしれない」と感じていました。
なぜか?それは「病院での生活が合わなかった」だけではないかと思ったからです。
病院ではベッド上での生活。外に出ることもしていない。
施設で日々刺激のある生活を作っていけば、本人の頑張り次第ではあるが「100歳のばあちゃん復活!!」が実現するのではないかと本気で思っていました。
現場でこの“復活”を支えたのは、明確なゴール設定と、一歩ずつのケアプロセスです。
STEP0 最初にすべきは「ゴールの共有」
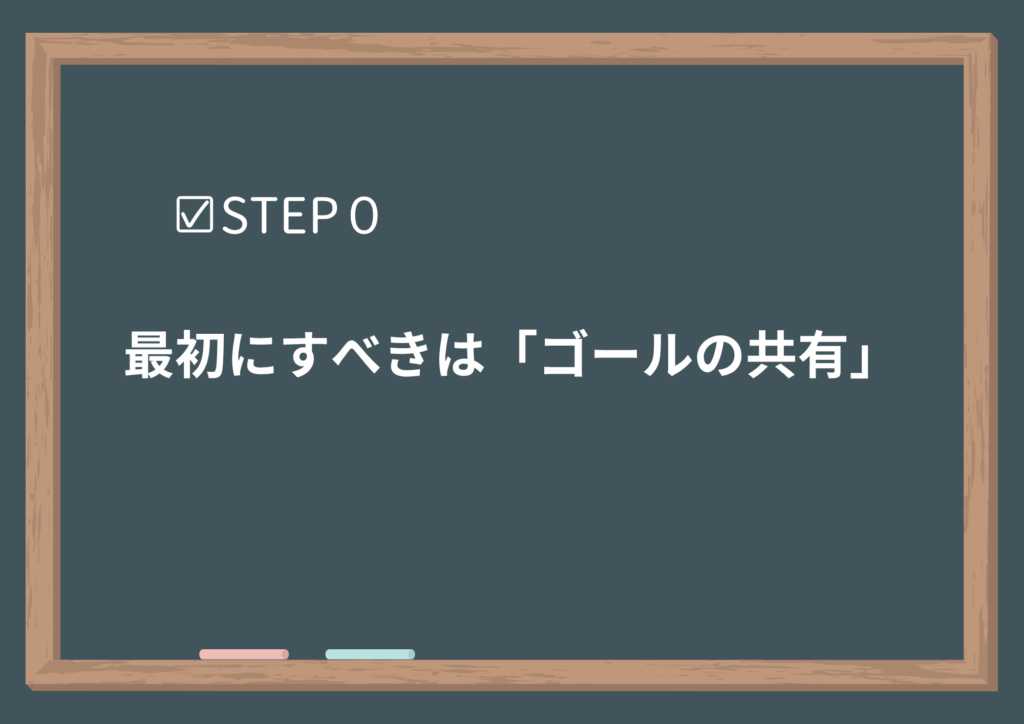
まず行ったのは、ご家族・ケアマネジャー・医師・看護師・介護職(リーダーと居室担当者)で生活のゴールを設定することです。※医師はその場にいなかったので看護師から医師に共有してもらいました。本人は状態が悪いため参加できず。
わたしは介護リーダーとして自分のやりたい介護・やりたくない介護があります。そこを軸に3大介護のそれぞれの目標を共有しました。
- 食事:椅子に座って自分で食べる
- 排泄:トイレで行う
- 入浴:個浴に入る
もちろん、周りの反応は今ひとつ。ご家族から「本当に可能ですか。」と聞かれました。
目標が達成できるかはわからなかったが、今のままの生活(ベッド上)を続けるか、少しでも回復する可能性を信じて前に進むか。どちらが良いか最終判断はご家族に委ねました。
「また母とお話がしたいです。」
方向性は決まりました。ここから、リーダーと居室担当者が中心となって動いていきます。
介護リーダーとして自分のやりたい介護・やりたくない介護が決まっていない方向けです▼
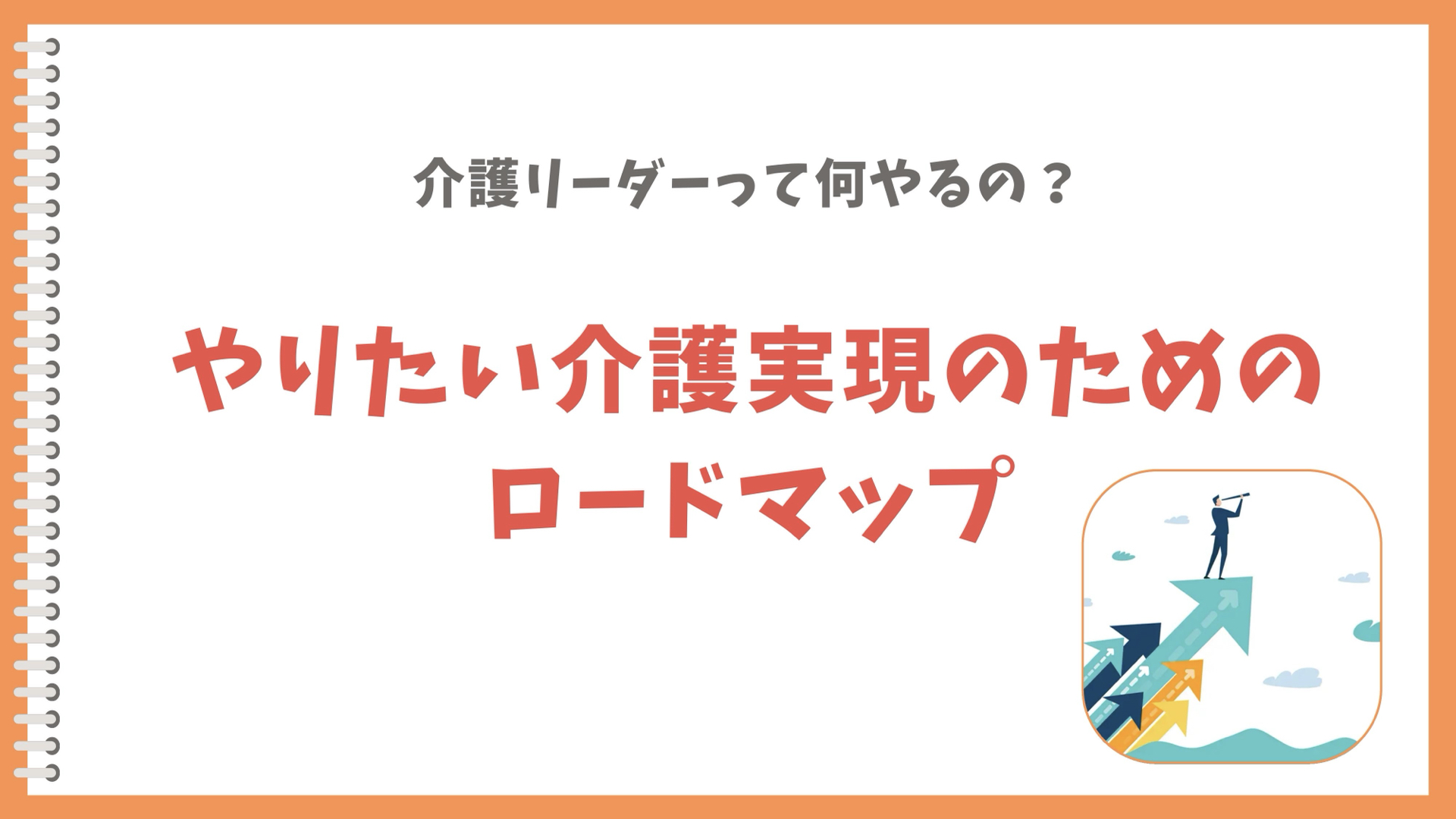 【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
STEP1 ベッド上で食事をする
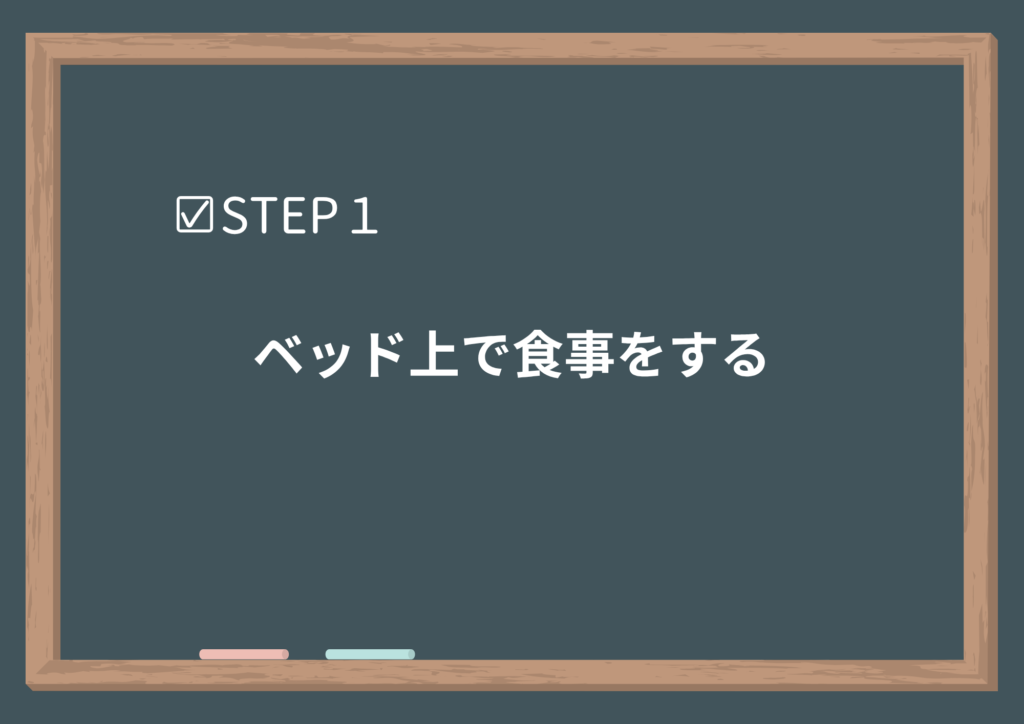
寝たきり状態から始めるには、食べること=生きるエネルギーの補給と捉え、まずはベッド上での食事介助を丁寧に行いました。
血圧の急変を避けるため、食事前後にはフルバイタルを看護師と連携して確認。
頭のギャッジアップ操作でさえ、全身に痛みを感じます。まずは30度から始めていきます。
身体と相談しながら、角度を少しずつあげます。最終的には90度近くまで目指します。
ベッド上での姿勢が悪いと誤嚥リスクが高くなるので正しい姿勢を作ってください
1.身体を上方移乗する
2.足・頭の順でギャッジアップ
3.顎を引く。目安:顎と鎖骨の距離は指4本分
4.足底にクッションを置く
1~2口の高カロリーゼリーや飲み物を摂るところからスタート。
※離床せず運動をしていないので食事量が一気に増えることはありません。ちょっとずつ増やしていきましょう。
すると徐々にお通じが出るようになります。「食べて、出す」の流れが出来てきます。
1.食事・水分量(何口)と頭部ギャッジアップは何度か、本人の様子を記録に残すことを現場に発信。
2.記録などをもとに、リーダーと居室担当者で1週間に1回振り返りを行う。
次のステップへ行く目安として、
①頭部ギャッジアップが90度ほどでも痛みが出ていないか。
②ギャッジアップによるバイタルの変化は許容範囲か。(看護師と連携)
③3日に1回お通じが出ているか。(看護師と連携)
STEP2 リクライニング車椅子で食事をする
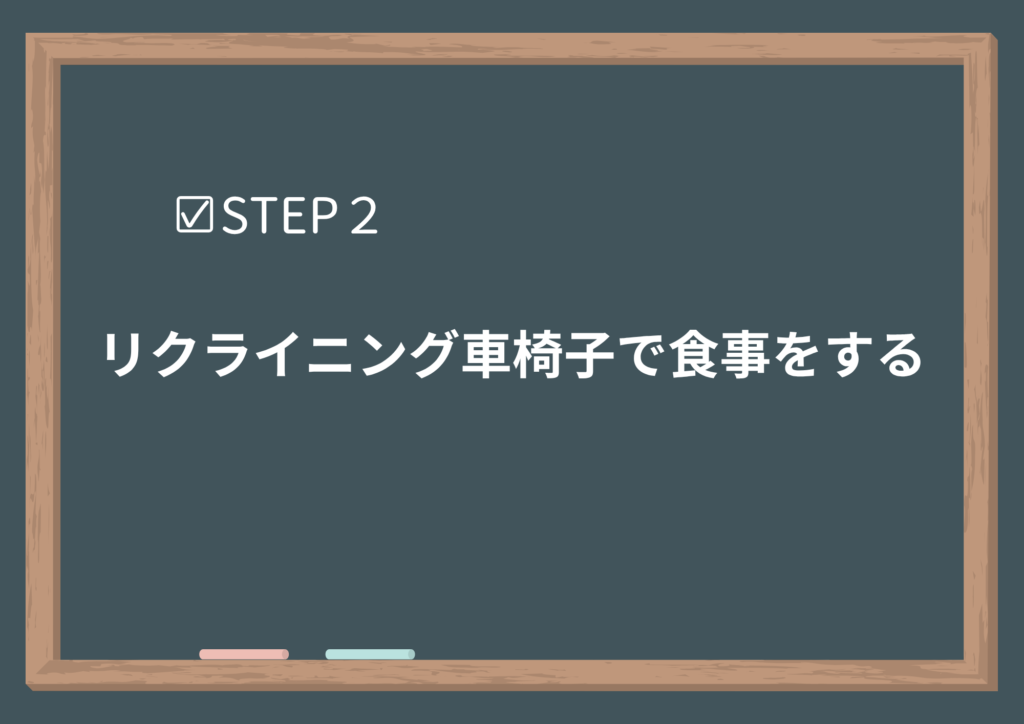
ベッドの頭部ギャッジアップをしても痛みはない様子。身体が徐々に慣れてきている。
食事は完食できるほどではないが、お通じがすこしずつコンスタントに出るようになった。
次のステップに進みます。
リクライニング車椅子へ移動し居室内での食事を開始します。
居室で食べる理由は急変時すぐベッドに横になる等、対応がしやすいためです。
移乗時は足に全く力が入りません。ただ、毎日のルーティンに組み込むことで、立つ=足に力を入れるを本能的におこなっているので自然に体力を戻す支援となります。
食事前後はフルバイタルを看護師と連携して確認。
昼食前は息抜きにお外へ。日光を浴びたり風に当たったりし、季節を感じてもらいます。
1.リクライニング車椅子を準備する。ケアマネジャーに依頼。
2.食事・水分量(何口)と移乗時足は動いたか、本人の様子を記録に残すことを現場に発信。
※一度発信しているので、改めて言わなくても記録に残してくれている可能性がある。
3.記録などをもとに、リーダーと居室担当者で1週間に1回振り返りを行う。
次のステップへ行く目安として、
①リクライニング車椅子での食事によるバイタルの変化は許容範囲か。(看護師と連携)
②3日に1回お通じが出ているか。(看護師と連携)
STEP3 機械浴で入浴をする
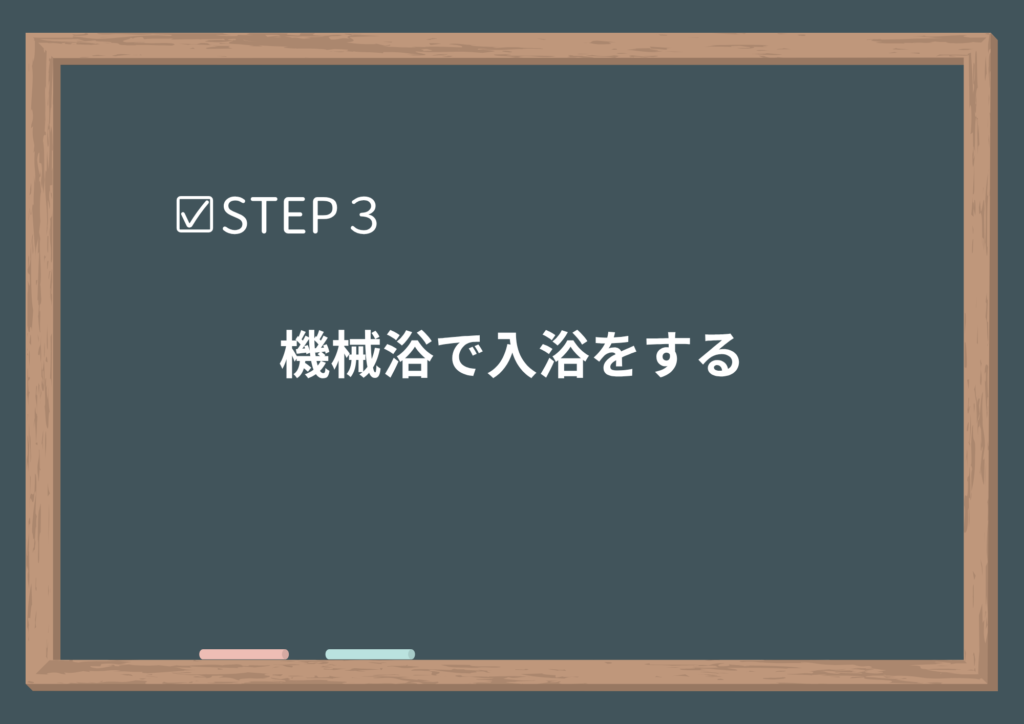
移乗後もバイタルが大きく変動することなかったため、
医師・看護師の許可を得て、機械浴による入浴を開始します。
週2回の入浴でリフレッシュしてもらいます。
入浴前後にフルバイタルを看護師と連携して確認。
入浴をすることにより、疲労からか夜間の睡眠時間が伸びました。
日中帯に外出をしてから食事をする。そして入浴をすることによって活動量が増える。
規則正しい生活になってきました。
1.どこまで自分でできるのかADLを記録に残すことを現場に発信。洗髪、洗体、洗顔など。
2.記録などをもとに、リーダーと居室担当者で2週間に1回振り返りを行う。
STEP4と同時並行で行う。
STEP4 ダイニングで食事をする
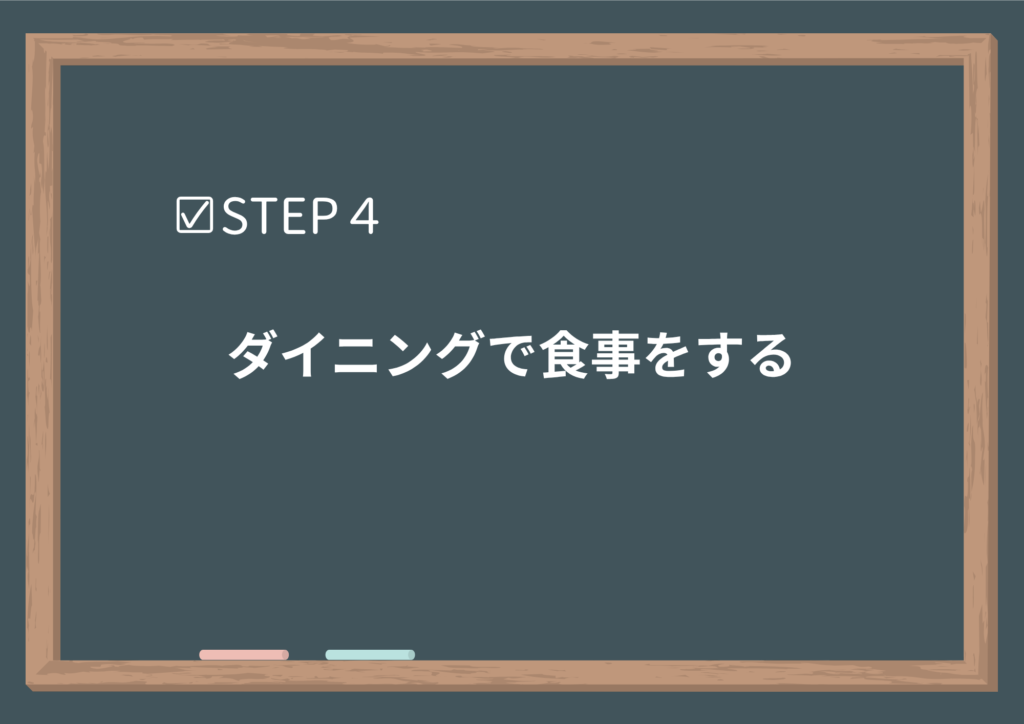
バイタルが安定してきたことにより、医師からダイニングでの食事可能と許可がおります。
まだこのときはリクライニング車椅子。疲労時や急変時、チルト(車椅子の座面と背もたれを一体的に後方へ傾けること)するためです。
他の利用者との挨拶や会話が食欲を刺激し、自分でスプーンを持って食べようとする姿勢が見られました。
ただスプーンは持てるが口まで運ぶことができず。スプーンを持った手を下からスタッフが支え、口元まで運ぶことを繰り返します。味覚は他人に食べさせてもらうより自分で食べたほうがおいしいと感じます。少しでも食事量を増やしてもらうため、「自分で食べている」を感じられる介助を行いましょう。
食事介助の目安:
・食事時間:約30〜40分
・最初の10分は自分でスプーンを持ってスタッフが下から支える
・残りはスタッフが全介助
1.食事・水分量(何口)と移乗時足は動いたか、本人の様子を記録に残すことを現場に発信。
2.記録などをもとに、リーダーと居室担当者で1週間に1回振り返りを行う。
次のステップに行く目安として、
①座位は安定しているか。移乗時のベッド上での座位姿勢にて判断する。
②急変するリスクはあるのか。(看護師と連携)
STEP5 椅子で食事をする
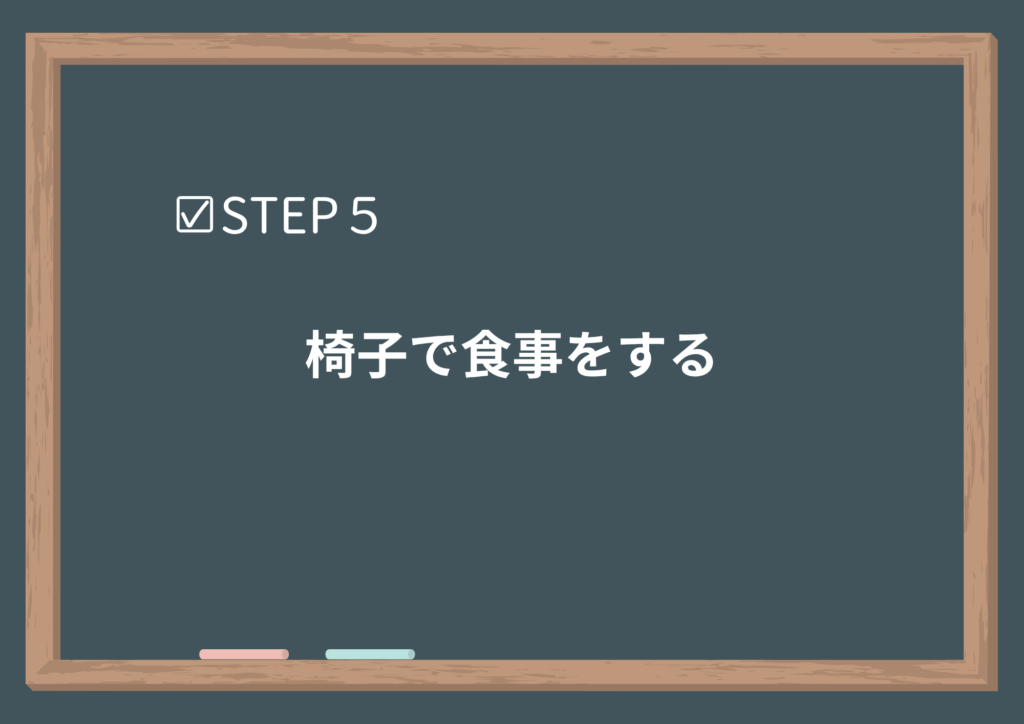
医師の指示を得て、椅子に座っての食事を行います。
急変時は居室のベッドへ急ぎで戻ることが条件。
食事量は全体の半分ぐらいで5口ほどしか自分で食べることはできなかったが、椅子に座り食事ができた。
座位が保持できている。
椅子に座って自分で食べるという目標達成‼️
1.目標が達成されたことをご家族に伝える。
2.また、施設内でも発信。成功体験を共有する。
STEP6 トイレで排泄をする
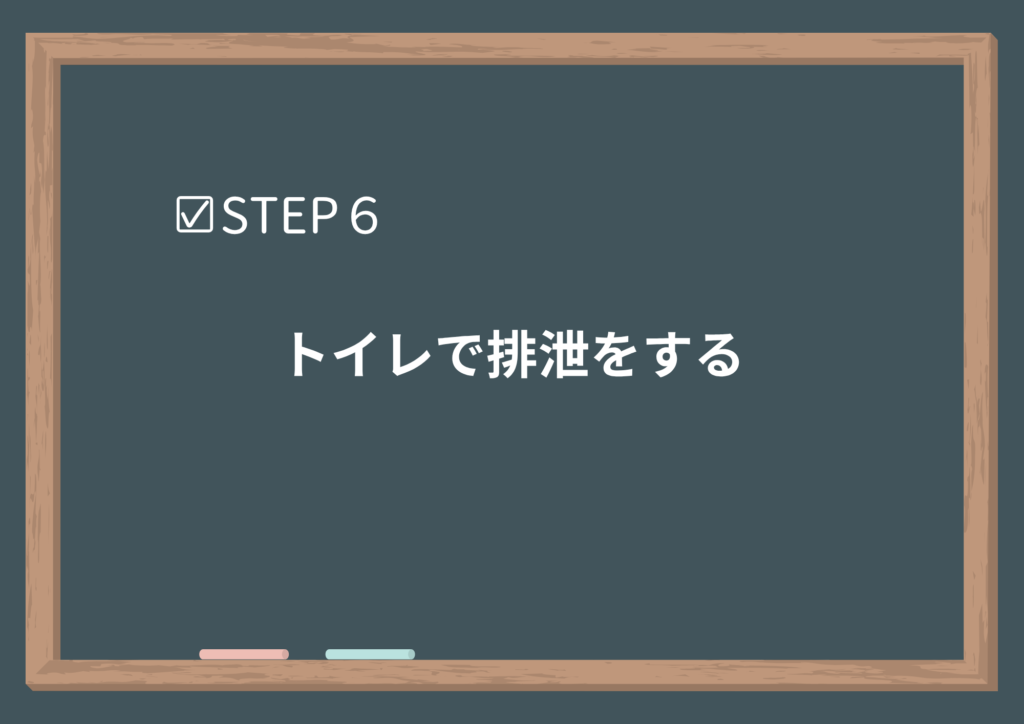
食事姿勢の安定により、座位保持ができるようになった段階で、トイレでの排泄支援がスタートします。
座位を取ることによって体幹が鍛えられます。
はじめは、2人介助で便座に座ってもらい、重力を活用して排便がしやすい体勢を作ります。
常に2名スタッフを確保できない場合でも、1日1回は最低でも便座に座るようにしましょう。お通じは朝食後に出ることが多いので、そこに合わすことができればベストです。
排泄をトイレでするという目標達成‼️
その後座位は保持され、足は移乗を重ねることで動かせるようになったので1人介助でトイレに行けるようになりました。トイレに行く回数が増えたことによりADL(日常生活動作)の向上が早く、ベッド上での排泄ケアを拒否されるようになりました。(笑)
1.朝食後、2名介助でトイレに行くように発信
2.お通じの有無と食事量を記録に落とすように発信
3.1週間に1回記録を確認。
①お通じは出ているか?②出ている場合は、食事量は増えているかの確認
4.目標が達成されたことをご家族に伝える。
5.また、施設内でも発信。成功体験を共有する。
STEP7と同時並行で行う。
STEP7 個浴で入浴をする
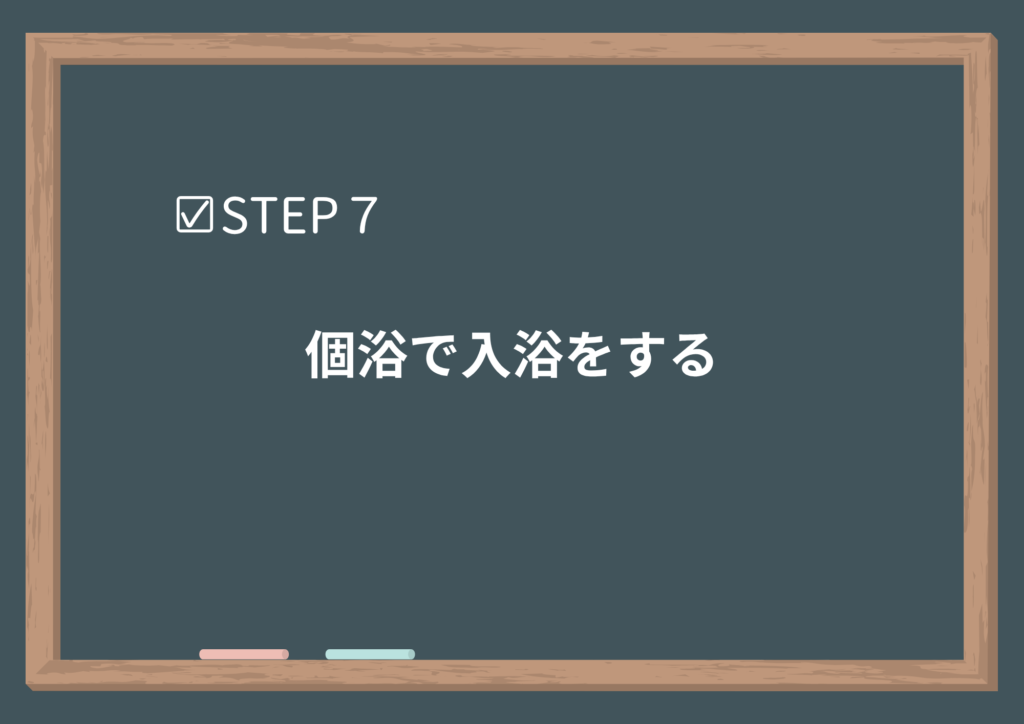
座位が保てるようになり、バイタルも安定してきたので医師の指示にて個浴の許可がでました。
浴槽のまたぎ動作と立ち上がりが課題となります。またぎはバスボードを使用すればクリア。浴槽からの立ち上がりは、スタッフ介助にてクリア。
個浴で入浴するという目標達成‼️
ご家族の希望だった「母との会話」も実現。「信じられない」と泣いて喜んでくださいました。
1.目標が達成されたことをご家族に伝える。
2.また、施設内でも発信。成功体験を共有する。
まとめ:リーダーが「できる」を信じたとき、現場が変わる
寝たきりの方を“復活”させるということは、奇跡を起こすことではありません。
人として当たり前の「今までの生活」を取り戻す支援を、チームが一つになって積み重ねた結果です。
トイレで排泄する。椅子で食事をとる。お風呂は個浴に入る。
そのどれもが、人としての尊厳と生きる意欲を引き出す行為です。
そして、それを「もう無理」と決めつけずに信じ続けたリーダーの姿勢こそが、現場を動かしました。
今回のケースが成功した要因は、本人の意欲だけではありません。
リーダーがゴールを明確にし、職員と共有し、都度振り返りをしながら小さな変化を積み重ねたこと。
その仕組みと信念が、寝たきりからの復活を支えたのです。
たとえすべての目標が達成できなくても、
「できない前提」から「できる可能性を探す前提」に変わるだけで、利用者・家族・職員、すべてにとって意味のあるケアになります。
“諦めないリーダー”の姿勢こそが、次の「復活」を生み出します。
【実践シリーズ】帰宅願望のある認知症。居心地を作っていくために介護リーダーがしたこととは?▼
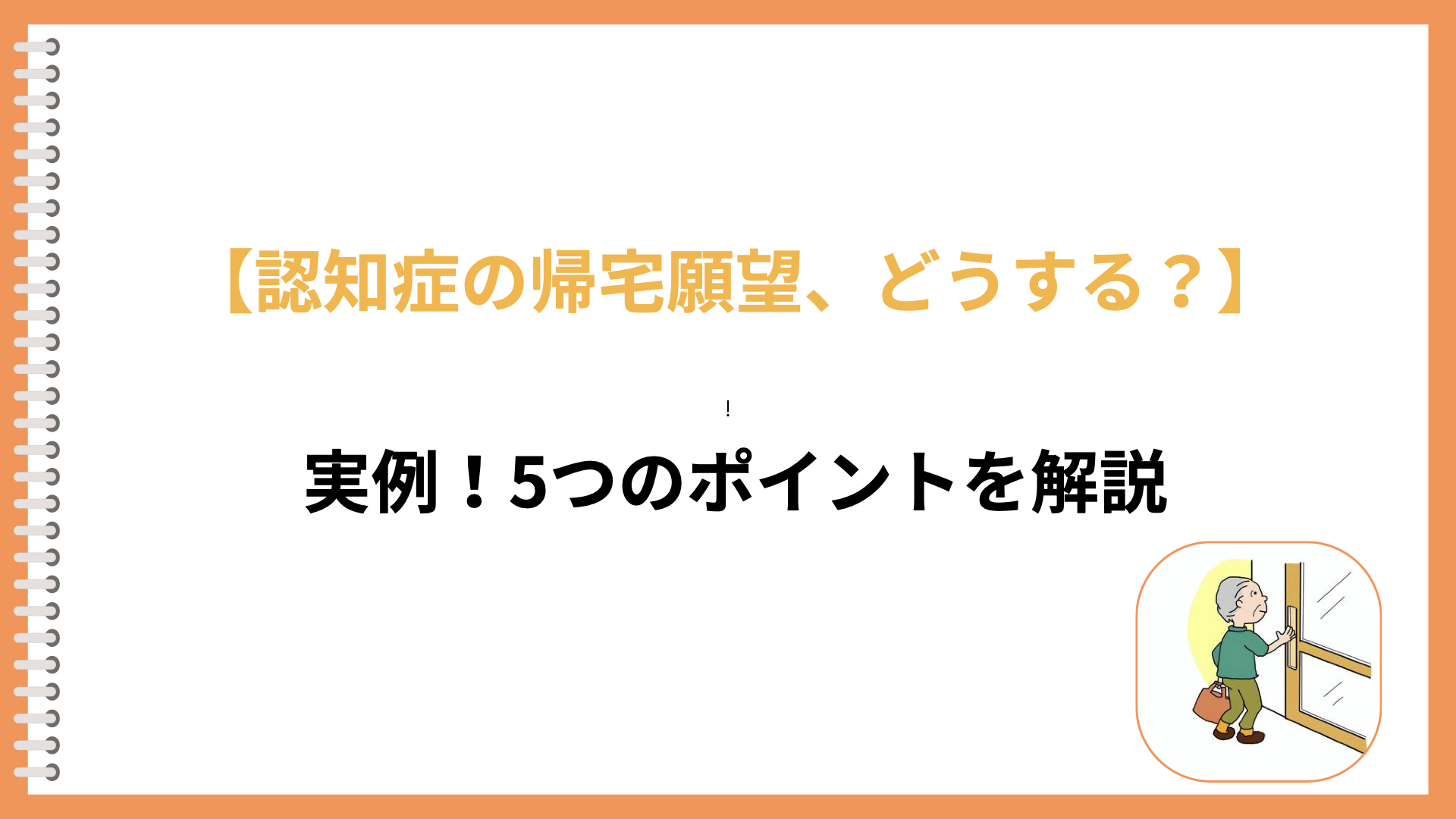 【実例】認知症の帰宅願望どうする?介護現場で実践できる居心地づくりの工夫
【実例】認知症の帰宅願望どうする?介護現場で実践できる居心地づくりの工夫
介護リーダーの悩みはコレを読めば8割解決できる!?▼
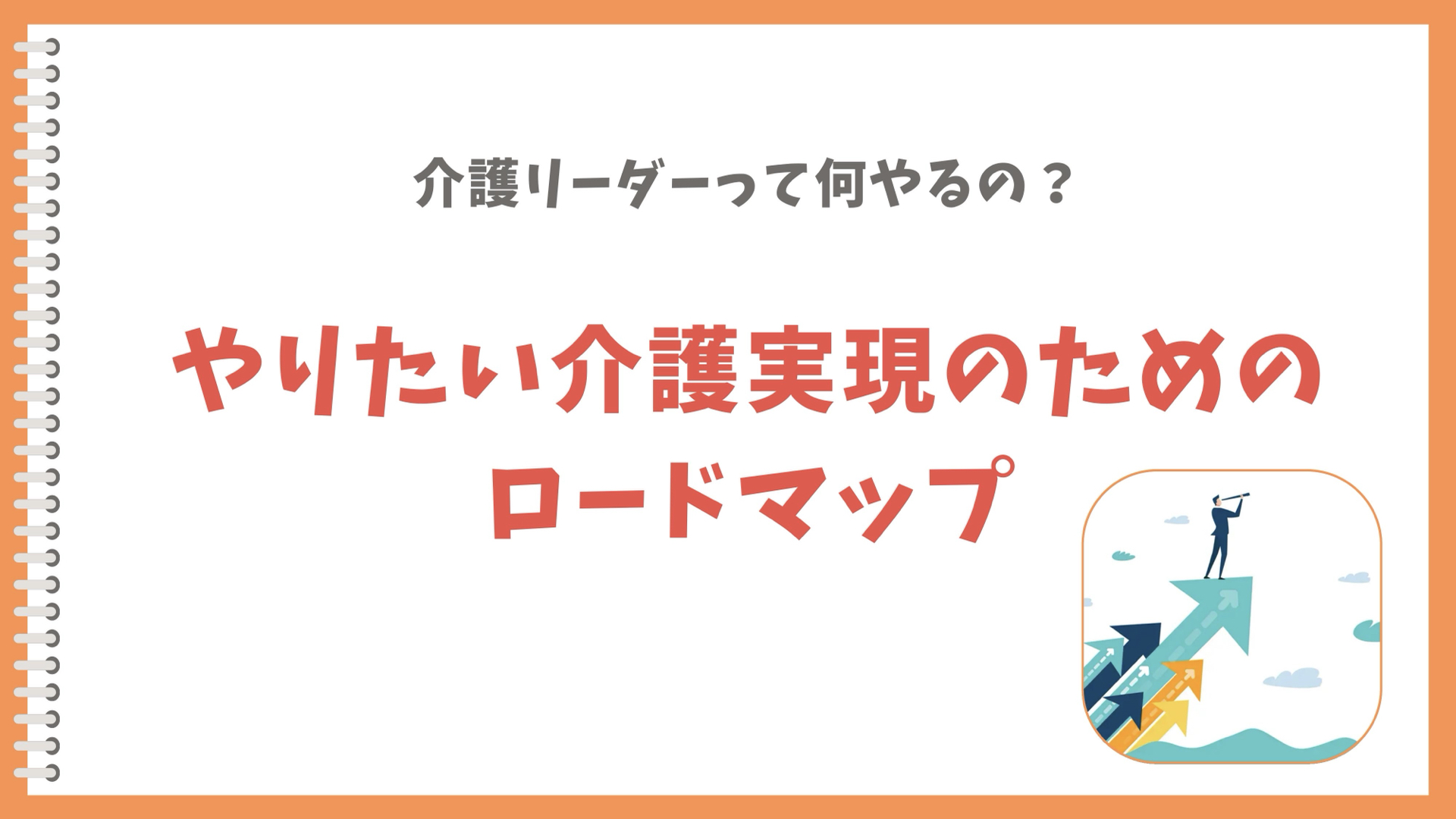 【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
【介護リーダー必見】リーダー職へのロードマップ|役割と成長のステップ
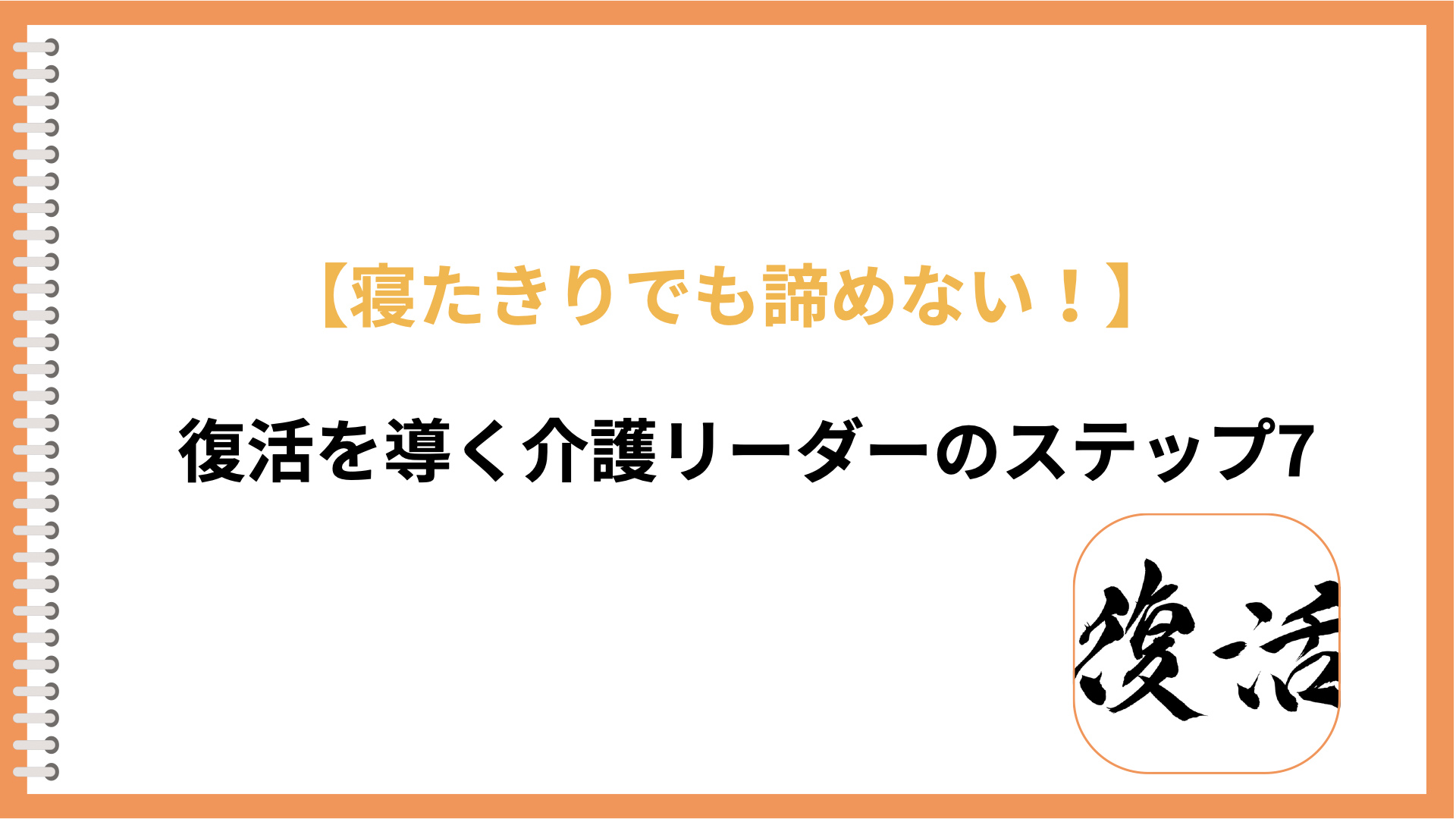
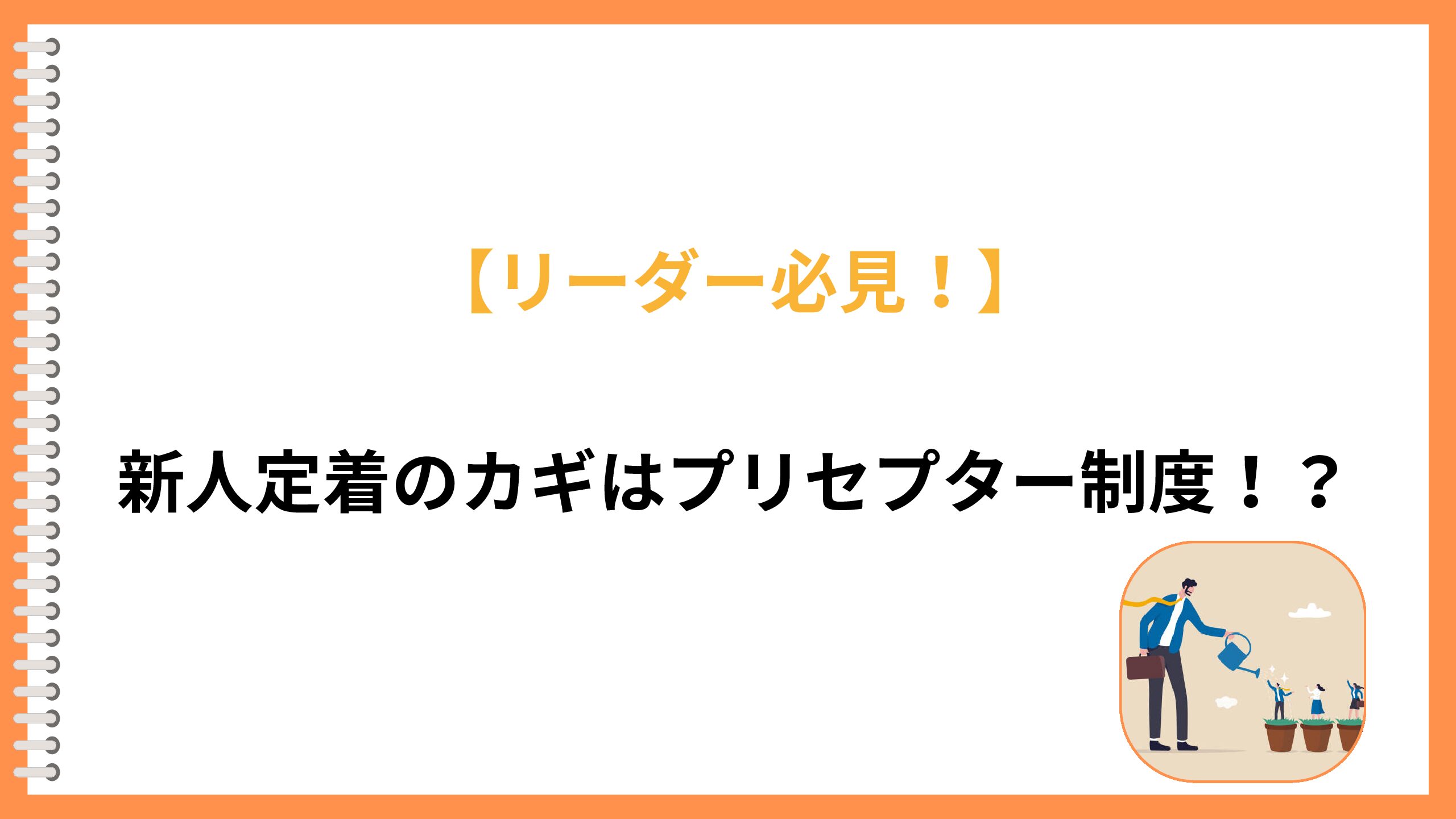
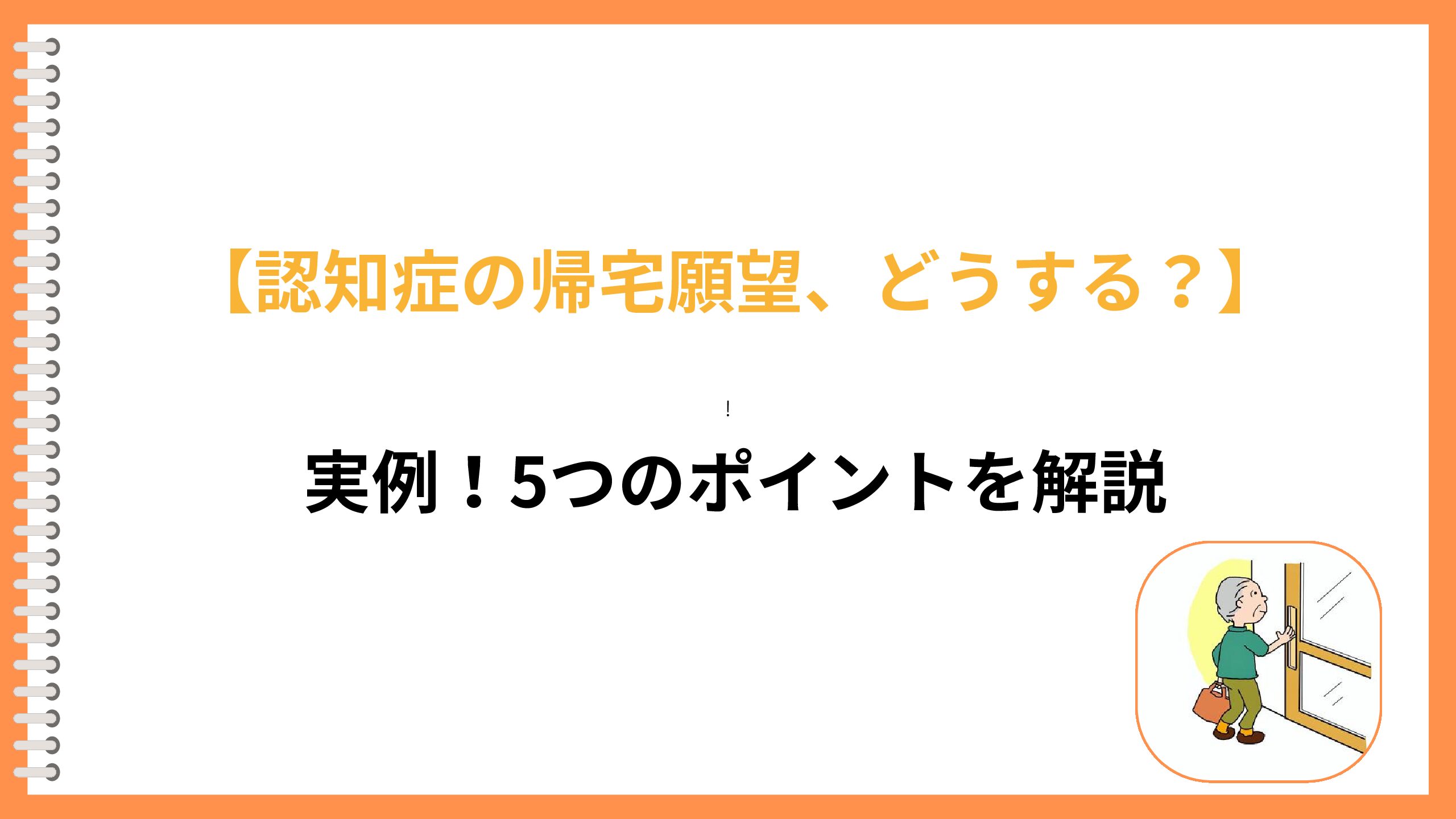
コメント