「リーダーがいるのに現場がまとまらない」「言葉はいいが行動が伴わない」──そんな悩みを抱える施設は少なくありません。その原因の多くは、介護観の不一致と、リーダーの役割や責任があいまいなことです。この記事では、住宅型有料老人ホームなどの現場で役立つ、チームリーダーの役割と責任、育成・選定のポイントについて実践的に解説します。
第1章:介護チームリーダーの役割とは?──“介護観の伝道者”としての立ち位置

チームリーダーの本質的な役割
介護現場におけるチームリーダーは、単にスタッフのまとめ役ではありません。利用者主体の介護観を現場に浸透させ、管理者がいない時間帯にも“介護の軸”を守る存在です。トッププレイヤーが明確になることで、他のスタッフの行動にも良い影響を与えます。
形だけのリーダーではダメな理由
口先では「利用者第一」と言いながら、行動が伴わないリーダーには誰もついてきません。現場では、発言と行動が一致しているかどうかが、信頼の鍵を握ります。
第2章:介護チームリーダーの選定基準とは?──育つ人・育てる人の見極め方

STEP1:リーダーの選定
リーダーに必要な5つの条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ①介護観が合っている | 利用者本位のケアを実践している |
| ②ご入居者を思いやれる | 発言と行動が一致する“生粋の人” |
| ③スタッフを思いやれる | 寄り添いと育成のバランスを持つ |
| ④「やりたい」という意志 | 本人の内発的動機がある |
| ⑤自立型人材 | 問題解決志向・原因自分論がある |
①〜③は素質、④〜⑤は育成で培える力です。
若手×ベテランの融合がカギ
| メリット | 内容 |
|---|---|
| ✅ 若手の意欲 × ベテランの知恵 | 新しい風と安定感の融合 |
| ✅ 定着率の向上 | 若手は辞めやすく、ベテランは残りやすい |
若手の意欲と、ベテランの知識・経験を融合させることで、現場にイノベーションが生まれます。ただし、固定観念に縛られすぎないよう、チーム全体のバランス調整も管理者の大事な役割です。
STEP2:リーダーの育成
リーダーの目標:「自分のやりたい介護・やりたくない介護」を現場で実現
リーダーの3つの取り組み
- リーダーのやりたい介護、やりたくない介護を現場(又はチーム)に浸透させる
- チームメンバーを1人にしない。成長をサポート
- 業務改善
1.リーダーの考えを現場、チームに浸透させる具体策
- フロア内での共有
- 申し送りでの伝達
- ミーティング・研修・面談を活用
リーダーは「やりたい介護」「やりたくない介護」を自分の言葉で語れる必要があります。その考えを、フロア・申し送り・ミーティング・研修・面談などあらゆる場面でスタッフに共有し続けることが求められます。
⚠️注意点:スタッフ主体ではなくご入居者主体で!
❌NG例:スタッフ主体
スタッフ主体のケア(例:立位困難になったらすぐパッド交換)から、利用者主体のケア(例:どうすればトイレに行けるか)への意識転換を進めましょう。利用者の困りごと→原因→対策を考える視点を、チームMTやフロアで日常的に伝えることがポイントです。
2.スタッフを1人にしない。成長をサポート
チームミーティングを毎月開催
ストレスや悩みを個人で解決させない。チームで解決する。集まれないスタッフには個別でのフォローを行いましょう。
メンバーを最後まで見る
メンバーの仕事が進んでいるのか?やり切るまでトラッキング(後追い)をする!
やり切るまで見届ける事でメンバーは責任感が芽生えます。
また、誰にも相談できず困っている人がいるかもしれません。(期限を)忘れやすいスタッフがいるかもしれません。そのスタッフの成長の為に最後まで寄り添いましょう。
指摘をする
成長に欠かせないのか指摘です。正しいことを伝えることは重要です。指摘は相手に伝わるか分からない為、めんどくさく嫌な作業です。が、指摘ができないとリーダーの目標である「自分のやりたい介護・やりたくない介護」を現場で実現することは達成しません。
3.業務改善
リーダーは仕組みの「破壊者」ではなく、「創造者」であるべきです。
◎仕組み改善の視点
- 新しい仕組みをゼロからつくる(0→1)
- 既存の仕組みをより良くする(1→2)
- 不要な仕組みをなくす(1→0)
仕組みは“足し算”ばかりでは業務が増えてしまい、こなすことでいっぱいいっぱいになりがちです。
新たに1つ増やしたら1つ減らす。業務全体の“引き算”も意識しましょう。
第3章:チームリーダーを支える管理者の役割と責任

チームリーダーに求めていることを管理者が体現する
管理者の考えをリーダーへ伝える
フロア・申し送り・ミーティング・研修・面談など、対話できる環境をつくる。
忙しくてフロアに行けていないのであれば、時間を作り一日一回はいく。や定期的に面談ができていなければ年二回行うなど仕組みをつくる。
利用者の情報を共有するミーティングには管理者は参加し、「利用者視点」と「スタッフ視点」を意識的に区別・共有しましょう。形式的な会議にならないよう、進行や議題にフィードバックを加えることも重要です。
何も言わなくてもリーダーが中心となって進めることができるようになれば、管理者の出番は終了です。
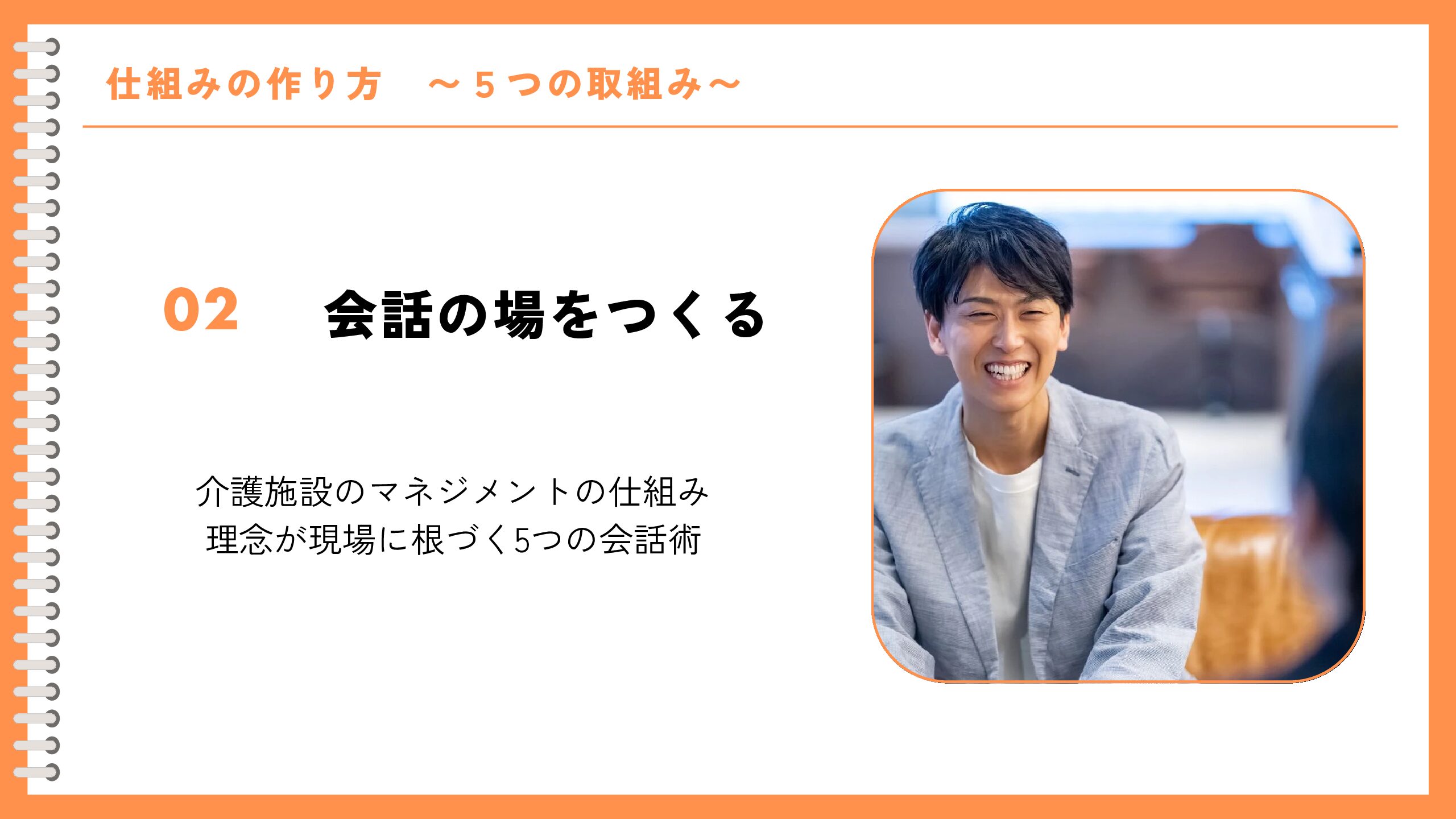 会話する場をつくる
会話する場をつくる
メンバー育成と後追いの徹底
リーダーが集まるミーティングを設ける。管理者も参加しましょう。
業務改善の話し合いなどをする場ではありますが、リーダーの困りごとを共有してもらいましょう。
リーダーは孤独を感じます。「リーダーだからしっかりしないと。」と不安や悩みを周りに打ち明けることにためらいを感じることがあるでしょう。リーダーミーティングは、悩みを打ち明ける場になるのです。
リーダーの不安や悩みごとはリーダーミーティングで、リーダーの下で働いているスタッフの不安や悩みごとはチームミーティングで話せる仕組みをつくります。
リーダーの権限ではできない業務改善を行う
現場リーダーは日々の運営やスタッフ調整、業務の効率化には大きく関われますが、組織全体に影響する大規模な業務改善や制度・体制の変更は管理者の権限でしか実行できません。リーダーから現場の声を集めて進めていきます。
例えば、全体の人員配置の再編や新たな職種の導入、シフト体制の根本的変更などは管理者の権限が必要。これには労務管理や予算調整、就業規則の変更が関わるため、リーダー単独では実施できません。
具体的には、業務を効率化するための新たな設備投資や人材の採用。人事(異動、退職)等が挙げられます。
リーダーミーティングで現場の課題を聞き、改善していきます。
【まとめ】介護チームリーダーに必要なのは“責任”と“仕組み”
介護チームリーダーは、人をまとめる立場ではなく、理念を行動で示し、現場に浸透させていく“介護観の伝道者”です。その役割と責任を果たすためには、仕組みとサポートが必要不可欠です。人を見て選び、仕組みで支える──この2本柱が、質の高い介護現場づくりに欠かせません。
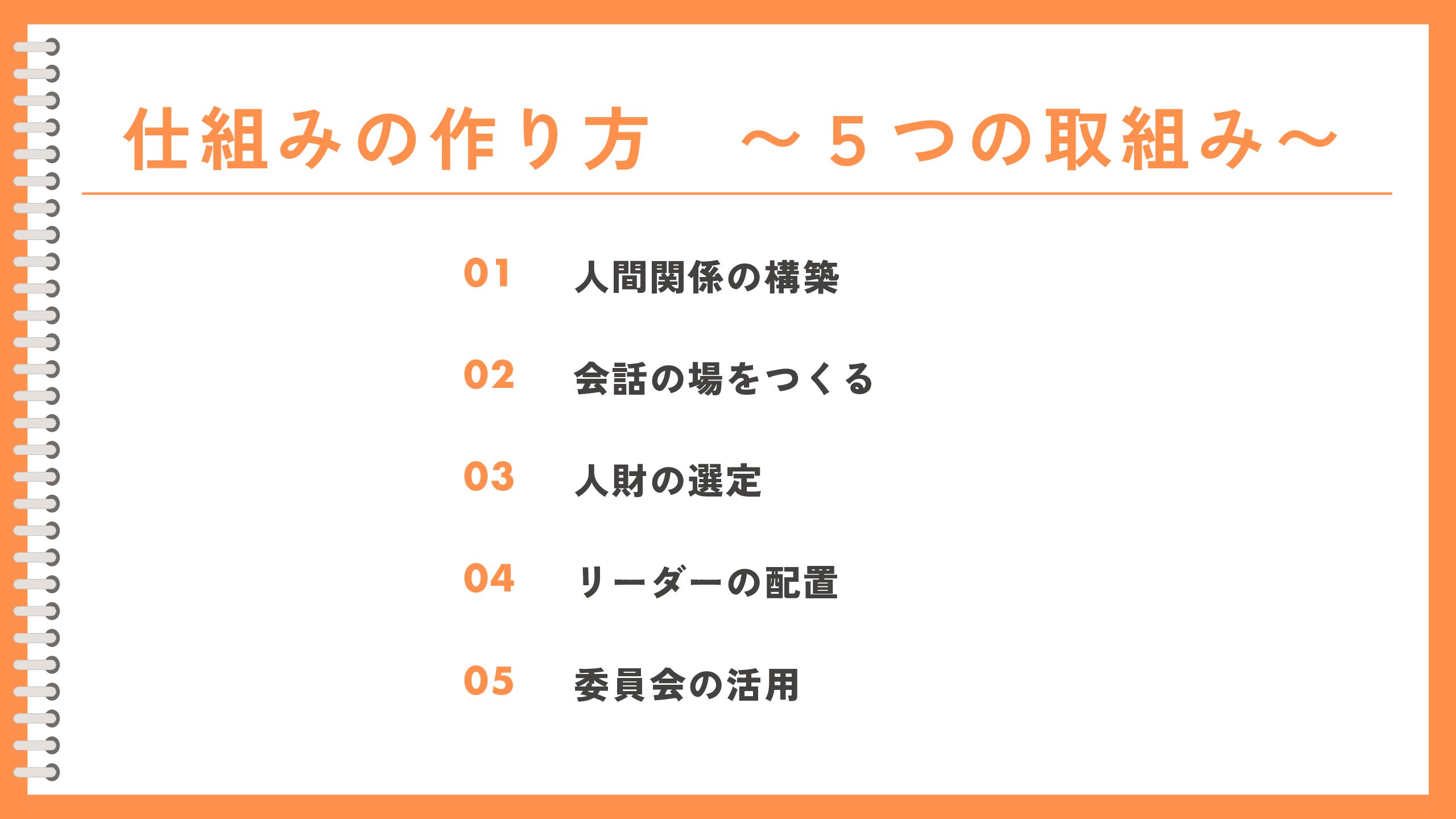 【老人ホームの仕組みの作り方】スタッフの意識を変える5つの実践とは?
【老人ホームの仕組みの作り方】スタッフの意識を変える5つの実践とは?
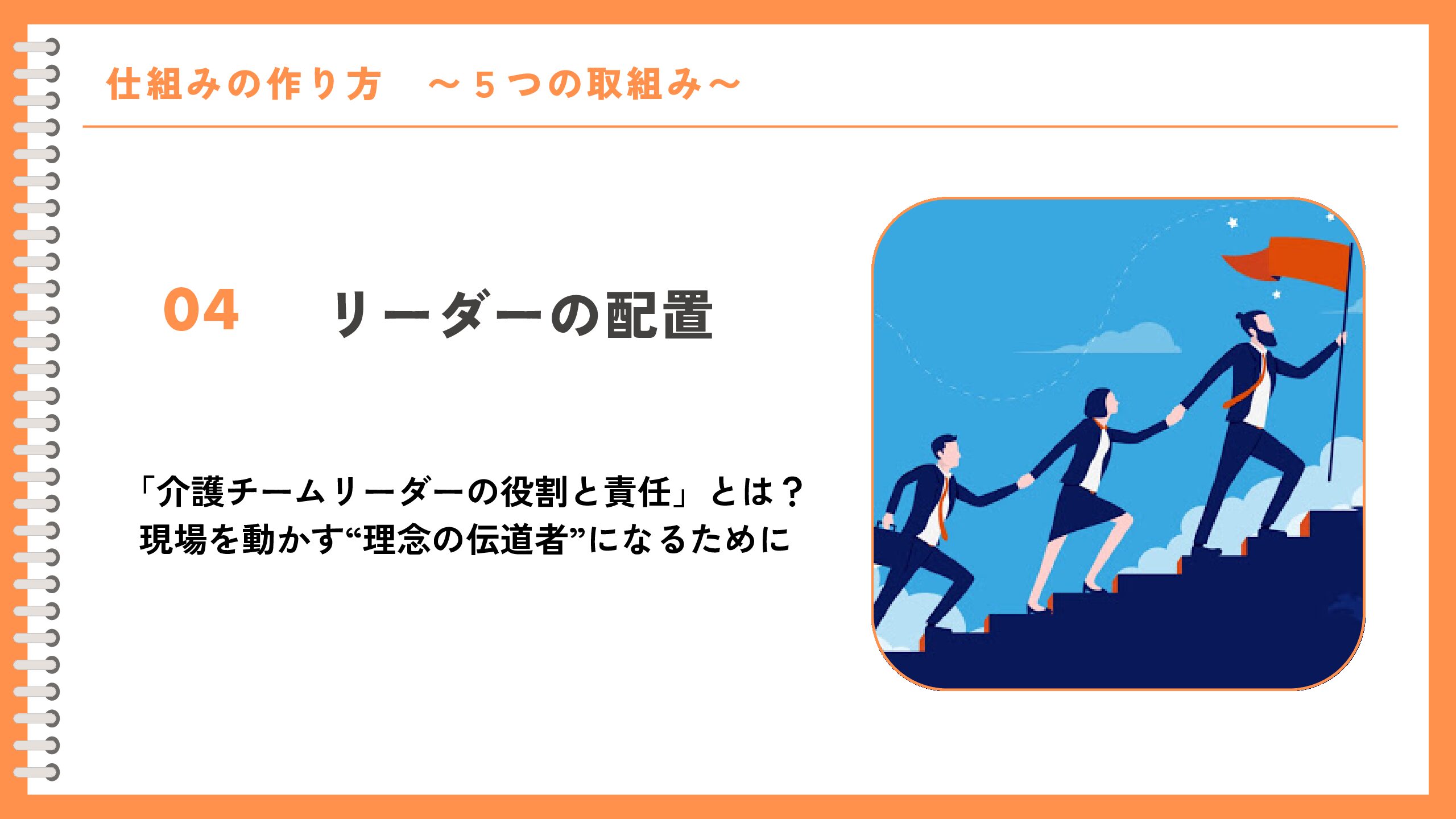
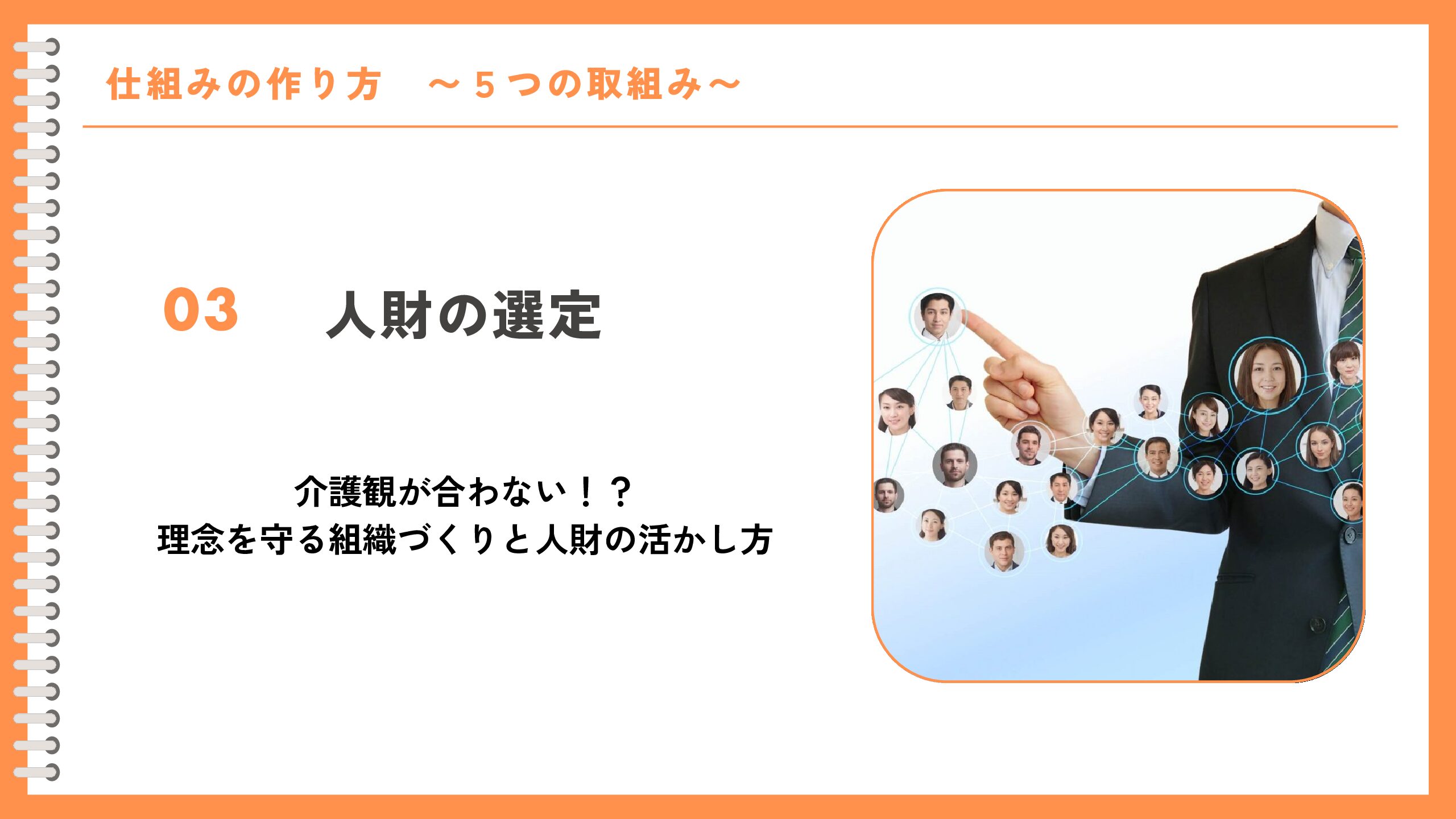
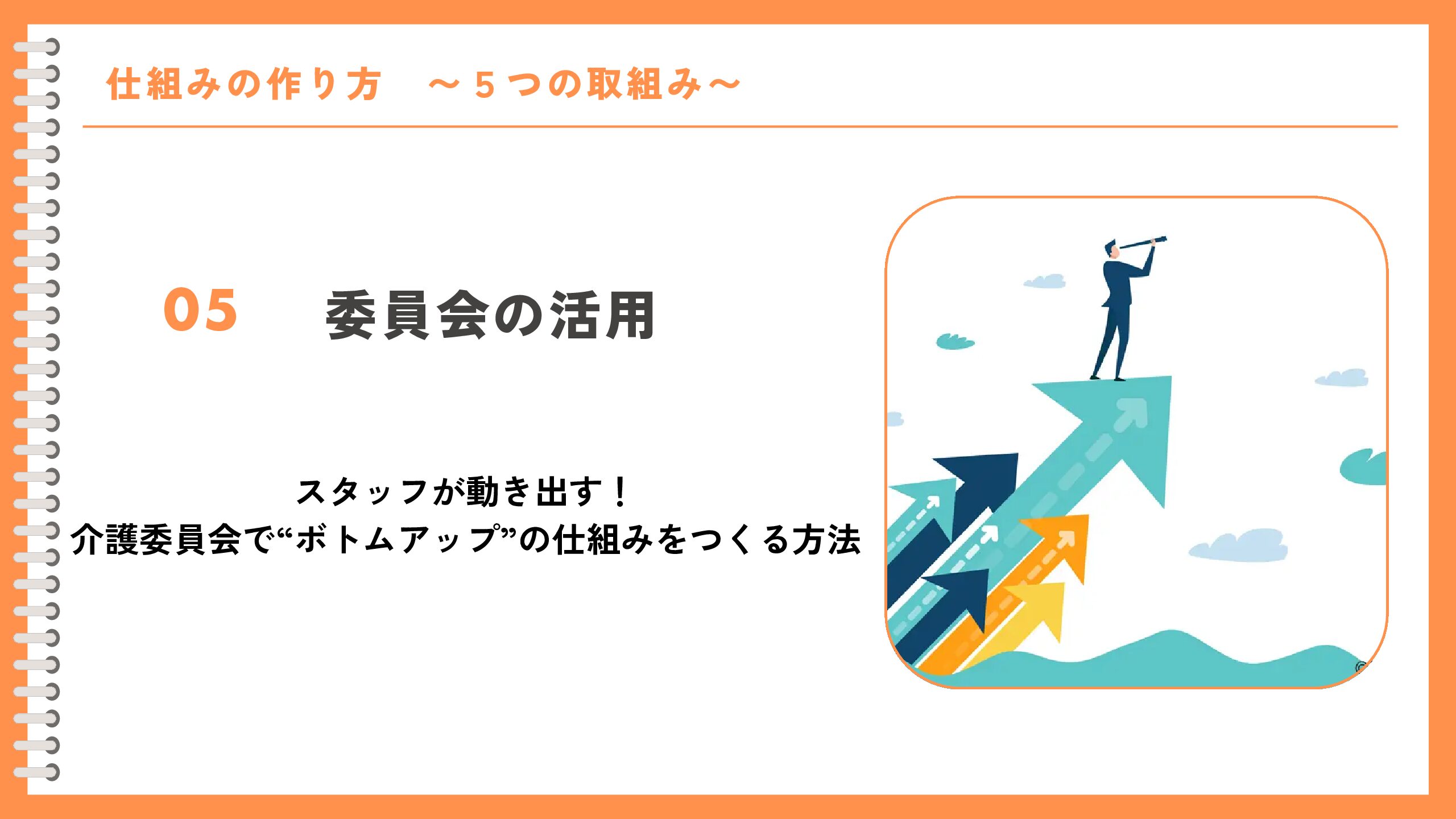
コメント