はじめに:事故が続く…どうすればいいの?
介護施設で働くみなさんの中には、「また事故が起きてしまった」「何度もご家族に謝罪するのがつらい」と感じている方も多いのではないでしょうか。事故が発生すると、報告書の作成や家族対応、他業務への影響もあり、スタッフの負担は大きくなります。
事故ゼロは理想ですが、現実的には難しいのが実情です。そこで重要なのが、「事故を繰り返さない仕組みづくり」と「施設全体でのチームワーク」です。今回は、介護施設における事故対応の現場で効果的だった3つのステップをご紹介します。
事故とは?介護現場における「事故」の定義

介護現場の事故というと大きな事件を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、実際には次のような日常的な出来事が該当します。
また、これらの中でも死亡事故や医師による治療が必要なもの、感染症の集団発生、職員の不祥事などは行政への報告が義務付けられています。
【行政報告が必要な事故7つ】
1.死亡事故
2.医師による治療が必要な事故
3.感染症・食中毒の発生
4.職員による不祥事や法令違反
5.火災や災害に関する事故
6.設備トラブルによる健康被害
7.離設・行方不明
事故報告書を書く目的
「報告書=始末書」と誤解されがちですが、それは間違いです。
介護における事故報告書の目的は以下の通りです
事故報告書の5つの目的
- 事故の再発防止
- 介護サービスの質の向上
- 透明性と説明責任の確保(家族・行政への説明含む)
- 職員間の情報共有
- 法的リスクへの備え
これらを意識して報告書を作成することで、単なる形式的な書類で終わらず、実効性のある改善に繋がります。
【STEP1】事故の「原因を深掘り」する

同じ事故が起きる理由=原因分析が甘いから
「また同じ利用者が転んだ」「対策をしたはずなのに…」というとき、根本的原因にたどり着けていない可能性があります。
事故原因は3つの視点から分析する
- スタッフ視点
- 本人視点
- 環境視点
原因は「直接的」と「根本的」に分ける
| 原因の種類 | 説明 |
|---|---|
| 直接的原因 | 表面的に見える具体的な要因(例:目を離した) |
| 根本的原因 | 背景にある構造的な要因(例:配置の問題・人手不足) |
【具体例】
食堂にて独歩禁止の認知症の方が、スタッフが目を逸らした瞬間に転倒していた。
スタッフ視点:(直接)目を逸らしてしまった (根本)他利用者に呼ばれた
本人視点:(直接)一人で歩いてしまった (根本)認知症がある
環境視点:
(直接)転倒された方の食席がスタッフから遠く見えにくい場所にある
(根本)一人では立ち上がらないだろうと思い込みどこでもいいと考えていた
原因の深掘りには、「なぜ?」を5回繰り返す(5WHY分析)の手法が有効です。
根本的原因か判断する方法は、
因果関係が逆も成り立つか?で考えます。
根本的要因を探す際は「なぜ?」を唱えていきますが、反対から「だから、〜だ」で無理なく遡る事ができれば逆の因果関係が成り立つことになります。
例えば、
「目を逸らしてしまった。」→なぜ?→「他利用者に呼ばれた。」
「他利用者に呼ばれた。」→だから→「目を逸らしてしまった。」
直接的原因が解決しても現状の回復にしかならず、問題が再発する可能性が大きいです。よって、再発防止には根本的要因に対策を打つ必要があります。
事故報告書に記載する際、根本的原因のみを書くだけでもいいですが、上記のように直接的原因も記載されていれば繋がりが見えてきます。他のスタッフも見るものなので両方記載するほうが良いでしょう。
【STEP2】具体的な対策を立てる:チームワークがカギ
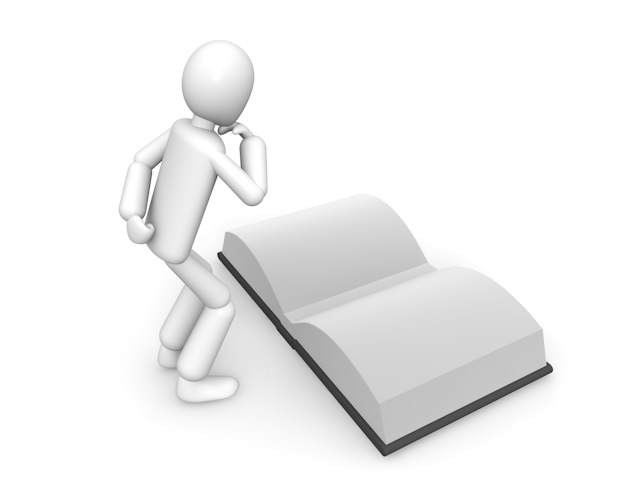
対策を立てる際は、「誰が、いつ、どこで、何を、どのように」まで具体化することがポイントです。
でなければ、誰が実行するのかわからず対策を挙げて終わりになってしまいます。
立てた対策は、日々徹底して行い、記録に残しましょう。振り返りの際、見返す為です。
【例】転倒事故の対策
- スタッフの対策
→ 毎食時、食堂担当のスタッフは危険度が高い利用者を優先的に対応する
→ 食堂に2名スタッフが配置出来るように、本日フロア責任者が業務プログラムを作り直す - 本人の対策
→立ち上がった理由を3日間本人に確認し、記録する。最終日にフロア責任者が分析しトイレ誘導のタイミングを調整する - 環境の対策
→ 本日、死角になる席のレイアウト食堂担当スタッフが変更する
→ 1ヶ月かけて全スタッフに危険予知訓練をする 主催者:管理者
▷ 危険予知訓練(KYT)とは?
利用者のADL(日常生活動作)から事故リスクを予測し、対応策を事前に考える訓練。未然防止の意識を高めるのに効果的です。
【STEP3】振り返りと再評価を習慣化する:継続的なチームの協力体制をつくる

対策を立てたら「実行→記録→振り返り」が重要です。
- 1週間後に再発の有無をチェック
- 再発していれば、分析が不十分だった証拠。再度、原因を見直す【STEP1】に振り返る
振り返りの習慣化
申し送りの後やシフト交代時に「事故カンファレンス(10分間)」を設けましょう。日常業務に組み込むことで、継続しやすくなります。
事故を減らす「仕組みづくり」がカギ
現場と方針のズレに悩んでいる管理者の方にとっても、この3つのステップはスタッフの意識を揃え、理想のケアを形にしていくヒントになるでしょう。
3ステップは一時的な対応ではなく、仕組みとして定着させることが重要です。
▷ 実践例
- STEP1:現場検証を事故発生時に必ず行う(原因の分析)
- STEP2:その場で対策を話し合い、報告書に記載(対策を決める)
- STEP3:記録ノートやSNSで実施状況を可視化し、毎日振り返る(振り返りをする)
「対策して終わり」ではなく、「動いて、見直して、改善する」サイクルを回していきましょう。
事故対応におけるチームワークの具体的メリット
チームワークを強化することで、以下のメリットがあります。
- 事故リスクの早期発見と迅速な対応
- スタッフ間の情報共有がスムーズになりミスが減る
- 家族対応においても一貫した説明が可能になる
- スタッフの心理的負担が軽減され、モチベーションが上がる
まとめ:事故再発防止に必要なのは“気づき”と“継続”、そして“チームの協力”
介護施設で事故ゼロを目指すのは簡単ではありませんが、チームワークを強化し、事故対応の仕組みを継続的に改善していくことで、事故件数は確実に減らせます。
スタッフ同士が支え合い、前向きに取り組む姿勢こそが現場を守る力となります。ぜひ積極的にチームの協力体制を築き、スタッフ育成や人材採用にも注力してください。
書籍紹介
介護現場でも使える問題解決に役立つ本です。
是非、参考にしてください。

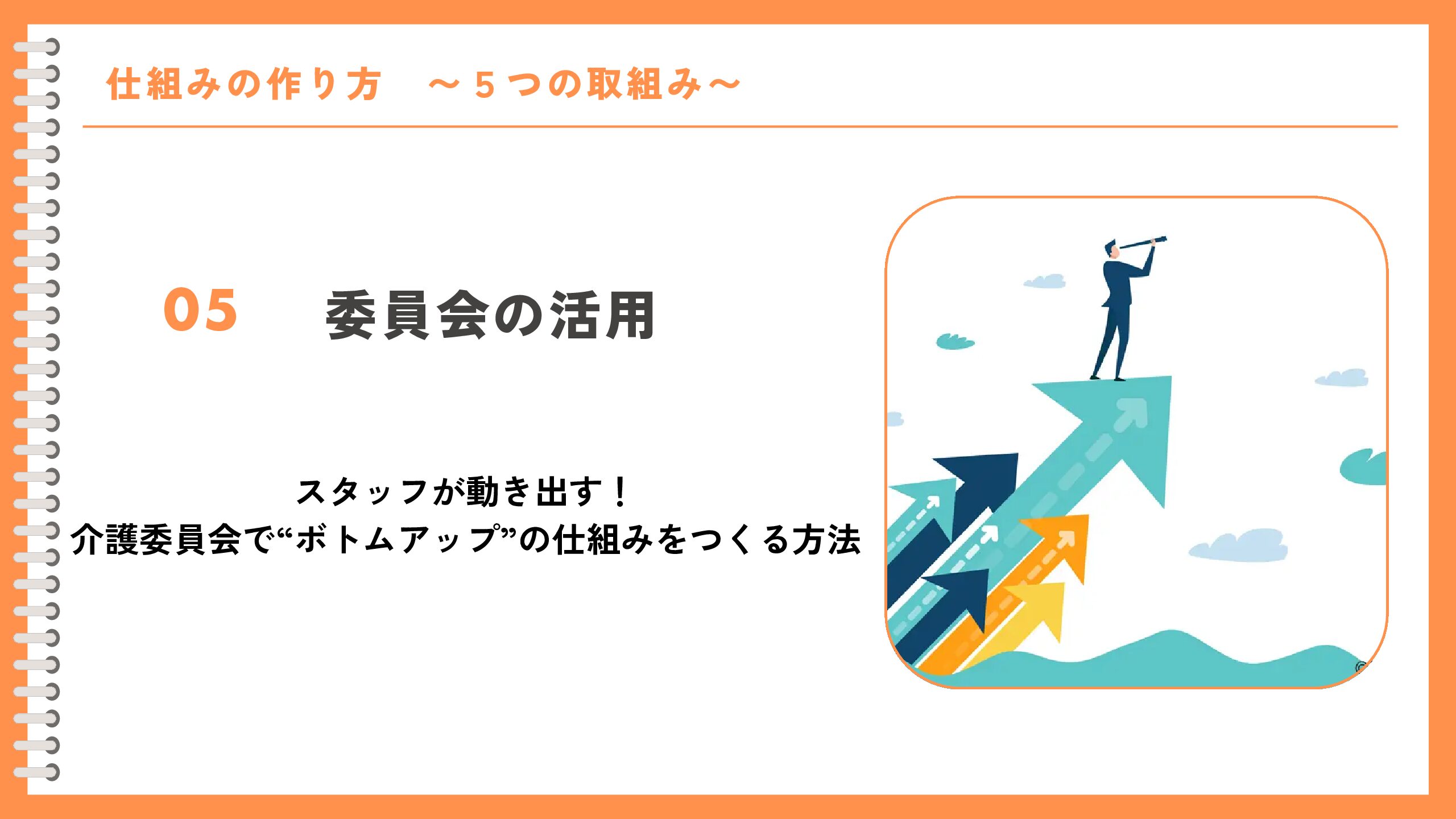

コメント