高齢者の“ちょっと気になる言動”…それ、認知症じゃなくて精神疾患かも?
高齢者と日々関わる介護職の中で、
「この利用者さん、うつ病かも…?」
「認知症とは違うような気がするけど、何だろう?」
といった“モヤモヤ”を感じた経験はありませんか?
近年、「精神疾患の患者数が増加している」というニュースをよく目にするようになりました。
これは、診断基準の見直しや精神疾患に対する社会的理解が進んだことが背景にあるといわれています。
つまり、「診断を受けていない精神疾患の高齢者と接している可能性」が私たちの周囲に広がっているのです。
そんなときに役立つのが『精神疾患にかかわる人が最初に読む本』
本書はタイトルの通り、精神疾患について「最初に学ぶ人」のために作られた入門書です。
以下のような特徴があります:
- 各症状を1ページに簡潔にまとめている
- イラスト付きで視覚的にもわかりやすい
- クイズ形式で“どう接すればよいか”を実践的に学べる
「症状の説明だけではなく、実際にどう行動すればよいかを教えてくれる」点が大きな魅力です。
実体験:認知症ケアのつまずきが“精神疾患の視点”で解決!
筆者自身、ある高齢者の方の言動が認知症とは異なる気がして対応に悩んだことがありました。
しかし、この本を読んだことで、精神疾患を疑う視点を持つことができ、対応を変えるきっかけとなりました。
認知症と精神疾患は似たような症状を示すことがありますが、アプローチ方法は全く異なります。
介護職がこの違いを理解し、知識を持っておくことは現場で非常に重要だと実感しました。
読者の口コミ紹介(楽天レビューより)
「精神科の用語って難しいけど、この本はイラストで理解できた」
イラストが豊富で具体的な場面が想像しやすい。教科書よりも実践的で、一気に読み終えました。
「知識がない自分でも読みやすい」
堅苦しい専門書とは違い、初心者でもスラスラ読めました。職場の“あの人”も、もしかしたら…と気づきを得ました。
「深く学びたい人には物足りないかも」
タイトル通り、初心者向けです。時間がないけど精神疾患について学びたい人にぴったり。
マイナスポイント(デメリット)
本書は初心者向けに設計されているため、以下の点で物足りなさを感じる人もいるかもしれません。
- 症状ごとの解説が浅めで専門性に欠ける
→ 本格的な知識や診断プロセスを学びたい人には不向きです。 - 内容の多くがイラストと概要中心
→ 「理論的に学びたい」「根拠を知りたい」と思う方には物足りない可能性があります。 - ページ数が少なく、情報量も限られている
→ 一冊で完結する“教科書的な一冊”ではなく、“入り口”としての位置づけです。
このため、精神科医や心理カウンセラーを目指す方、より専門的な学習を希望する方には、ステップアップとして別の専門書を併用することをおすすめします。
どんな人におすすめ?
- 高齢者と日々関わる介護職や福祉職
- 認知症との違いに迷うことがある方
- 精神疾患の知識をこれから身につけたい方
- 家族や身近な人の変化が気になる方
- 「精神疾患かも?」と思っても対応が分からない方
リーダーとして「後輩にどう伝えるか」に悩むあなたにも、症状の背景を理解するこの一冊は、後輩育成の視点でも役立ちます。
まとめ|精神疾患の“入り口”として、まず読むべき一冊!
精神疾患のある方との関わりは、ときにとても難しく感じます。
でも、それは「知識がないことによる不安」が原因かもしれません。
『精神疾患にかかわる人が最初に読む本』は、
難しい専門用語を使わずに、すぐに現場で役立つ視点と接し方を教えてくれる一冊です。
「どうしたらいいかわからない」と壁にぶつかったあなたにこそ、手に取っていただきたい本です。
書籍情報
書名:精神疾患にかかわる人が最初に読む本
著者:一般社団法人メンタルヘルス協会 監修
出版社:翔泳社
発売日:2023年
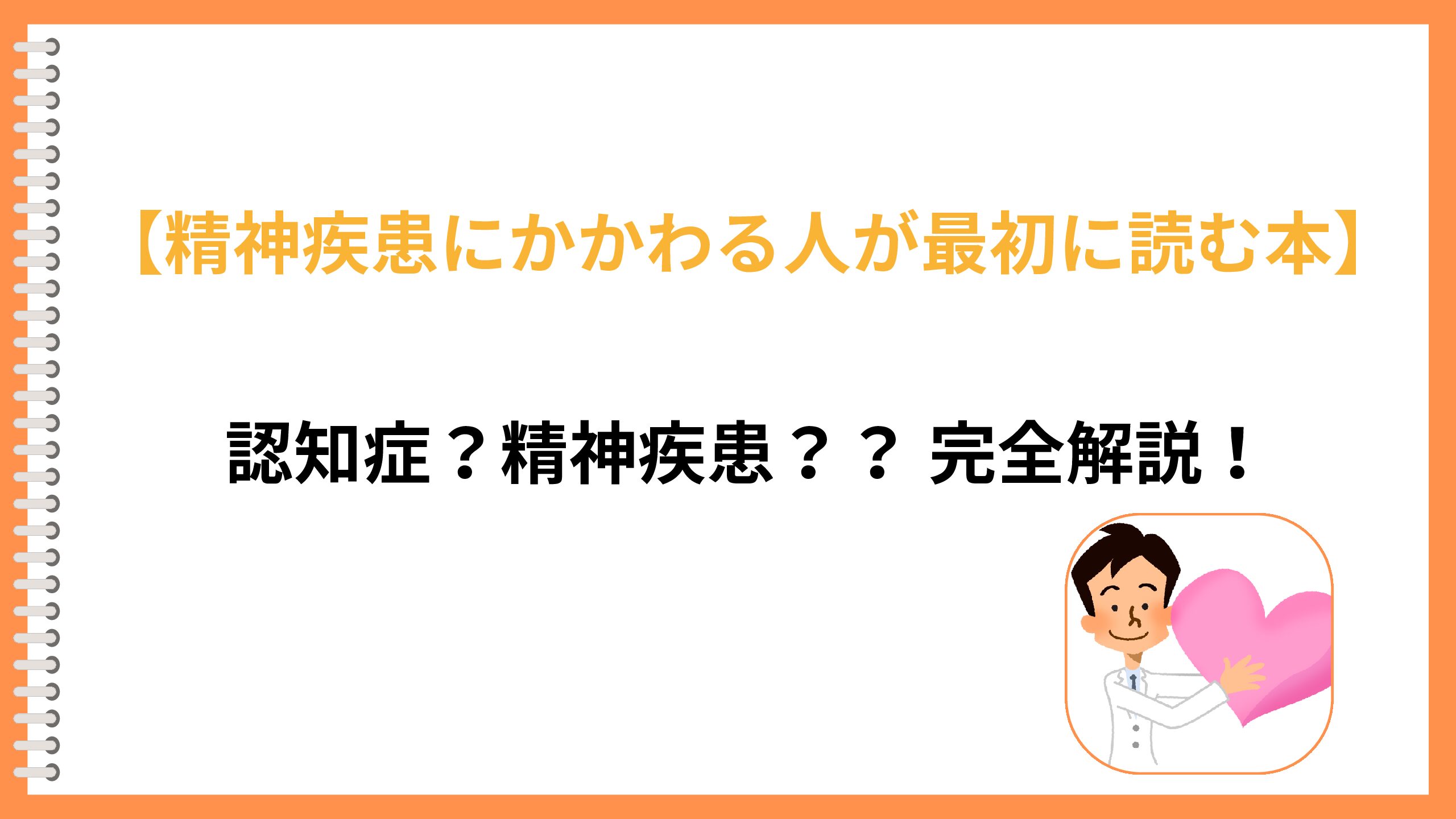

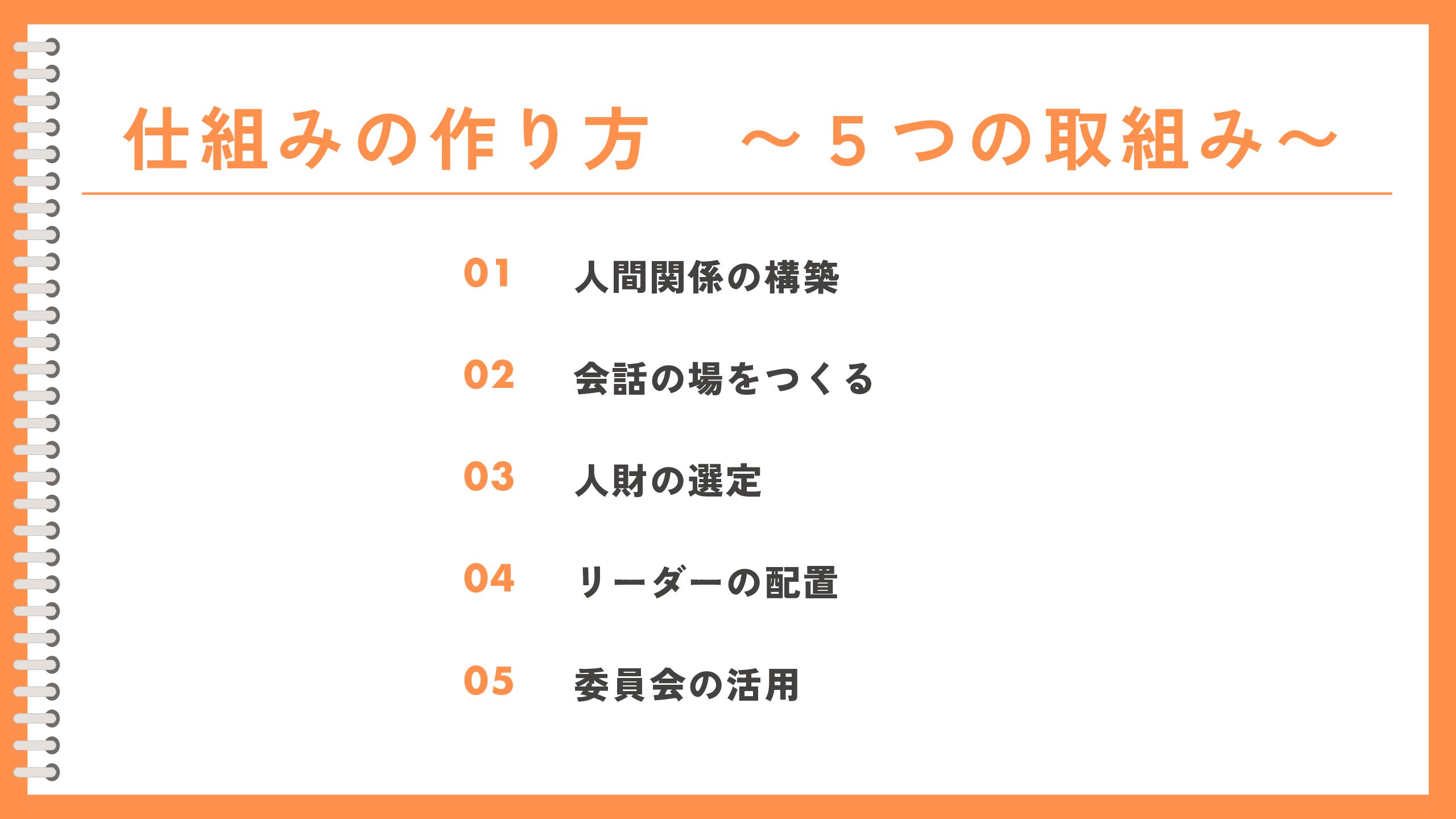
コメント