認知症の方が施設に入居されると、本人も職員も戸惑い、不安を感じることが多いですよね。
特に環境が変わることは認知症の方にとって大きなストレスとなり、BPSD(行動・心理症状)が強く現れることも珍しくありません。
私が有料老人ホームで9年間、数多くの認知症の方と関わってきた経験から言えることは、「生活環境を整えること」が認知症ケアの土台であり、最初にすべき大切なケアだということです。
今回は、施設入居時に特に意識したい「認知症 生活環境づくり 7原則」を具体的に解説します。
施設職員はもちろん、ご家族や関係者の方も参考にしていただければ幸いです。
認知症ケアのゴール:安心して安定した毎日を過ごしてもらうこと
認知症ケアの最終的な目標は、「認知症の方の日常生活を安定させること」です。
そのためには、以下の2つが特に重要です。
・BPSD(行動・心理症状)を軽減する
・生活環境を整える
今回は、「生活環境づくり」に注目し、施設入居時にすぐに実践できる7つの原則をご紹介します。
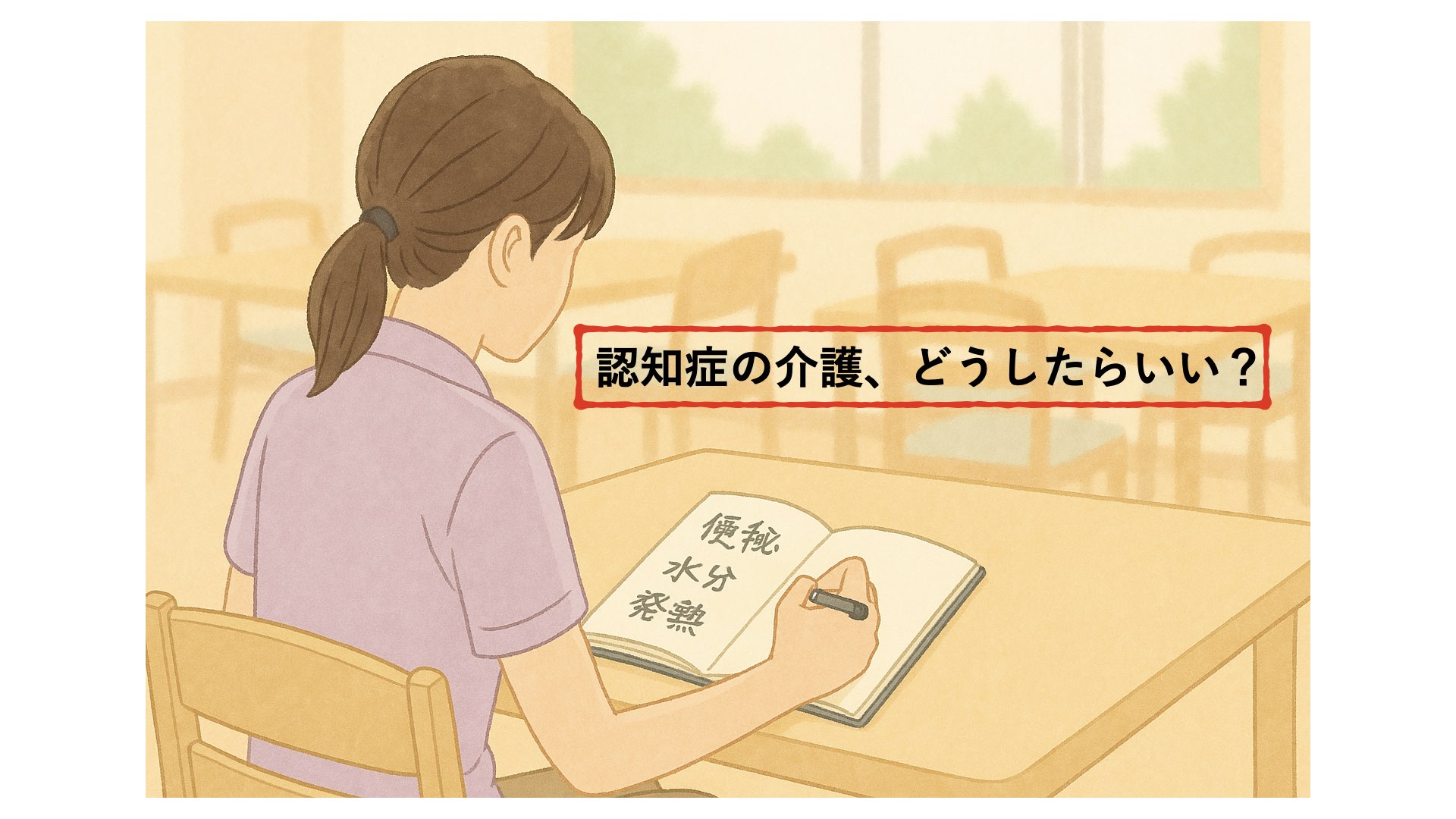 BPSD(行動・心理症状)を軽減するポイントは?
BPSD(行動・心理症状)を軽減するポイントは?
認知症 生活環境づくり 7原則:施設入居時に職員が意識すべきポイント
認知症の方は環境の変化に敏感で、見知らぬ場所や人との接触に不安を抱きやすいものです。
そのため、施設入居という大きな変化は本人にとって混乱や不安の原因になりがちです。
以下の7原則を押さえてケアにあたることで、「ここは安心して過ごせる場所だ」と感じてもらえる生活環境づくりができます。
1. 環境を変えないことを最優先にする
入院、ショートステイ、引越しにより住む環境が変わることは、認知症の方にとって大きな不安となります。 認知症状により、なぜ自宅を出ないといけないのかわからないから尚更です。自宅で過ごしていただくことが1番ですが、いろいろな理由があり、そうはいかないのが現実です。
ご自宅を離れることになった際は、下記2〜7の取り組みを施設で行いましょう。
ただ、親族の方や介護職員等は「どうすれば自宅で過ごしてもらえるのか?」を考える事は大切です。
2. 生活習慣はなるべく変えない
長年続けてきた生活リズムや習慣(例えば夕食時の晩酌や朝の新聞)をそのまま続けてもらうことが大切です。
健康の観点も大切ですが、本人らしく過ごす時間の確保が、認知症の進行予防にもつながります。
3. 人間関係を急に変えない
入居によって家族や地域のつながりが途絶えると、不安や孤立感が強まります。
私達も新しい組織やグループに入ると落ち着きません。挨拶をして徐々に打ち解け仲間が出来ます。ただ認知症の方には難しいです。スタッフが他入居者との仲介役をしないと孤立してしまいます。まずは挨拶から行い、同じテーブルで食事をする。レクに参加しそのままお茶タイムをする。などの工夫が必要です。
入居して間もない時は家族との面会頻度を多めに設け、徐々に施設内の人間関係を築けるようになってきたら回数を減らすようにしましょう。
4. 三大介護(食事・排泄・入浴)は基本通りに行う
認知症の方も、できる限り「普通の生活」を送ることが大切です。
食事・排泄・入浴という三大介護も、無理に特別対応するより、今まで通りの流れを重視しましょう。
例えば、過度な機械浴の導入がかえって不安を招くこともあります。
認知症ケアにおいては「特別扱い」ではなく、「自然な生活の継続」が安定への近道です。
 利用者主体の介護とは?
利用者主体の介護とは?
 尊厳を保持する食事介助とは?
尊厳を保持する食事介助とは?
 排泄介助で尊厳を守るには?
排泄介助で尊厳を守るには?
 入浴介助×尊厳 その人らしさを支える方法
入浴介助×尊厳 その人らしさを支える方法
5. 個性的な空間づくりをサポートする
認知症の方にとって、自分らしさを感じられる空間は、安心感とアイデンティティの回復につながります。
可能であれば、以前使用していた家具や日用品、趣味のアイテムなどを持ち込んでもらいましょう。
よく聴いていた音楽を流す、慣れ親しんだ色の布団を使うなど、細かな工夫が「ここは自分の居場所だ」と感じるきっかけになります。
6. 一人ひとりの「役割」をつくる
認知症の方にも「人の役に立っている」という感覚が必要です。
その人がかつてしていた仕事や趣味、今できることをアセスメントし、小さな役割をつくっていきましょう。
役割作りの着眼点:
・かつてやってきたこと(趣味、仕事等)
・今の身体でできること
・周りから認められること
(「◯さん、手先が器用ですね。」その場合、野菜の皮むき等の役割を担ってもらう)
役割を持つことで、「自分は必要とされている」という前向きな気持ちが芽生え、BPSDの軽減にもつながります。
7. 一人ひとりの関係づくりを大切にする
「3. 人間関係を変えない」と重複するところはありますが、
施設という新しい環境で、新たな人間関係を築くサポートは必須です。
ただし、認知症の方は自然に関係性を築くのが難しいことも多いため、スタッフの介入がカギになります。
ポイントとなる関係性:
- 共感してくれる人(他の認知症の方など)
- 規範となる人(見本になれる入居者)
- 頼れる人(職員や看護スタッフ)
✅ 共感してくれる人=認知症の他入居者
認知症の方は、相手の話を遮ったり否定したりすることが少なく、自然と笑顔(愛想笑い)で対応される場面も多く見られます。これは、会話の内容が正確に理解できていないことが要因とも言われていますが、それでも「否定されない安心感」を与えてくれる存在です。
たとえ名前を覚えていなくても、食事を同じテーブルでとり続けることで「顔なじみ」として安心感が生まれ、落ち着きに繋がります。
✅ 規範となる人=面倒見の良い自立された入居者
新しい環境では「どう動けばいいか分からない」ことが多いもの。そんな時、体操などの動作を見せてくれるような“お手本”となる入居者がいると、認知症の方も安心して行動を真似することができます。
関係性が築かれることで、その方が“頼れる仲間”となり、集団生活への参加意欲も高まります。
✅ 困ったときに頼れる人=介護職員やスタッフ
介護職員との信頼関係も、日々のケア(入浴・排泄・食事など)を通じて少しずつ構築されていきます。認知症の方が不安そうにしている場面や困っている時には、すかさず声をかけ、手助けをすることが重要です。
小さな積み重ねが「ここにいれば安心」という信頼に変わり、認知症の方の生活の安定に繋がっていきます。
このような関係づくりを通じて、「ここでの生活も悪くない」と感じてもらえるような環境を整えましょう。
まとめ:認知症 生活環境づくり 7原則は「いつもの暮らし」を支えること

認知症ケアの7原則は、特別な技術や道具を使うのではなく、本人がこれまで通りの生活を続けられるよう支える視点が大切です。
環境や習慣、人間関係をできる限り変えず、本人らしい毎日を尊重することが最大のケアとなります。
介護現場で「この支援で本当に本人のためになっているのか?」と迷ったときは、ぜひこの7原則に立ち返ってみてください。
 【実践】家にいるかのような雰囲気をつくるコツ!
【実践】家にいるかのような雰囲気をつくるコツ!



コメント