はじめに
介護施設の現場運営において、「介護観のズレ」はしばしばチームの足並みを乱す原因となります。
特に影響力のあるスタッフとの価値観のギャップは、現場の空気感やサービスの質に直結するものです。
しかし、「合わない=辞めてもらう」という短絡的な選択だけが正解ではありません。
“人を活かす視点”からの組織づくりこそが、理念を根づかせるための第一歩です。
本記事では、「介護観が合わないスタッフ」への具体的な対応法と、理念に沿った組織づくりの考え方を解説します。
介護観が合わない職員が組織にもたらす影響とは?
リーダーの介護観がズレているとどうなる?
まず注意したいのが、リーダーやベテラン職員の“介護観”です。
もしその人の価値観が施設の方針や理念とズレている場合、現場全体にその影響が波及する可能性があります。
たとえば、
・「早く終わればいい」
・「このやり方が昔から一番効率的」
といった言動が、暗黙のルールとして現場に染み込んでしまうと、理念に沿ったケアの実践は難しくなります。
「現場の空気」をつくるのは“職位”ではなく“影響力”
職位の高低にかかわらず、実質的に周囲に影響を与えている“キーパーソン”が誰なのかを見極めることが重要です。
その人の介護観が施設の方向性と一致しているか、日々の言動に注目しましょう。
「一生懸命やってるから…」で見過ごす危険性
よくあるのが「ベテランだし、一生懸命やってくれてるから…」と遠慮して介入を避けるケース。
ですが、それではいつまで経っても組織の変革は進みません。理念とズレた価値観が現場の“当たり前”になってしまう前に、方向性の修正が必要です。
【対応法①】影響力のあるスタッフを見極め、配置を見直す
「役割を変える=降格」ではない
役割を変えることに対して、「降格」「処遇が悪くなる」と受け止めるスタッフもいます。
ですが、ここで大切なのは“人をポジションで活かす”という発想です。
本人の強みを活かせる別ポジション例
介護観はズレていても、別の面で力を発揮できる人材は多くいます。
たとえば:
- 整理整頓が得意 → 環境委員会や物品管理担当
- 教えるのが上手 → 新人教育係
- 記録が丁寧 → 業務マニュアルの整備係
再配置によって現場が良くなった実例
たとえば、ある15年目のベテラン職員Aさん。
昔ながらの介護観を強く持っていたため、若手との摩擦が続いていました。
しかし彼女は「清掃と整理整頓」が得意だったため、衛生管理係として任命。
現場の衛生環境が改善されただけでなく、Aさん自身のモチベーションも上がり、良い影響をもたらす存在へと変わりました。
どうしても合わない場合は「異動」も選択肢に
再配置しても介護観のズレが大きく、組織への影響が懸念される場合は、異動も視野に入れた判断が必要です。
「現場の雰囲気を守る」「ご利用者の生活の質を保つ」ことを優先し、感情ではなく組織全体の健全性から決断する姿勢が求められます。
【対応法②】“価値観のズレ”を早期に見つける関係づくり
日常の信頼関係が本音を引き出す
介護観の違いは、業務の中では見えづらいもの。
だからこそ、日頃から信頼関係を築くことで、スタッフの本音や価値観が徐々に見えてきます。
小さな声に耳を傾けられる環境づくりこそ、ズレを見逃さない第一歩です。
⏬️人間関係構築に必要なポイントとは?⏬️
介護マネジメントは人間関係が9割?聞く・伝える
「会話の場づくり」で考え方の違いを可視化
スタッフの価値観を把握するには、「対話の時間」も効果的です。
- 1on1の面談で個別に話を聴く
- 委員会活動で理念や方針を語り合う
- 申し送りやカンファレンスで意見交換の土壌を整える
これらを日常業務に組み込むことで、考え方や感情のズレを早期に発見できます。
⏬️介護現場にスタッフ間で会話する場を作ろう⏬️
理念が現場に根づく5つの会話術
【対応法③】介護観の違いを“対立”ではなく“仕組み化”へ
「排除」ではなく「再活用」の視点を持つ
介護観が合わないからといって、その人をすぐに否定・排除するのではなく、“組織に合う役割”を再設計することが大切です。
適切なポジションに配置することで、その人の強みを活かしつつ、組織との摩擦を減らすことができます。
「理念浸透型マネジメント」とは?
目指すべきは、理念を語り、仕組みによって現場に根づかせていくマネジメントです。
「この施設では、こういう介護を大切にしている」と語り続け、
「そのために、こういうチーム・配置・会話の仕組みがある」と示すことで、理念が徐々にスタッフの中に浸透していきます。
「仕組みとしての人財選定」で理念が根づく
育成、配置、評価、会話……これらを仕組みとして運用することで、人によってブレないマネジメントが可能になります。
理念に沿った「人財の見極めと再配置」は、属人的ではなく、再現性のある組織づくりの土台となります。
まとめ:介護観が合わない職員への対応と組織づくりの3つの視点
介護観のズレは、対立ではなく“仕組みづくりのきっかけ”にできます。
改めて、以下の3つを意識しましょう。
- 影響力と価値観のズレを見極め、必要な配置転換を行う
- 強みを再発見し、適切な役割で本人の力を活かす
- 会話と関係性のなかで、価値観のズレを可視化できる仕組みをつくる
こうした考え方は、介護施設の理念を現場に根づかせる「理念浸透型マネジメント」の第一歩となります。
「合わない人を切る」のではなく、「どう活かすか」を考えることで、
介護の現場はもっと健全に、あたたかく、チームとして機能するようになります。
ただどうしても介護観が合わない人はいます。その場合は、退職してもらうことも視野に考えましょう。
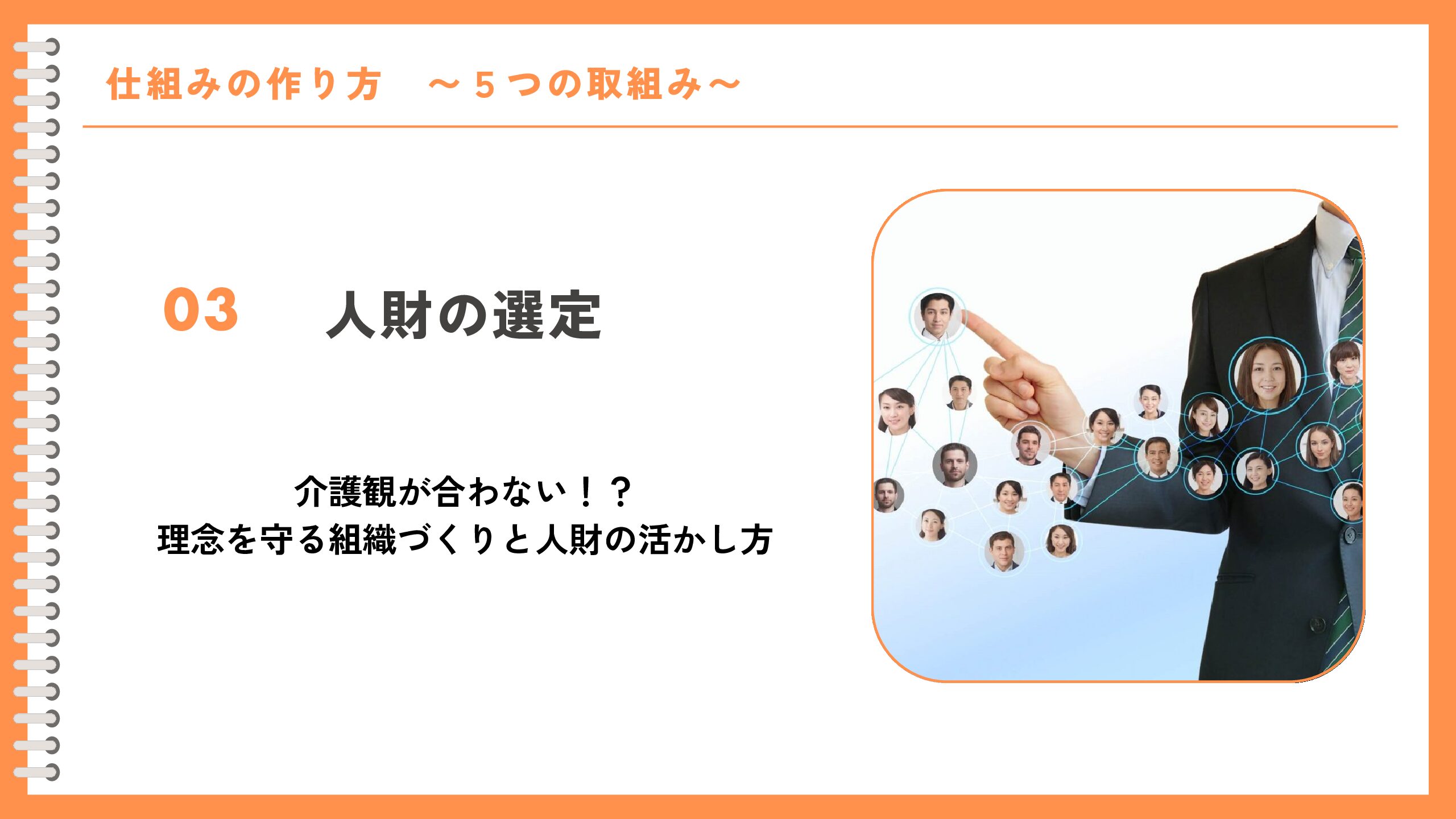
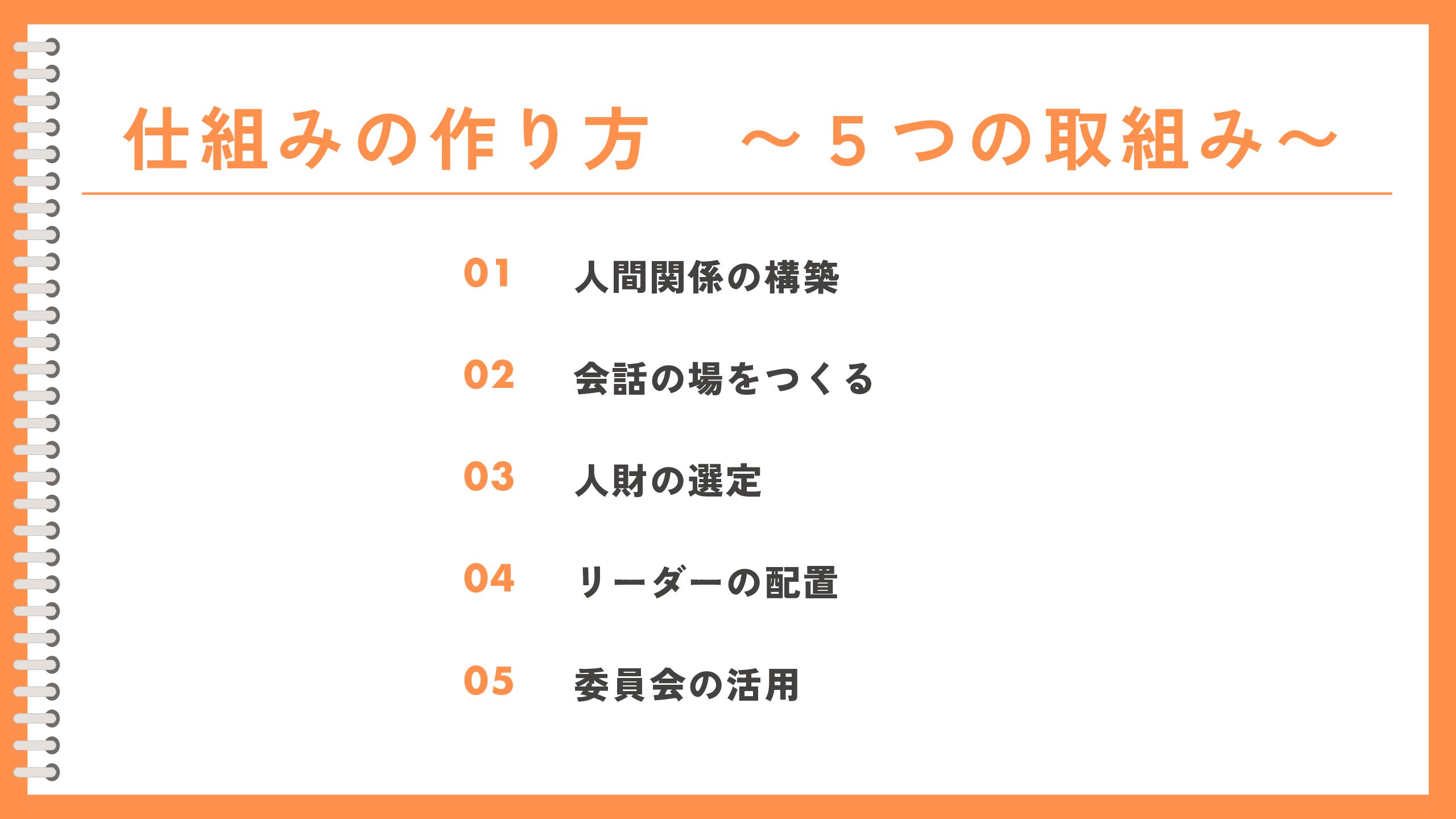
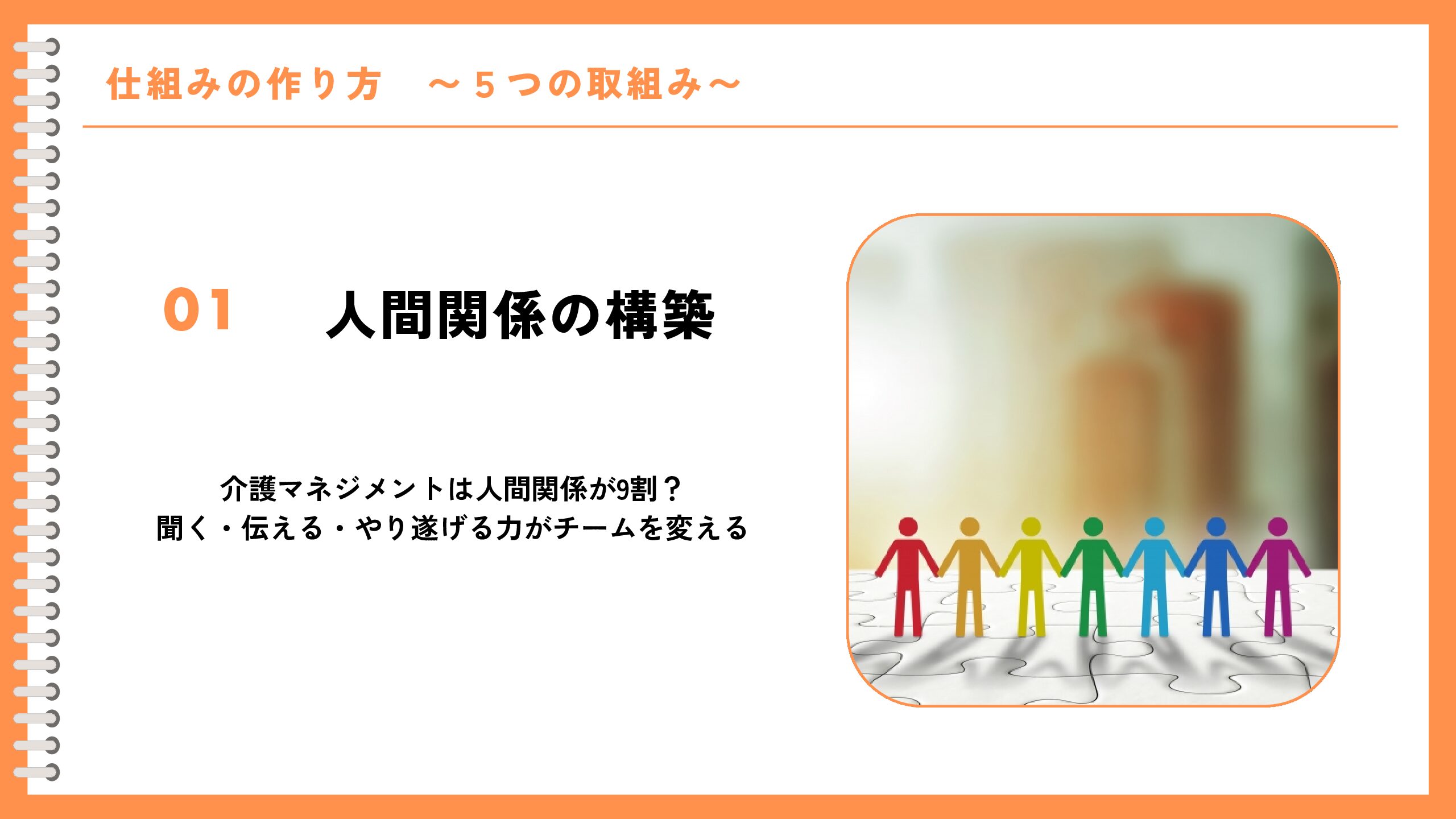
コメント