「その方に寄り添った」「その人らしさを大切に」といった理念を掲げる介護施設は多くありますが、具体的にどんな介護をすれば“良い介護”なのか、わからなくなることはありませんか?
「利用者主体の介護って何?」「やりたいことを叶えるって、実際には難しくない?」と感じている方も多いはず。
今回は、介護歴9年の私が現場で感じた「本当に利用者にとって良い介護とは何か?」を、具体的な例と共にお伝えします。
利用者主体の介護とは?本質は“普通の生活”の支援
「利用者主体」とは、利用者の希望を最優先にするという意味ではありません。
大切なのは、「その人がその人らしく生きるために、できることをできるように支援する」こと。
つまり、“自分でできることは自分でやってもらい、それを支援する”というのが、本来の意味での利用者主体です。
介護における「尊厳」とは?制度が定める介護の目的
介護保険制度の第1条には「尊厳の保持」と明記されています。
これは「個人の人格・生命を尊重し、その価値を認めるケアを提供する」という意味です。
尊厳を守る介護とは──
➡ 「普通の生活ができること」の支援であると、私は考えています。
普通の生活とは──
➡ 「誰の手伝いも必要とせず生活していた時のこと」
3大介護が重要な理由|食事・排泄・入浴の基本が“QOL”を支える
3大介護(食事・排泄・入浴) は、身体機能の維持と尊厳保持に直結しています。
たとえば、
- 食事を自分で食べる
- トイレの便座に座って排泄をする
- 自宅と同じような個浴に入る
これらを実現するには職員側の工夫が必要ですが、生活リハビリにもつながり、QOL向上を実感できる支援です。
ありがちなNGケア|スタッフ都合が尊厳を奪っていないか?
- 自分で食べられるのに食事介助してしまう
- トイレに行けるのにオムツ対応してしまう
- 理由なく、機械浴で入浴させる
こうした“スタッフ主体のケア”が蔓延すると、「介護される人」から「介護されるだけの人」になってしまいます。
実践するためのマインド|“できる前提”で考え続けることが大切
介護の本質は「できない理由を並べること」ではなく、「できる方法を探すこと」。
決めつけや先入観は、尊厳を守るケアの妨げになります。
「どうすればできるのか」を常に考えることがポイントです。
環境を変える勇気も必要
介護に対する考え方は人それぞれです。
同じ介護観(価値観)を持つ仲間がいないなら、思い切って職場を変えるのも選択肢の一つ。
あなたの考え方に共感してくれる環境は、必ずあります。
まとめ:利用者主体の介護とは“その人の人生を支えること”
利用者の尊厳を守り、“普通の生活”を支援することこそが、良い介護の本質です。
介護職として選ばれる人材になるために、まずは今日から、「目の前のケア」を見直してみましょう。
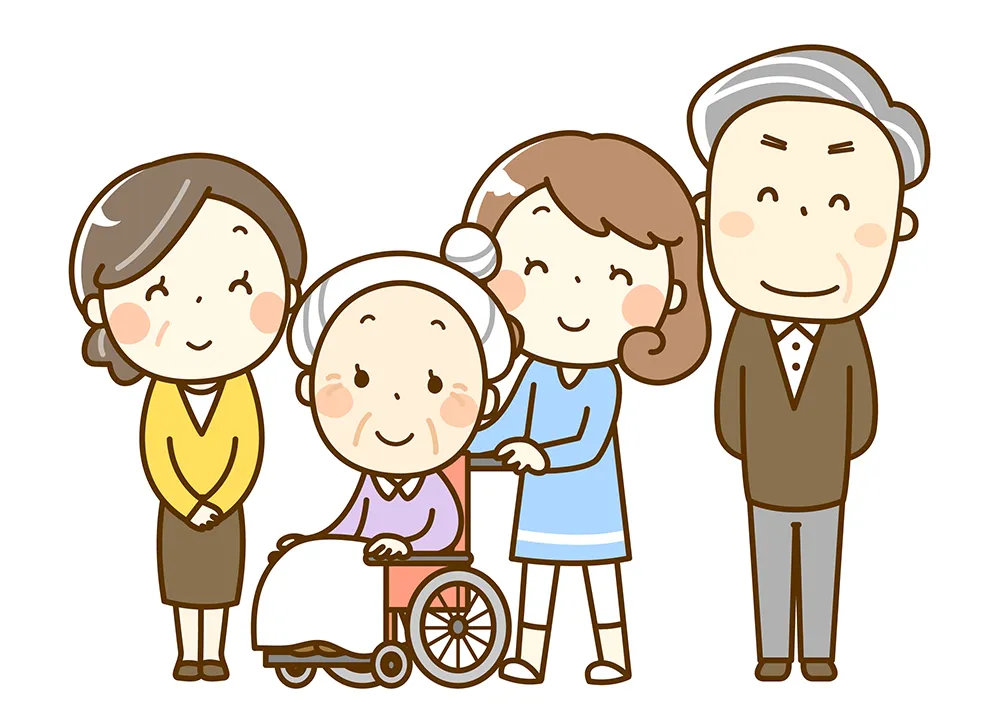

コメント